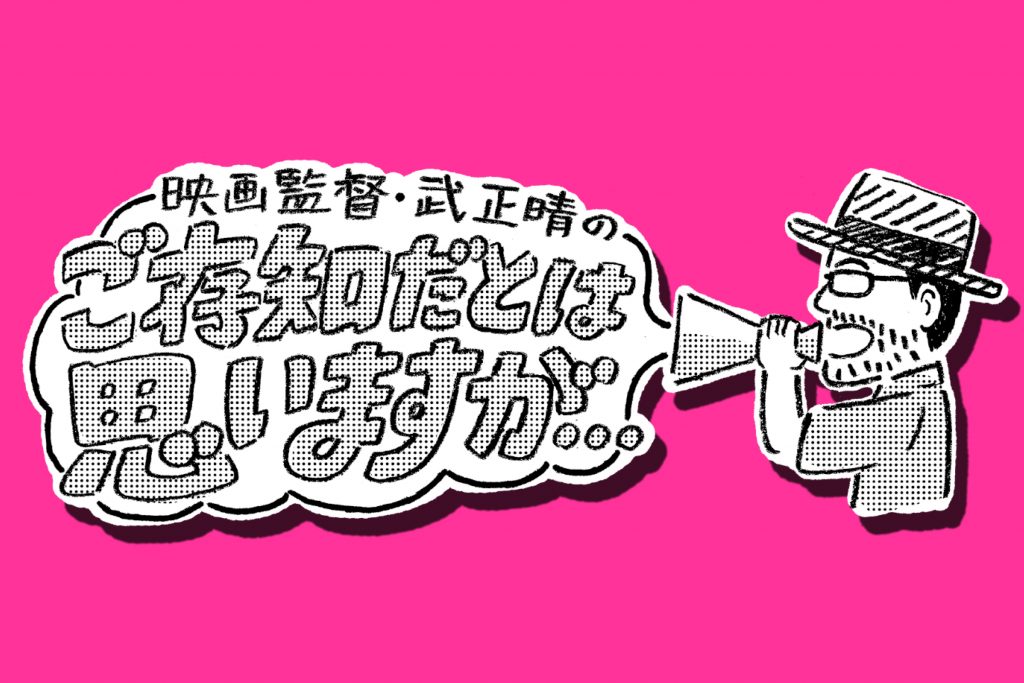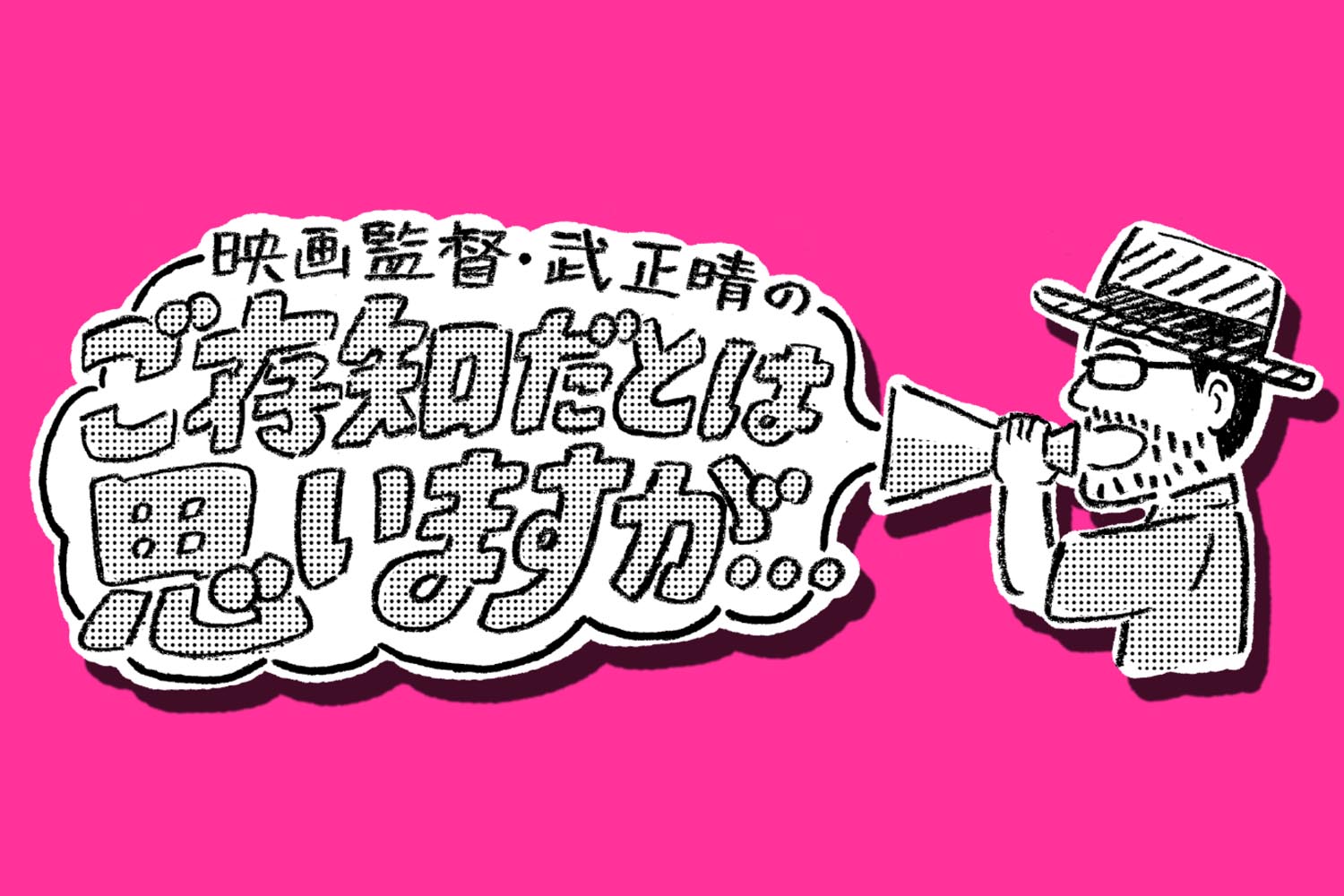
中・高・大と映画に明け暮れた日々。
あの頃、作り手ではなかった自分が
なぜそこまで映画に夢中になれたのか?
作り手になった今、その視点から
忘れられないワンシーン・ワンカットの魅力に
改めて向き合ってみる。
文●武 正晴
第3回『8 1/2(はっかにぶんのいち)』

イラスト●死後くん
____________________________
作品概要:創作に行き詰まった映画監督の苦悩を現実と幻想を交えて描く。本作はフェデリコ・フェリーニ8作目の作品。アルベルト・ラットゥアーダとの共同監督だった処女作『寄席の脚光』は1/2本と数え、8 1/2本目となることから、このタイトルがつけられた。
製作年 1963年
製作国 イタリア、フランス
上映時間 140分
アスペクト比 ビスタ
監督 フェデリコ・フェリーニ
脚色 フェデリコ・フェリーニ
トゥリオ・ピネリ
エンニオ・フライアーノ
ブルネロ・ロンディ
撮影 ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ
編集 レオ・カトッソ
音楽 ニーノ・ロータ
出演 マルチェロ・マストロヤンニ
クラウディア・カルディナーレ 他
____________________________
※この連載は2015年7月号に掲載した内容を転載しています。
イタリアのファーイースト映画祭にて
4月28日~5月2日(2015年)までイタリアのウデイーネに滞在した。第17回ファーイースト映画祭に拙作『イン・ザ・ヒーロー』と『百円の恋』が招待されたのだ。スロベニア、オーストリアに接する国境の街はヴェネチアから車で1時間ばかりの立派な小さな田舎街だった。
英雄ガリバルディの銅像に迎えられた僕は胸が高鳴った。四階席まである1200席の劇場で50本余りの極東アジア映画が上映されるのだ。連日毎回満席の観客に驚愕し、イタリアだけでなくヨーロッパ各地から駆けつけてくれるのが嬉しい。
現地のプレスから『100Yen Love』は『ミリオンダラー・ベイビー』から発想したのかと聞かれ『レイジング・ブル』に影響を受けたのだと僕は答えた。『イン・ザ・ヒーロー』は『バードマン』を意識したのかと聞かれ、まだ観ていないと苦笑した。撮影に入る前にフェリーニ監督の『8 1/2』を見直したと返答した。何人かの記者が頷いてくれていた。
フェリーニにとって8番目の単独長編監督作品を僕が最初に見たのはNHK教育テレビの名作劇場だった。母に薦められて見た『道』のジュリエッタ・マシーナに完全にイカれてしまっていた中学2年の僕には少し難しかった。ゲージュツ映画だと思ったが、正直よく判らなかった。
1987年の渋谷でフェリーニ特集上映で大学生になっていた僕はスクリーンで全作品を観るのだが『そして船がゆく』に出会った記憶や『カビリアの夜』や『崖』を字幕なしで夢中で観ていた記憶のほうが強い。
『イン・ザ・ヒーロー』は
僕にとっても8 1/2
『イン・ザ・ヒーロー』の撮影準備で2013年を終え、14年を迎えた元旦の撮影所のスタッフルームで改めて『8 1/2』を1人で見た。映画のバックステージ物の参考として見ておく必要性を強く感じていたからだ。
主人公の映画監督グイドの苦悩と現実逃避から始まる最初の3分で作品にのめり込んでしまった。何を撮ったらいいのか分からずスタッフに闇雲な指示をして、台本も書かずに愛人の元へ逃げ込むグイド。
彼の現実逃避の様々な妄想が少年時代の回想と絡まってこの映画は進んでゆく。フェリーニ監督=グイド=マルチェロ・マストロヤンニ。見事だ。撮影されることなく解体され始めた巨大セットを前にして「人生は祭りだ。共に生きよう」と映画のすべての登場人物と手を取り合って躍り続けるラストシーンに熱いものが込み上げてくる。
主人公グイドが何のために映画を撮るのか。次に何を撮ったらよいのかを思い出してゆくラストシーンに、主人公グイドのように力がみなぎってくる。少年時代のグイドがマントをなびかせて現れ、笛を吹いて行進を先導する。フェリーニ監督の盟友ニーノ・ロータのメロディーに間違いはない。
主人公グイドと登場人物達が踊り続け去っていったあと、一人残って笛を吹く少年グイドの姿を巨大スポットライトが追ってゆく。少年が去りライトが消えて映画が終わる。不覚にも慟哭しそうになった。
フェリーニ監督に感謝したかった。フェリーニを教えてくれた母にも感謝だ。『イン・ザ・ヒーロー』は僕にとっても8番目の長編作品で、短編を含めると8 1/2だった。
映画を創る意義を
感じた瞬間
映画祭の最終日。満員のお客様の拍手に劇場が包まれている。夢か幻か。4階席、3階席の人達が立ち上がって手を振ってくれている。2階席の人達が喚声を上げてくれている。僕は精一杯手を振り返し、すべての観客の皆様に拍手を送り返した。
「コングラチュレ―ション」と駆けよって握手を求める人達に囲まれた。映画を創る、さらなる意義を感じていた。映画がまた創りたくなった。観客の皆様の投票による観客賞の上位5本のうち4本が韓国映画だった。拙作『イン・ザ・ヒーロー』は12本の日本映画の中では一番高い評価をいただいたと聞かされた。『百円の恋』にも沢山の拍手をいただいた。忘れ得ない瞬間を経験できた。すべての作品上映が終わり、授賞式が始まった。スクリーンにはフェリーニ監督が写し出されていた。熱いものが込み上げてきた。
授賞式が終わり、映画祭が終わりを告げた時、夜中の2時になろうとしていたが、満席の1200人を越える観客やスタッフは余韻に浸り、帰るそぶりを見せなかった。僕は帰りの飛行機の便の都合でホテルを4時半に出発しなくてはならなかった。映画祭関係者に別れと感謝と再会の約束を告げ、劇場を後にした。
帰りがけにカンボジアの
女性監督と一緒になった
ヴェネチア空港に向かう車中でカンボジアの女性監督と一緒になった。唯一の韓国映画以外の観客賞受賞作『ラスト リール』という作品の監督さんで、40年前のクメール・ルージュ時代に粛清された映画人達を描いた作品だ。
現代のカンボジアの若者達が、未完の40年前の映画のラストシーンを完成させる自伝的作品で、僕は東京国際映画祭で拝見した。勇気ある力作である。顔見知りになっていた僕達はイタリアでの再会同様に、帰りも一緒になったのを喜びあっていた。『100Yen love』をカンボジアの映画祭で上映したいと彼女が言ってくれたのが嬉しかった。
「夫や子供達が待っているロサンゼルスに」、「イスタンブール経由で京都に」とそれぞれの帰路を返答しあった後に「シー ユ― ネクスト タイム イン カンボジア」、「イン カンボジア!」と握手を交わして、僕らは帰路に向かった。来た時よりも明らかに増えた荷物を抱えて去ってゆく、彼女の小さいながらも、力強い後ろ姿を僕は暫く眺めていた。
●この記事はビデオSALON2015年6月号より転載
http://www.genkosha.co.jp/vs/backnumber/1472.html