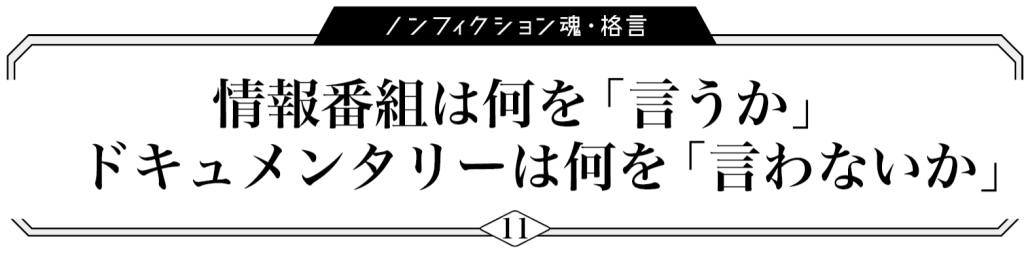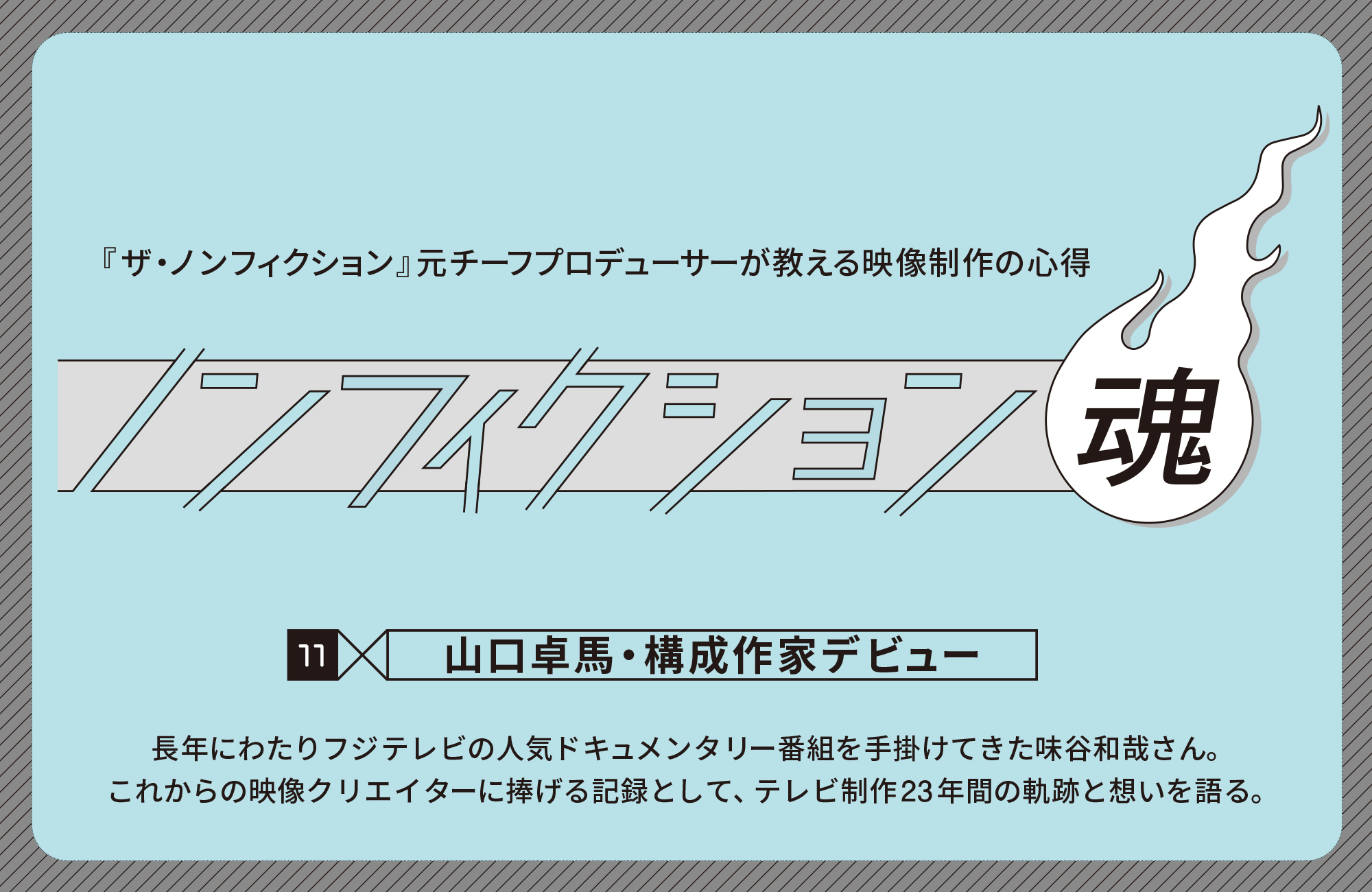長年にわたりフジテレビの人気ドキュメンタリー番組を手掛けてきた味谷和哉さん。これからの映像クリエイターに捧げる記録として、テレビ制作23年間の軌跡と想いを語る。
文 味谷和哉
1957年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、読売新聞大阪本社 社会部記者を経て、1992年フジテレビ入社。以来ドキュメンタリー畑一筋で、ディレクター、プロデューサーとして制作に携った作品は500本を超える。2003年〜15年まで『ザ・ノンフィクション』チーフプロデューサー。文教大学非常勤講師。
●主な作品と受賞歴
▶︎ディレクターとして
1993年1月 『なんでやねん西成暴動』
1993年7月 『娘のことを教えて下さい』(FNSドキュメンタリー大賞佳作)
1996年7月 『幻のゴミ法案を追う』(FNSドキュメンタリー大賞グランプリ)(ギャラクシー賞奨励賞)
▶︎プロデューサーとして
2007年6月 『花嫁のれん物語 〜地震に負けるな能登半島〜』(ニューヨークフェスティバル銅賞)
2007年7月 『負けんじゃねぇ 〜神田高校に起こった奇跡〜』(ギャラクシー賞奨励賞)
2010年10月 『ピュアにダンスⅣ〜田中家の7年〜』(USインターナショナル フィルム&ビデオフェスティバル GOLD CAMERA賞(金賞))(国際エミー賞 ノミネート)他、国内外受賞多数
ひょんなことから、新しい自分を発見したことはありませんか?
『ザ・ノンフィクション』のチーフプロデューサーになって3年半が過ぎたころ。それまで番組の構成(ドキュメンタリーでは大きな流れとナレーション原稿担当)は構成作家さんに頼んで書いてもらっていました。ドキュメンタリー界で実績のある作家さんにお願いして書いてもらった原稿を、「本直し」と呼ばれるスタッフ全員が集まってナレーション原稿を仕上げる作業を経て、ナレーション録りに入るという最終過程後、放送に至ります(NHKではナレ原はディレクターが書いているようです)。
映像の原稿は活字ではなく音声
実績のある作家さんと仕事をさせてもらい、ナレーションを書くコツのというようなものは少し分かってきた頃でした。私は新聞記者出身ですから、原稿は黙読が基本でした。映像の原稿は声に出して「なんぼ」です。活字ではなく「音声」なのです。
転職して間もないころ、最初に参加した「本直し」で洗礼を受けました。スペインで行われたバルセロナオリンピック直前、ゴールデンタイムの情報番組でスペインを取り上げていました。その最初のナレーションに腰を抜かしました。
「今、世界で最も輝いている国、スペイン」光り輝くスペインの太陽の映像に合わせて作家さんが朗々と読み上げていました。活字ではまずありえない書き出しです。活字なら「バルセロナオリンピックで、今注目を集めている国、スペイン」が精一杯でしょう。そう、繰り返しますが、ナレ原は「音声」なのです。
ひょんなきっかけでナレ原を書くことに
その衝撃から、早や15年が経っていました。仕上げの段階で、お願いしよう思っていた作家さんが、忙しくて時間が取れない、しかも、他のいつも書いてもらっている作家さんも「都合がつかない」とのことで企画者の西村朗プロデューサーから相談がありました。そこで仕方なしに言ったのが、この一言でした。
「じゃ、僕が書くよ」
この一言が運の尽きでした(運の着きかもしれません)。それまで部分的には「本直し」で原稿は書いてきましたが、一からすべてを書くのは大変な作業であることを、痛感した体験でした。
高校野球弱小校がまさかの逆転勝利
作品は、私の好きなスポーツものでした。神奈川県立神田高校の野球部(2009年統合によって平塚湘風等学校に)が舞台です。ここに隻腕の投手がいるというのです。しかもキャッチャーは双子の兄。しかし、この学校はこの10年公式戦で勝ったことがない弱小校でした。しかも入学者の4割が途中で退学するほど、学校は荒れていたのです。少なくともこの試合までは…。
最初は、申し訳ないですが「どうせ今年も甲子園予選の初戦で負けるだろうから、ナインたちの野球への思いやご家族をしっかり描いて仕上げるかな」くらいの思いでした。
でも、そこはドキュメンタリー。どうなるか、分からないものです。2006年甲子園への夏の神奈川県予選。神田高校は初戦、9回2アウトから2点差をひっくり返し、見事な逆転勝利を飾ったのです。まさにドラマチックな展開です。

あえて1年後に設定した放送
現場の勝 亮輔ディレクターからは、「すぐ放送を」との要請があり、検討しました。確かにこのまま弱小校の大逆転劇を、放送することもできたでしょう。しかし、その時の私はどこかそれだけで仕上げるにしては、この素材はもったいないと感じていました。すでに作家モードに入っていたのかもしれません。
この試合のヒーローたちが卒業して社会に出た上で、1年前の「あの夏」を思い出す構成にしたかったのです。きっと「日常の中にこそヒーローが存在する」との感覚があったのだと思います。現場には「申し訳ないが就
職するまで追いかけてほしい。放送は1年後にしたい」と伝えました。現場もその「思い」をわかってくれました。いいスタッフに恵まれたものです。
だから事実はおもしろい
今思うと、この番組には不思議と現実と思えないような要素がそろっていました。まずは同校の松山大介監督が異色の先生で、エリートサラリーマンから「悔いのない人生を」と転職した人物であったこと。
当初は隻腕の投手を中心に描くつもりが、そこはノンフィクションで、最後は9回2アウトから人生初めての公式戦バッターボックスに立った、補欠の佐藤和成君がこの試合のヒーローとなるのです。だからこそ、「事実」は面白いのです。
印象的な場面があります。予選本番前の練習試合で覇気のない試合をした後、部員を集めて監督が初めてその年で監督を退くことを告げます。
「6年間やってきた俺の思いに1年や2年のお前たちの思いが勝てるわけない。でもな、それじゃだめなんだよ。俺の思いを上回ってくれないと…」
そして、最後に涙を流しながら、ぽつりとこう言い放ちます。
「負けんじゃねぇ」
それは部員だけでなく、自分へ、そしてすべての人へ向けたメッセージであると私は受け止めました。だから、タイトルにしたのです。この言葉が火をつけたのか、部員たちは真剣に練習に取り組むようになるのです。
最後まで諦めなかった者へのプレゼント
さて、2007年6月に仕上げの段階になりました。そもそもこの年、いわゆる「特待生」の問題で高校野球界も揺れていました。そんな中、名もなき神奈川の公立校の1勝は「一陣の涼風」でもありました。
作家としての私は、そんな思いもあってタイトル前のナレーションを大きく振りかぶりました。
「この番組をすべての野球ファンに捧げる」
そして番組最後のナレーションをこう締めました。9回2アウト、人生初打席で逆転のきっかけのヒットを放った佐藤君。それは補欠でありながら、毎日の素振りを欠かさなかった彼を念頭に置いたものでした。
「勝利の女神は、最後まで諦めなかった者にだけ、時々、奇跡ともいうべきプレゼントをくれるのだ」
構成作家として徹夜で原稿を書き上げたところで、家内が起きてきました。私が「疲れたよ」というと、家内はこう言いました。
「楽しそうに見えるわよ」
ひとつの番組が教えてくれたドキュメンタリーの真髄
番組の反響は予想以上のものでした。強面の的場浩司さんのナレーションもピタリとはまり、当時阪神タイガースの藤川球児投手(現監督)がブログで紹介してくれたり、ネット上でも盛り上がりました。しかも、ギャラクシー賞の奨励賞までいただき、私のペンネーム「山口卓馬」の作家デビューは、有難きものとなりました。
この体験で分かったことがあります。ドキュメンタリーは「視聴者に何を感じてもらうか」がとても大切なことだと…。