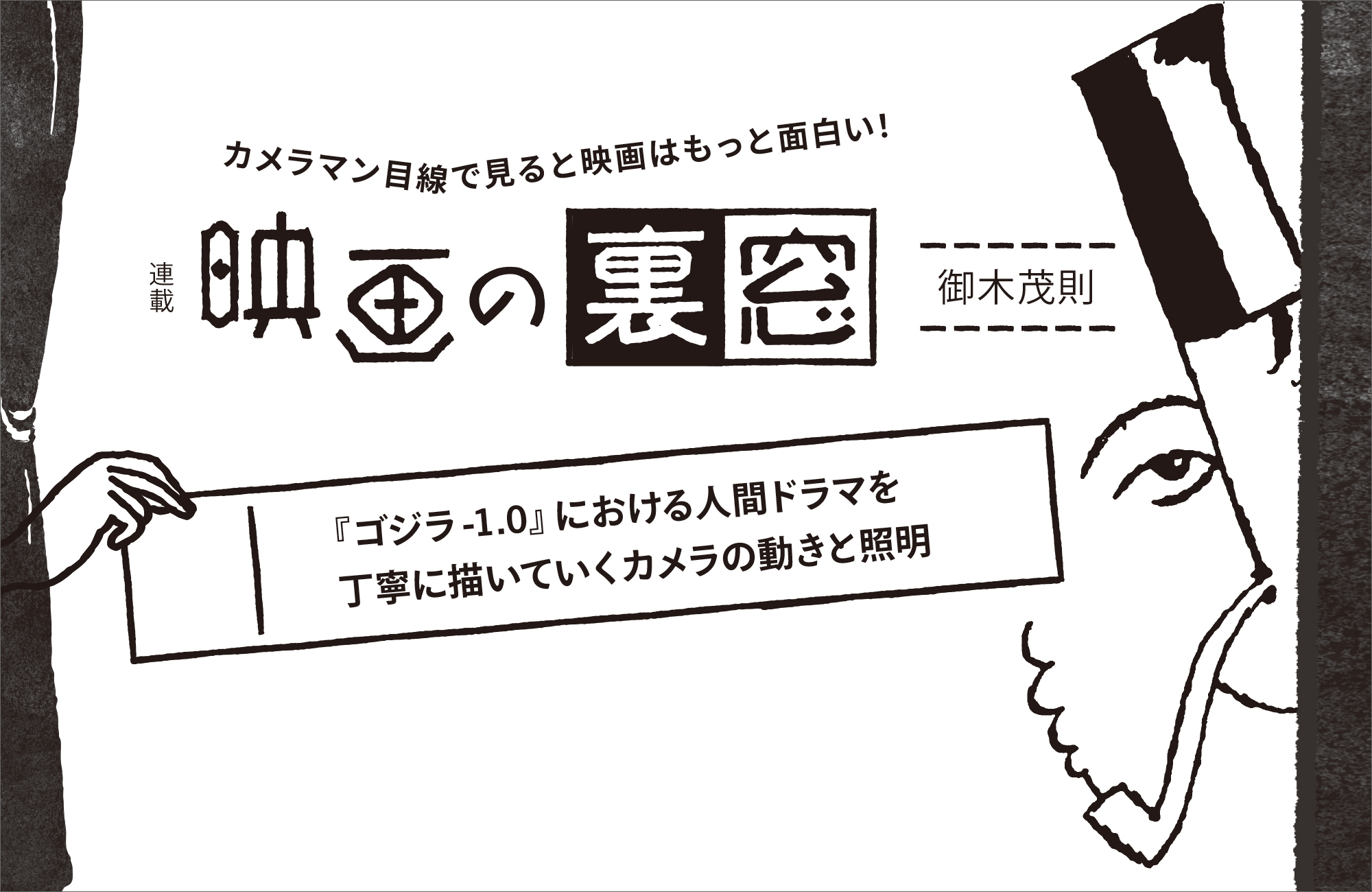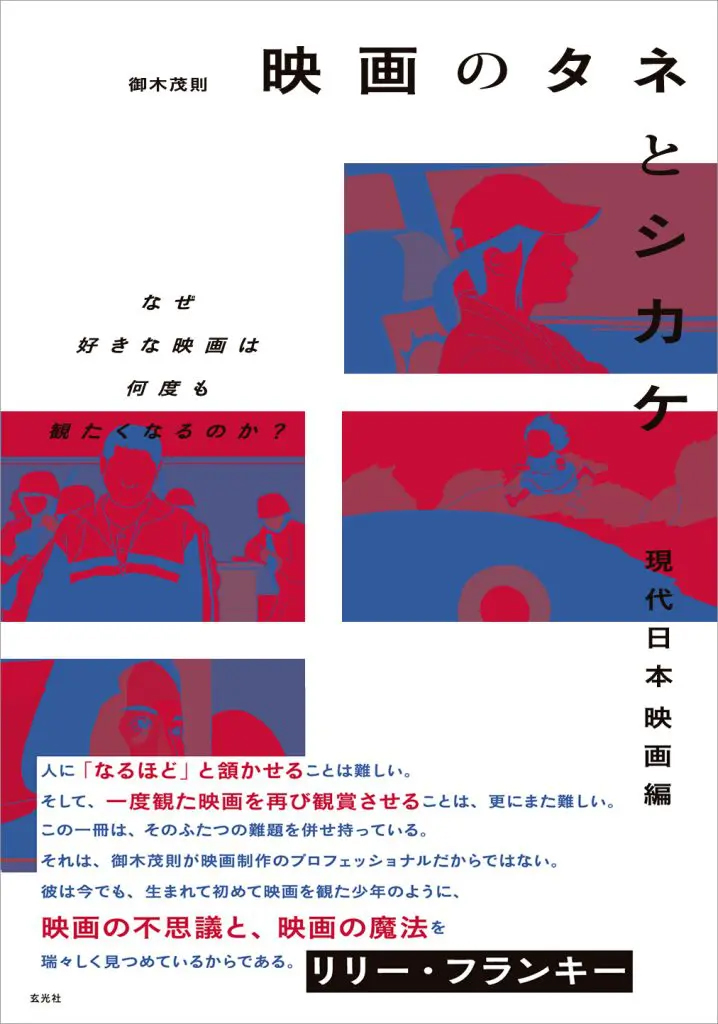御木茂則
映画カメラマン。日本映画撮影監督協会理事。神戸芸術工科大学 非常勤講師。撮影:『部屋/THE ROOM』『希望の国』(園子温監督)『火だるま槐多よ』(佐藤寿保監督) 照明:『滝を見にいく』(沖田修一監督)『彼女はひとり』(中川奈月監督) など。本連載を元に11本の映画を図解した「映画のタネとシカケ」は全国書店、ネット書店で好評発売中。
『ゴジラ-1.0』(山﨑 貴/23年)は第二次世界大戦末期、敷島浩一(神木隆之介)が特攻に向かう途中、操縦する零戦の故障を理由に大戸島の守備隊基地に着陸することから始まります。ベテランの整備兵・橘 宗作(青木崇高)は零戦に故障がないので、敷島が特攻から逃げてきたことに気がつきます。
その夜、全長15mの巨大生物「呉爾羅」(のちのゴジラ)が基地を襲います。敷島は零戦の機関銃で呉爾羅を撃つことを橘に頼まれますが、敷島は目前にした呉爾羅への恐怖で撃つことができません。そして敷島と橘を残して守備隊は全滅します。
2年後の1947年、復員した敷島は秋津淸治(佐々木蔵之介)・野田健治(吉岡秀隆)・水島四郎(山田裕貴)と戦争中に敷設された機雷を掃海する仕事をしています。敷島は特攻から逃げたことと、呉爾羅への恐怖で多くの人を死なせたことに負い目を感じていましたが、大石典子(浜辺美波)と明子(永谷咲笑)と共同生活を送ることで、生きていく気持ちが芽生えます。
翌朝、水爆実験により呉爾羅から変異して、巨大化したゴジラが現れて、焼け跡から復興し始めた日本を再び焦土にします。典子はゴジラが吐き出した熱線で起きた爆風から、敷島を庇って吹き飛ばされます。
生き残った敷島はゴジラへの復讐を誓い、海軍の技術士官だった野田を中心に、元軍人たちにより立案された対ゴジラ作戦「海神(わだつみ)作戦」に参加します。
グレーディングとティール&オレンジ(「T&O」)
グレーディングとは撮影した映像やCGの映像を、映画の世界観に合わせた色味や明るさに調整する作業です。グレーディングに興味を持つと出会う用語が、「ティール&オレンジ」(以下「T&O」)です。中間調やハイライトにオレンジ系の色、暗部にブルー系の色を使い、補色効果を利用して映像に立体感を出す手法です。
巨額の予算をかけて大きな収益を上げるブロックバスター映画で使われることが多いルックス(色調)です。このルックスを映画全編を通して徹底的に使った映画が『トランスフォーマー』(マイケル・ベイ/07年)です。この映画以降「T&O」を使う映画が増えています。
『ゴジラ-1.0』(以下『ゴジラ』)では未曾有の危機を生き抜こうとする人間たちのドラマを描きますが、ゴジラが現れると観客の視点は人間ではなくゴジラに向かいがちになります。
この視点を人間側にも向けさせるため、映像には工夫が必要になります。そのひとつがグレーディングによる映像の色味の調整です。
「T&O」により観客の視点は人間に向かう
『ゴジラ』で「T&O」が効果的に使われるのが、ゴジラと海上で遭遇する海のシークエンス(36分10秒〜)です。ゴジラは色味の少ない暗いグレー系に対して、敷島たちの顔の色味にはオレンジ色を足して、海は実際の色よりも濃いブルー系の色味にしています。
この海のシークエンスではグレーディングによる色味の調整だけでなく、俳優の着る衣装、手に持つマグカップ、錆びついた機雷、木造船の船体など、美術と衣装になるべく多く茶系の色を使うことで、人間とその周りの色味に統一感を作っています。
色味の統一は、濃いブルーを背景にした人間は映像の中で目立ち、観客の視点をゴジラだけでなく人間にも向かわせます。
照明により敷島の生きる気持ちの芽生えを見せる
敷島が典子と明子と共に暮らすバラックに帰ってきて、機雷を掃海する仕事を見つけたことを典子に伝えるシーン(19分57秒〜)では、敷島の命の心配をする典子に対して、敷島は3人が生きるために必要な仕事だと説得をします。
このシーンの照明は、敷島の顔には斜め正面から当てる光で明るくして、典子の顔は斜め後ろから当てている光で暗くしています。ふたりの顔の明暗からも、敷島に生きる気持ちが芽生えてきたことと、典子が敷島のことを心配している心情が描かれます。
このシーンの最後のショット(21分36秒〜)は、敷島と典子を窓向けの横位置から映すツーショットから、敷島へ向かってカメラが近づき、敷島を斜め正面から映すアップになります。
このショットの照明は、カメラが動くことで光の当たり方が途中から変わります。横位置のツーショットでは窓からの外光が逆光で当たることで、ふたりの横顔を暗く見せています。カメラが動いて、敷島を斜め正面から映すアップになると、敷島への照明は斜め正面から当たる光に変わります。
ひとつのショットの中で、敷島の顔を映すサイズが大きくなり、顔が明るくなることで、敷島が典子と明子のために生きようと決意した顔を印象的に見せます。
このショットでは、背景の白い障子を敷島の前に配置することでも、敷島の顔を明るく見せています。
室内でのカメラの動きのコントロール
『ゴジラ』では敷島たちが暮らすバラック(のちに家)の室内のシーンは、カメラは基本的には三脚に据えて動かさず、左右に振るパンか、上下に振るティルトで敷島たちの動きをフォローしています。カメラを移動車(ドリー)に載せて動かすのは、カメラが動いているのを意識させないようにしながら、映すサイズの大きさを調整する最小限の動きにとどめています。
カメラが動いているのを意識されるショットは、劇中で転換点となる効果的なタイミングで使われて、観客の登場人物たちへの感情移入を強めています。
室内でカメラが動いているのが意識されるシーンは、敷島が典子へ機雷を掃海する仕事をすることを伝えるシーン以外に5つあります。以下4つのシーンを箇条書きに挙げます。
明子がお絵描きするのを典子が見ているシーン(28分〜)、敷島が典子に自分は生きていてはいけない人間だと告げたあと、典子が必死に敷島を鼓舞するシーン(45分50秒〜)での、座っている敷島と典子を後ろ姿をツーショットで映すショット、ふたりを正面から映すふたつのショット。敷島が明子と遊んでいるシーン(53分48秒〜)で、ゴジラ来襲を告げるラジオへカメラが近づいていくふたつのショット。典子の葬式のシーンで、野田が敷島の横へ座り、対ゴジラ作戦が秘密裏に進んでいることを教えるショット(64分51秒〜)になります。
敷島のカメラ目線に入るカメラの動き
最後に室内でカメラが動くのは、敷島が「海神作戦」で使う戦闘機の整備と改修を、橘に頼むシーン(80分44秒〜)になります。大戸島の惨劇を起こした敷島を許せない橘は、敷島の頼みを断りますが、敷島は必死で説得を続けます。
このときカメラは、手足を縛られて土間に横たわる敷島と戸口の外に立つ橘を、交互にカットバックで映します。敷島向けのショット(82分23秒〜)では、カメラは高さを少しずつ上げて、橘を見上げている敷島の顔を正面から映す位置へと動いてきます。
敷島がゴジラへ特攻する考えを橘に打ち明けたあと、このシーンの最後になる敷島向けのショット(82分58秒〜)では、カメラは敷島に向かって近づき、敷島の目線の軸線上(カメラ目線)に入る位置へ動きます。
カメラは敷島の狂気に満ちた目をカメラ目線で映すことで、観客は敷島が自分に語りかけているように感じて、彼の狂気を共有することになります。
このシーンでは、敷島のカメラ目線になる位置へ、カメラを少しずつ動かすことで、敷島の狂気を宿した視線を観客は受け止めることができています。もしいきなり、敷島のカメラ目線になる位置へカメラを動かしていたら、観客は敷島の眼差しの強さに驚いて、映画への没入感が妨げられることになります。
このシーンでは敷島の上にある照明が、敷島の白目に当たることで視線の印象がさらに強められています。
「映画のタネとシカケ 現代日本映画編」~なぜ好きな映画は何度も観たくなるのか?(著・御木茂則)全国書店、ネット書店で好評発売中
ビデオサロンの好評連載「映画の裏窓」をベースに図版を作成して、大幅に改稿した書籍「映画のタネとシカケ」。前著から約2年。今度は世界から評価されている、2000年以降の日本映画を取り上げた「映画のタネとシカケ 現代日本映画編」が好評発売中。(『ゴジラ-1.0』は含まれていません)