プロデューサーと脚本家が設立した制作プロダクションという個性を活かしながら、多数の映画制作を手がけてきたコギトワークス。最近は「日本映画を世界のミニシアターへ」というプロジェクトを開始し、2024年に“作り手ファースト”の制作体制を目指した映画レーベル「New Counter Films」も立ち上げた仕掛け人の関 友彦さん、鈴木徳至さんに「企画開発」「制作」「仕上げ」「宣伝」「配給」を分業しない独自の映画づくりを語ってもらった。
※この記事は有料会員限定のコンテンツです。続きを読む場合はVIDEO SALONプレミアムコンテンツへの会員登録が必要になります。この記事の最下部にあるボタン「続きを読む」をクリックして会員登録をお願いいたします。1記事・250円。またはサブスクプランならば月額1,000円(2024年1月号より月に4-5本を配信)にて全記事を閲覧できます(既にウェビナープランや電子版プラン、ウェビナー+電子版プランにご加入の方は新規の登録は不要です)。

代表取締役/プロデューサー 関友彦 Tomohiko Seki
2000年に英国留学から帰国後、フリーランスの制作として多くの国内映画や合作映画の現場を経験し、2008年に株式会社コギトワークスを設立。2021年からは協同組合日本映画製作者協会(日映協)の理事に就任。また、2024年には【New Counter Films】という新たな映画レーベルを鈴木徳至と共に立ち上げる。プロデューサーを務めた近作に、石川 慶監督『Ten Years JAPAN 美しい国』、荒木伸二監督『人数の町』など。入江 悠監督作『あんのこと』が現在公開中、石井岳龍監督作『箱男』(8月23日公開)が待機中。
X(Twitter)● https://x.com/tomohikoseki

プロデューサー 鈴木徳至 Tokushi Suzuki
早稲田大学卒業後、株式会社ディレクションズにて主にNHKの番組制作を担当。2011年に独立後、初プロデュース作『隕石とインポテンツ』がカンヌ国際映画祭・短編コンペティション部門に出品される。『枝葉のこと』、『王国(あるいはその家について)』など、国内外の映画祭や批評家から高い評価を受ける作品を手掛けている。2019年にコギトワークスに入社。近年は『街の上で』、『うみべの女の子』、『ムーンライト・シャドウ』、『逃げきれた夢』など精力的に作品を発表。待機作に『ナミビアの砂漠』(9月6日公開)がある。
X(Twitter)● https://x.com/toxi13
テーマは“自分たちが作りたいと思えるものを作る”
会社が迷子にならないように羅針盤を持つ
関 僕は1996年から2000年までイギリスに留学していたんですけど、日本に帰ってきてから飲み仲間でもある専門学校の先輩から映画制作に誘われたんです。業界のことは何も知りませんでしたが、「来月空いてるか?」と言われて初めて参加したのが行定 勲監督の短編の現場でした。そこからまた「来月空いてるか?」と言われて次の現場に参加する…これを繰り返していまに至る、という感じです(笑)。当時、バイリンガルのスタッフはあまり多くなかったこともあって、『キル・ビル』『ロスト・イン・トランスレーション』といった海外作品の現場にも参加できました。最初はフリーランスの制作として活動していましたが、それに限界を感じて、2008年に脚本家のいながききよたかと一緒に立ち上げたのがコギトワークスです。「プロデューサーと脚本家が設立した制作プロダクション」というのがコギトワークスの特徴のひとつだと思います。
鈴 僕は大学時代に映画の現場が見てみたいと思って、石井克人監督がワークショップのスタッフを募集していたので、いったんボランティアとして潜り込むことにしたんです。そこからいつのまにかカチンコを打ったり、周りの人たちと映画づくりに没頭していました(笑)。大学卒業後はTVの制作会社で働いたんですけど、東日本大震災が発生したこともあって、いつまで生きられるか分からないなら映画がやりたいな、と。会社を辞めてから脚本を学んだりもしましたが、やはり企画を立てるところから携わりたくなって、一番最初に作ったのが『隕石とインポテンツ』(佐々木 想監督作)でした。カンヌの短編コンペに選ばれたことでネットワークも徐々に広がり、そこからずっと映画を作り続けることができています。2019年にコギトワークスに入社したことも含めて、本当に人との出会いに恵まれてここまできました。
関 コギトワークスは「自分たちが作りたいと思えるものを作る」というのが大前提にあります。すごく幼い発想に見えるかもしれませんが、いまもこの理念は変わっていません。ただ、呑気ではいられないところもあって、特にコロナ禍を経て加速度的に時代が変わっていると実感しています。でも、時代に合わせて理念を変えてしまうと、風を読むことばかりに気を取られてしまって、逆に地図をなくして迷子になってしまう。どんどん時代が変わるからこそ、会社としての羅針盤はしっかりもっておく必要性を感じています。つまり「自分たちが作りたいと思えるものを作る」という羅針盤を持ちつつ、時代の変化に合わせてブラッシュアップしていくことが大切なんです。
二極化の加速と企業理念のせめぎ合い
コギトワークスのムービングロゴに込めた想い
コギトワークスの作品冒頭に挿入されているムービングロゴ。CGで作るのが一般的だが、実際に立体造形したロゴを照明の当て方の変化で浮かび上がらせている。このロゴひとつにも常識を疑いながらクリエイティブファーストを目指すコギトワークスの理念が込められている。

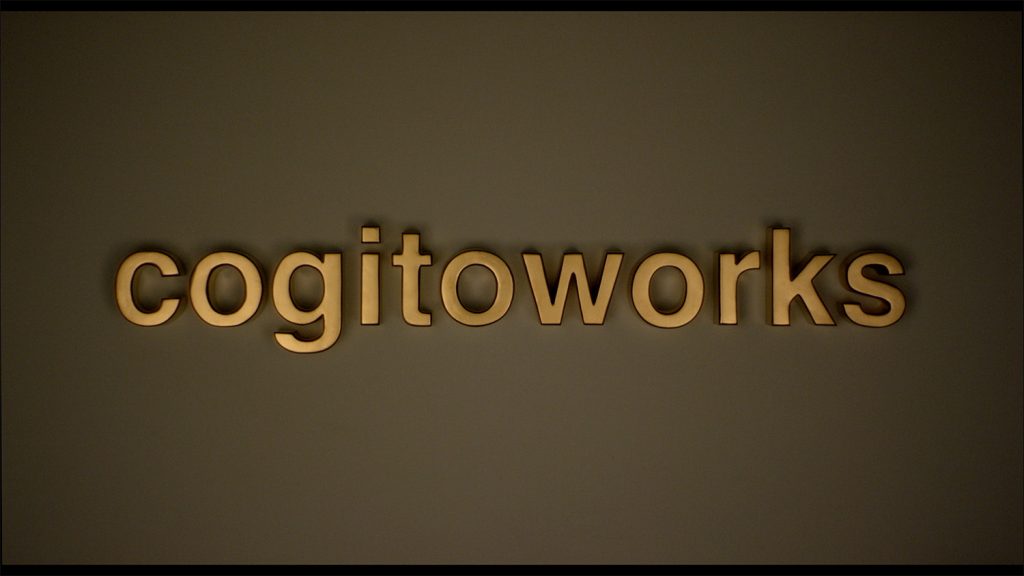
“いろんな見方ができる作品”はどんどん作りづらくなっている
関 コギトワークスという会社名の“コギト”の語源は“Consider”で考える・熟考するという意味です。“ワークス”は動かすという意味なので、そのふたつをくっつけるとクリエイティブになるという想いが込められています。あと、熟考というのは“疑う”ことでもあって、いまやっていることが本当に合っているのか、制作会社とはこういうものだと言われているけどそれは本質なのか…そんな問いも常に持っているということですね。
ここ数年、映画・映像業界に環境の変化が波及しています。大きなところでいうと「二極化」の加速。ブロックバスター映画とミニシアター映画など、製作費や産業の形態としての二極化はどんどん進んでいます。それに付随して“良い意味”と“悪い意味”で作品の多様性が生まれました。いろんな作品があるということ自体は歓迎されるべき良いことだと思います。ただ、昔よりも“売れること”が求められているので、売れていない作品=悪のような流れのなかでは、本来の多様性とは違う気がしていて…。
鈴 インディペンデント作品も“商品”として測られてしまうんです。ここ数年はどこまでいっても売上という数字でしか判断されない。当たらない作品も含めて映画業界だったはずが、その余裕がなくなってきているな、と。
関 映画というエンターテインメントの業界なので、観客や視聴者のみなさんから楽しそうだと思ってもらいたいんですが、産業の話をするとみんな表情が暗くなるんですよね…(笑)。あと、お客さんに届ける場所=劇場という意味でも多様性が失われています。シネコンに行くことは決して悪いことではないんですが、かたや文化として大切だった小さな作品を見る機会が減りました。これはコロナ禍でさらに顕著になったと思います。
鈴 “ミニシアターブーム”と呼ばれていた頃とはお客さんのあり方にも変化がありました。『ダンサー・イン・ザ・ダーク』や『アメリ』は興収が億を超える大ヒットをしていましたが、いまはどうなんだろう…。
関 それぞれの作品ごとに失敗できないという“責任感”が重くなっている気がします。加えて、少し尖った作品をつくると腫れ物に触られるような扱いを受けることが増えましたね。いろんな見方ができる作品がたくさんあるから文化として豊かだったはずなのに、漂白されたものしかなくなってしまうと、僕たちが思っている“映画”とは違う形のものになってしまいます。
鈴 極端な話、殺人鬼を描く映画を見て「人を殺すことは良くない」と感じることもあるわけじゃないですか。それを一方的に「この映画は殺人を助長している!」と言われる、みたいな拒絶反応は多くなりましたね。
関 もちろんコンプライアンスに無知であってはいけないし、われわれ作り手も自覚しないといけないと思います。ただ、映画はチケットを買ってみていただくわけです。わざわざ情報を取りに行く場所だからこそ、いろんな角度のものがあるほうが文化として豊かなはず…。それが漂白されていくことに違和感を覚えながらも、時代の変化は止められません。「昔は良かった」と言うつもりはありませんが、そんないまだからこそ映画としてやるべきものを模索して取り組むしかないですね。
鈴 数字を絶対的な評価軸として考えると、ひと言でみんな同じ感想が言える作品が増えるんです。たとえば「泣ける映画」みたいなひとつの感想がたくさん出る作品のほうが広がりやすくて、勢いがあるように見える。逆に多様な感想が出る作品は盛り上がってないように見えてしまします。だから売る側の論理として分かりやすい作品が増えていくのは避けられない。それが“良い作品”なのか、ということは二の次になっているのかもしれません。
“社会の急速な変化”を加味した取り組み
映画・映像業界に波及している環境の変化を理解する
それぞれの作品にあったルールが必要
関 国内の映画市場自体は落ち込んでいないんです。それはアニメーション映画がヒットしていること、ブロックバスター的な映画に昔よりも人が入っていることが要因ですね。ここにも二極化があって、大ヒットした一部の映画によって市場が横ばいに保たれているように見える、と。毎年日本映画は600本ぐらい公開されているなか、右肩上がりなのは上位数%で、残りのアベレージはずっと下がっていることに目を向けないといけません。
鈴 ここから派生する問題として助成金のあり方が挙げられます。助成を求めて申請を出しても、可否を判断をする人は「産業としては右肩上がりなのになぜ助成金が必要なのか?」となってしまう。多様性のある作品と商品として作られる作品をどう分けて説明をするのか、本当に足りていないところにどう助成をしてもらうか、それを作家たちがいま必死に考えていますね。
関 僕は日映協(日本映画製作者協会)の理事をしていて、映適(日本映画制作適正化機構)とも話をしているんですが、邦画メジャーの映連(日本映画製作者連盟)各社の作品は毎年140本ぐらい、これすべて映適認定作品にしたとしても残りの400〜500本は取り残されてしまいます。
鈴 つまりスタッフの職場環境もメジャーとインディーズで二極化している、と。メジャー映画のルールができても、スタッフはドラマ作品も含めていろんな現場に参加します。いまはプラットホームも乱立している状態で、すべての現場に対応したルールを作ることは不可能なんです。
関 日映協ではバジェット1億円以下には映適ルールを活用するのはやめよう、という議論をしてきました。新人監督の作品やドキュメンタリー作品に撮影時間の上限13時間というルールを当てはめてしまうと本来作りたいものを作れなくなりますし、余計な予算や日数がかかってしまって、完成までの道のりが遠くなってしまうからです。もちろん商業作品においては、やる気の搾取で何時間も過酷労働をさせるのはダメですが、グラデーションのあるそれぞれの作品に合ったルールが必要であると思います。
鈴 自主映画でも撮影時間をもっと短くしている作品もあって、思考する時間や寝る時間も含めていい作品ができるという考え方も広がってきた気がします。だから作品規模が小さい=過酷というわけではないですね。
自社製作・自社配給への一歩
もともとは守屋文雄監督が進めていた自主企画だったが、制作プロダクションとしてだけではない映画づくりを模索していた関さんが出資を申し出てコギトワークスの製作・配給第1弾作品となった。木陰でハンモックに揺られている主人公をただ見つめる…というある意味でラディカルな作品だったが、一部でカルト的な支持を得た。上映開始直後、コロナ禍の緊急事態宣言によって中断を余儀なくされたが、最終的には全国20ほどの劇場で上映されることに。
—映画 『すずしい木陰』—

虫の鳴き声がする夏のたそがれ時、木の間に吊るされたハンモックに女の子が寝ている。起きるでも寝るでもなく、そこに寝転がっている。この映画で物語らしいことは何も起きない。にもかかわらず、たしかにそこで何かが起きている——。「見つめる」という行為の向こうに、立ち現れてくる何か。『まんが島』などの監督作だけでなく、脚本家、俳優としても活躍する守屋文雄による異色作。2020年に新宿K’s cinemaほかで公開された。
〈スタッフ・キャスト〉
監督・脚本・編集:守屋文雄 プロデューサー:関 友彦 撮影:高木風太 音響:弥栄裕樹 現場応援:柴田 剛 出演:柳 英里紗
製作・配給:コギトワークス
入江 悠監督10年ぶりの自主作品をプロデュース

画像はMotion Galleryのクラウドファンディングページ。入江監督が“3つの夢”として①コロナ禍で苦境にある全国のミニシアターで本作を公開すること、②コロナ禍で仕事を失ったスタッフ・俳優と、商業映画では製作できない映画を作ること、③未来を担う若い学生たちと新たな日本映画を完成させることを掲げ、自身による出費とクラウドファンディングのみで、制作費をまかなうことを宣言した。全キャストをオーディションで選考した際には応募が2,500名を超えたほか、クラウドファンディングでのサポーター募集が開始されるとすぐに話題となり、目標金額の10,000,000円を達成。最終的にコレクター1011人から11,923,001円が集まった。
劇場の支配人と仲良くなることの重要性
関 コギトワークスはいわゆる制作プロダクションの業務だけをやっていました。すでに企画があって、監督やメインのスタッフ・キャストも決まっていたりする状態で、プロダクション業務を受託して現場を遂行する…というのが主な仕事だったんです。ただ、先ほどお話ししたような変化を目の当たりにするなかで、鈴木が参画した2019年あたりから自社で製作・配給してみよう、と。当時、鈴木は『枝葉のこと』(二ノ宮隆太郎監督作)を上映していたんですが、スカウトしようと思って何度も声をかけていたんです(笑)。なぜスカウトしたのかというと、自主映画だからこそ監督と二人三脚で映画を作って、劇場に届けるところまで自分たちでやっていたから。映画って本来こうあるべきだよな、と考えるところもあって、『すずしい木陰』という作品で初めて自社製作・配給をしてみることにしました。
鈴 最初の製作・配給作品としてはかなり攻めた内容の映画だったと思います(笑)。
自社で配給することへの想いを再確認
入江監督からの直接の依頼でコギトワークスが配給を担当することになった『シュシュシュの娘』。最終的に全国43館の劇場で上映されるなどコロナ禍のミニシアターに活気を与えることに成功したが、関さんは「作るところから届けるところまでずっと感謝しっぱなしでした」と振り返り、自分たちで作品を届けることの大切さを改めて学んだという。
—映画 『シュシュシュの娘』—

移民排斥、改ざん、不寛容…など、不穏な空気が漂う街で暮らす鴉丸未宇。自死した先輩の仇をとるため、そして暗雲立ちこめる市政に一矢報いるために、未宇はひそかに立ち上がる——。コロナ禍で打撃を受けた全国のミニシアターや撮影現場を失ったスタッフ、俳優を苦慮し、入江 悠監督が『SR サイタマノラッパー』シリーズ以来の自主映画として手がけた。
〈スタッフ・キャスト〉
製作・脚本・監督・編集:入江 悠 プロデューサー:関 友彦 撮影:石垣 求 照明:高井大樹 録音・整音:古谷正志 音楽:海田庄吾 出演:福田沙紀、吉岡睦雄、根矢涼香、宇野祥平、金谷真由美、松澤仁晶、三溝浩二、仗 桐安、安田ユウ、山中アラタ、児玉拓郎、白畑真逸、橋野純平、井浦 新 ほか
制作・配給:コギトワークス
