2025年2月27日(木)から3月2日(日)までの4日間、パシフィコ横浜で開催された「CP+ 2025」。本記事では、そこで行われた玄光社のVIDEO SALONとCommercial Photoがプロデュースしたイベント企画「CREATORS EDGE Spring Edition」の長山一樹さんによるセミナーの模様をお届けする。3月1日(土)17:20-18:00にステージCで行われたこのセッションでは、長山さんが仕事で撮影した写真を通して、撮影時に意識するポイント、ライティング、モデルとのコミュニケーションの取り方などをあらゆる角度から解説していただいた。
レポート●武石 修
戦わずして勝つにはカメラも重要
僕は広告やファッションポートレート、コマーシャルの仕事をメインにしているフォトグラファーの長山一樹と申します。
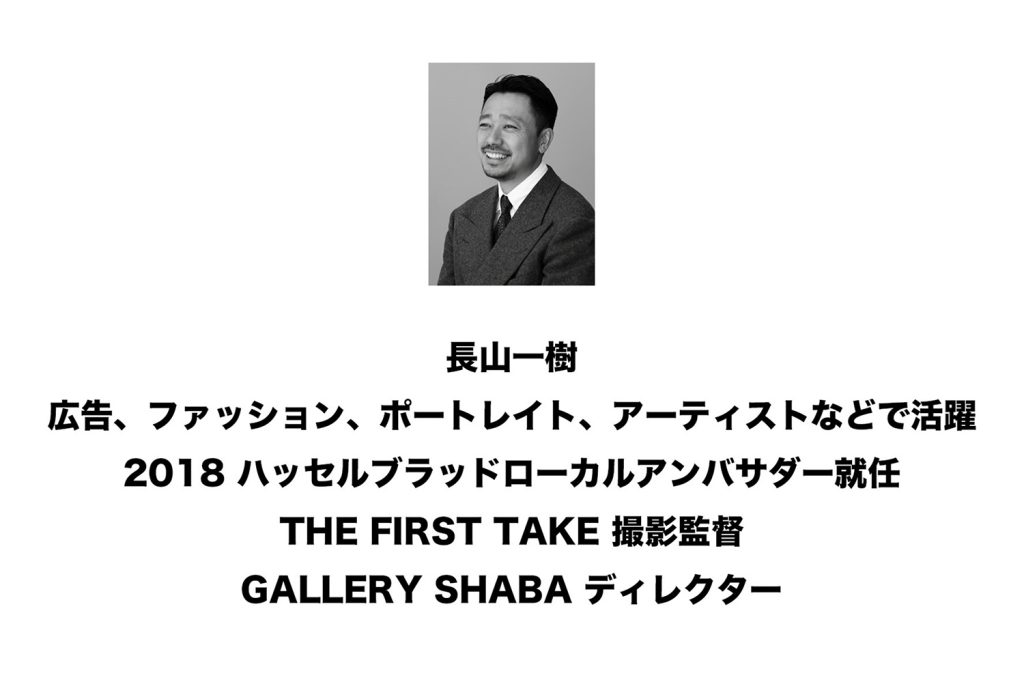
ご存知の方も多いかと思いますが、THE FIRST TAKEというYouTubeチャンネルの撮影監督を最初からしていて、今もずっと撮影してます。コマーシャル・フォトの表紙も過去に3回ほど撮らせて頂いて、僕の中でお気に入りの仕事の一つなので紹介させて頂きました。

タイトルに戦略と書いてありますが、「戦いを略す」ということで、戦わずに差別化を生むお話をしたいと思います。今はSNSの誕生もあって写真をやっている人が多く、その数と戦おうと思ったら正直僕でも戦える気がしません。ですので、そこと戦わずに差別化を図ろうということです。
今のポートレート写真はほとんどの人がミラーレスカメラを使って撮ってると思いますが、僕がプロとして独立した時は中判とか大判のフィルムカメラでスタートしていて、それ主流でもありました。
そこからカメラも進化して、ミラーレスになってスマホのようなものまで出てきた。ミラーレスカメラのメリットは軽くて機動力があるし、何枚でも撮れます。動画も撮れるし、レンズの選択肢も多い。他にもありますがメリットだらけだと思います。
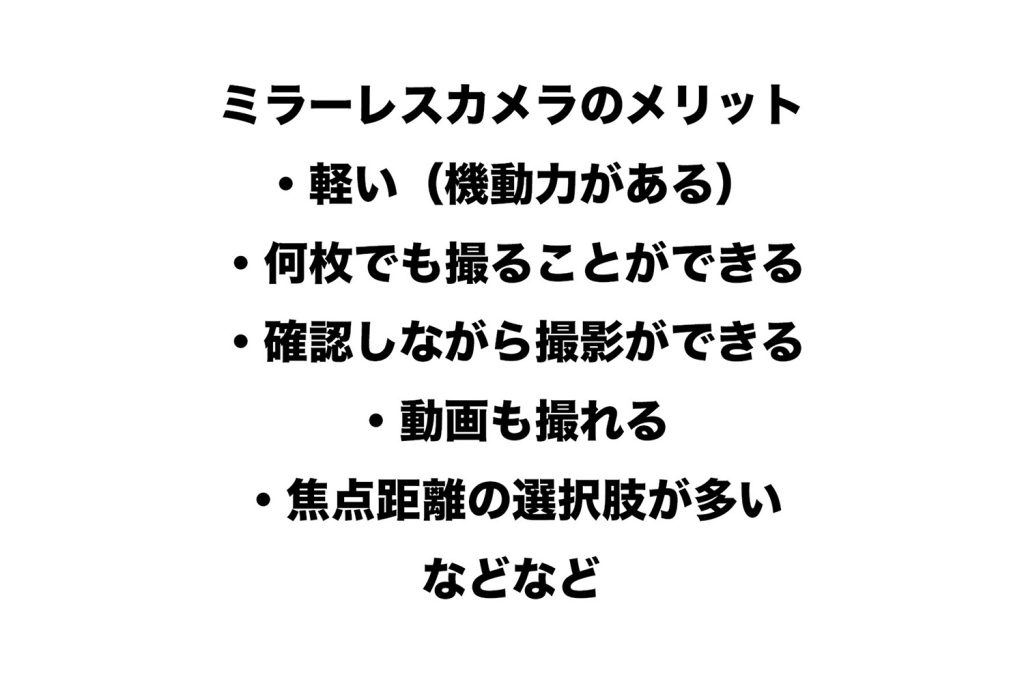
逆に中判や大判カメラのデメリットを挙げると、やっぱり重いし持ち運びがそもそも大変です。連写で撮れないこともありますし、もちろんフィルムなのですぐ確認できないわけです。値段も高く手を出しづらいということもあったでしょう。
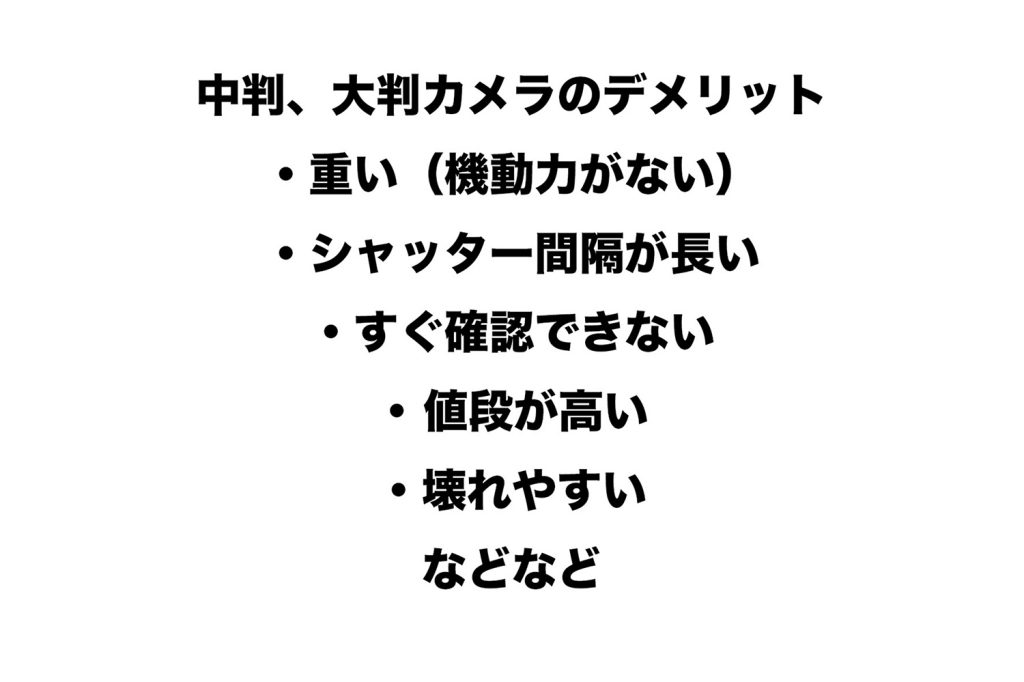
中判カメラのデメリットを述べましたが、このデメリットの中にポートレート写真を差別化するためのポイントがあると思っています。デメリットがある場所では、大多数の人とは違うことができるのです。
シャッターを押さずに待つ「間」の力
ここ数年、すごく「上手な写真」が毎日のようにスマホに出てくるようになりました。プロなのかそうで無いのか判断しづらいぐらいで、色味もトーンも上手です。そこにはプロかそうでないかの境界線は無いのかなと思うくらいです。しかし僕は「強い写真」を見なくなったと思っています。
自分はその強い写真を意識してポートレートを撮ってきたので、その考え方やスキル、ちょっとしたさじ加減で強く見える写真のコツを話したいと思います。カメラは便利になりましたが、「過去に比べて失われたもの」にヒントがあります。
3つあって1つは「間」です。フィルム時代はフィルムチェンジをすると一呼吸空くわけです。そこで次は「こう撮ってみようか」という間が生まれたりします。今はそういうものがどんどん無くなって、時間が短縮されています。
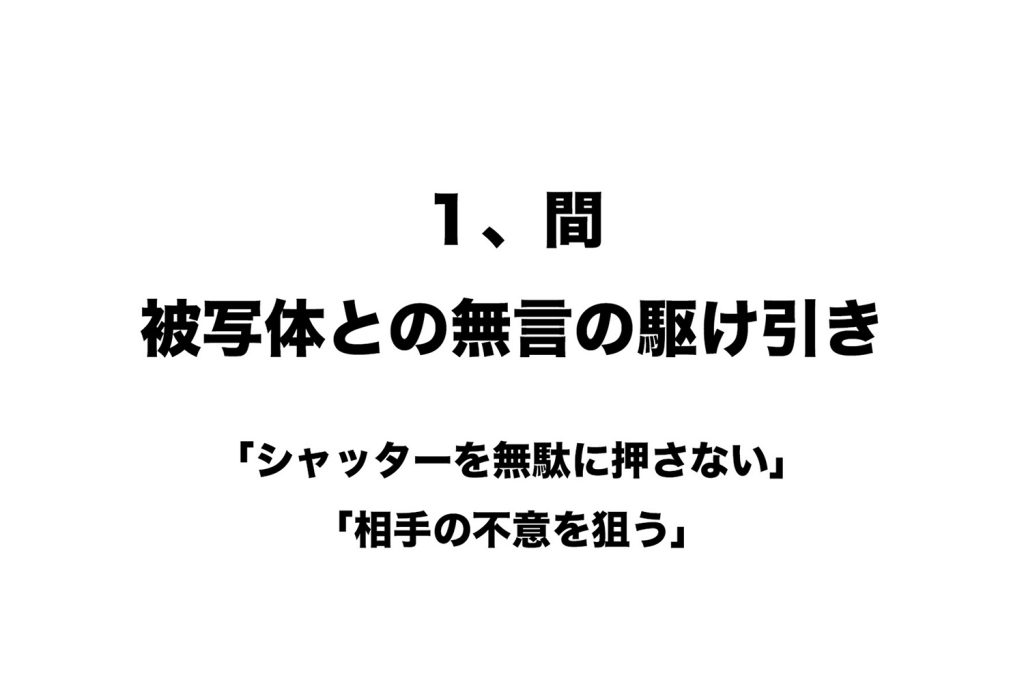
被写体とは「無言の駆け引き」が必要だと思っていて、自分が良いと思った瞬間以外はできるだけシャッターを押さないことを意識しています。どんどんシャッターを押してしまうと相手もどんどん動いてしまう。だから、相手の不意を狙うためにじっと待つんですね。
その時に被写体も「いつ撮るんだ?」とこちらを伺うわけです。そして一瞬力を抜いたときだったり、一瞬ポケットに手を入れるために動いた瞬間だったり、固まった空気から違う動作に移る瞬間が必ずあって、そういう瞬間を撮るようにしています。
すると被写体は「今撮るのか!」「この人は隙があるところを撮りに来るんだ」という無言の会話が生まれる。これが今どんどん無くなっているんです。ポートレートを撮るときには、冷静になって一度被写体と無言の会話をやってみる。これは今の時代には無いことで、被写体も新鮮に感じると思います。
表情が変わる魔法の言葉
2つ目として今の現場だと自ずと「緊張感」が無いことが多いんですね。「強い写真」には緊張感が必要だと僕は思っていますので、緊張感をどう作るかを紹介します。
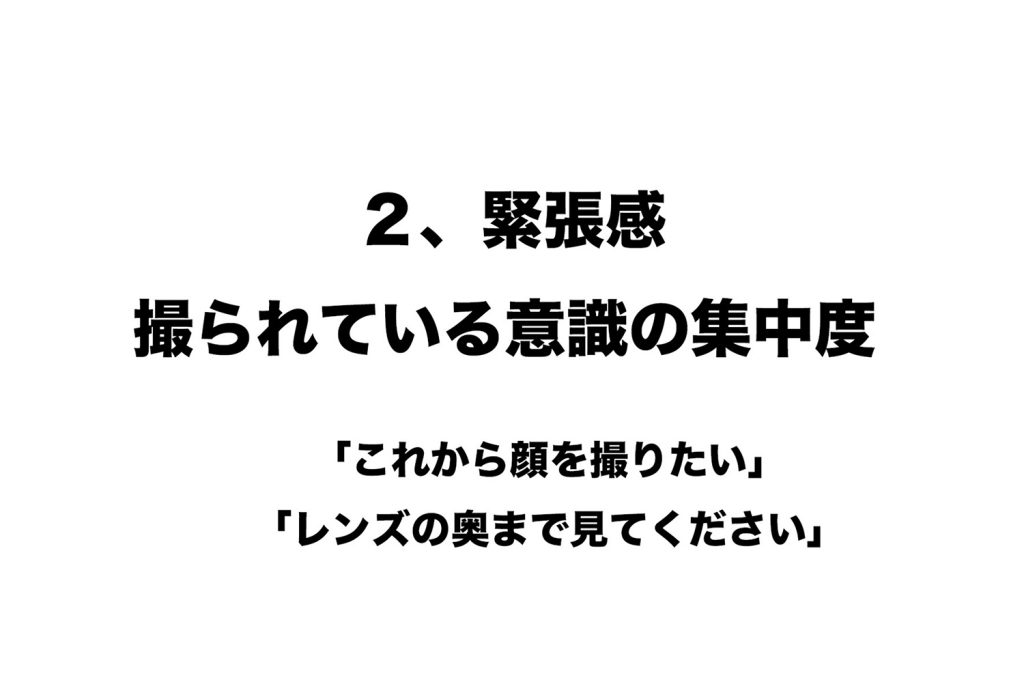
被写体をできるだけ緊張させないで和んだ風に撮りたいと思う人もいると思いますが、強い写真を撮る上では撮られている人がカメラの前で緊張している状態を生みたいと考えています。
そこで、ポートレートを撮るときに2つの言葉を被写体によく掛けるんですね。1つは「このカットは顔を撮らせてください」。そうすると相手は「勝負のポートレートだ」と感じて被写体の意識がガラッと変わり、顔の集中度がすごく増します。
そして目線をもらうわけですが、「カメラを見てください」ではなく「レンズの奥を見てください」と声を掛けるんです。そうすると目の強さが全然違ってきます。
強いポートレートを撮りたいという時にはこの2つの言葉を掛けると思った以上に表情が変わるので試してみてほしいと思います。
カメラマンも存在感を出す
3つ目の存在感というのは被写体ではなく、自分自身の存在感です。
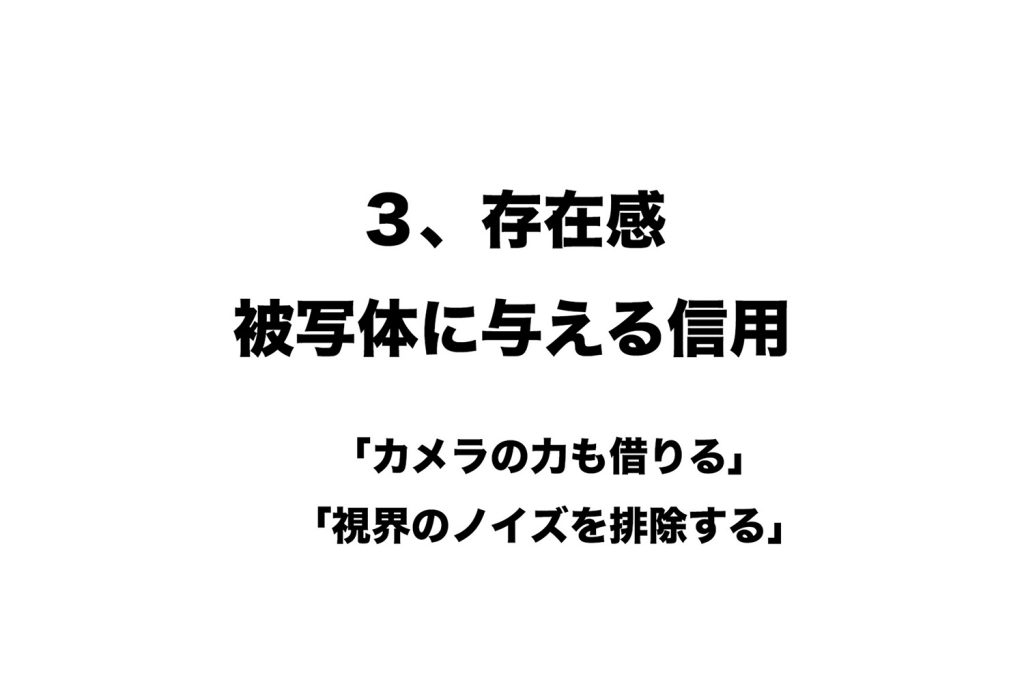
今はフレンドリーでライトな現場が主流になっています。どういうカメラを使っているか? どういう佇まいで現場にいるか? というのを下積み時代に見て憧れたり、被写体と対等に渡り合っているプロの姿を見てきました。ですから、この存在感という要素からも今は遠ざかっているのかなと思います。
存在感は被写体に与える心理ですね。僕の経験ですが、ミラーレスカメラ、音のしない小さなカメラで撮られることに被写体もみんな慣れていて何の新鮮味も無いんですね。だから誰に撮られても同じ顔になってしまう。
そこでカメラの力を借りるわけです。カメラに詳しい被写体の方は結構多くて、例えばハッセルブラッドというだけで、「今日はハッセルなんですね」とか「中判なんですね」となる。そこにカメラマンの箔みたいなものが付く。「今日はちょと違うな」という意識が被写体の中に生まれると撮る側の存在感が出ます。
独立して間もないときに、来日したファッションデザイナーを撮る仕事がありました。いくつもの媒体が集まっていてほとんどの人は35mmの一眼レフとストロボ1個で撮っていましたが、僕は4×5のカメラを担いで行ったんです。モノクロで撮ったのですが、被写体がその雑誌の編集者に「この撮影が一番良かったよ」と言ってくれて、その雑誌から仕事が来るようになりました。
そんな経験がありまして、作り込むというと言い過ぎですが、カメラマンとして現場を支配する意味でこういったものを利用するのは1つのアイデアだと思っています。
それから「視界のノイズを排除する」と書いてありますが、撮影の時は1対1の勝負になるので僕の後ろ側にあるものはできるだけ見せないようにしておきたいんです。
多くのギャラリーやいろいろな機材があったりしますが、そうした目に付くものを極力隠すんですね。被写体の目の前にはカメラしかないという状況をできるだけ作るようにして撮っています。
今はデジタルでみんながモニターを見ながらああでもない、こうでもないと話す現場は免れられないのも正直ありますが、「今日のカメラマンはセットの作り方も違う」と、何かこだわっているのが被写体にわかるようにしています。
不意の一瞬を捉える
以上を踏まえて、僕の撮ったポートレートを見ながら話していきたいと思います。
1枚目は木村拓哉さんで、Penという雑誌で撮ったポートレートです。本人にも気に入って頂いて、今この写真はオフィシャルのアーティスト写真にも使ってもらっています。
※肖像権の関係で写真は掲載しておりません
やはりこのときも「レンズの奥をじっと眺めてください」と言いました。そして間ですね。できるだけ無駄なシャッターを押さなかった。会話が無くても木村さんはそのムードを一瞬で汲み取って、こっちもその気だよというムードが出て撮れた一枚です。
木村拓哉さんが手をスッとコートの隙間に入れた一瞬があったんです。その指示をしたわけではないのですが、無言の沈黙の中に動く瞬間があってその時にシャッターを押しました。
顔の強さと、敢えてこの手が入ったところのバランスがポートレートとしてすごく好きで、今日見て頂きたいと思って紹介しました。
次はファッション雑誌で撮影した一枚です。雨をテーマにした撮影内容だったのですが、実は晴れた日に雨を人工的に用意して撮影したものです。
※肖像権の関係で写真は掲載しておりません
日差しが当たらない日陰で、上から雨を降らせてじっと待つわけです。一番良い表情が出るように「レンズの奥を見て」とこのときも言っていました。そして、たまたま良い風が吹いたその時に撮ったのがこの写真です。
シャッタースピードがそんなに速くないので、よく見ると風に吹かれた髪がブレているんですね。一瞬の目の強さと良い具合にブレた髪という、その1枚しか撮れないだろうという瞬間を撮れた写真でした。
木村拓哉さんだから強いというのもありましたが、こちらの意識を被写体に伝えることで、男女関係無くこうした強い表情になることが多いと思います。
すぐ実践できる5つのポイント
ただ、「そう言われましても……」という部分もあると思いますので、皆さんに具体的に使ってもらって仕事で確実に役立つと思うスキルをここで5つ紹介します。
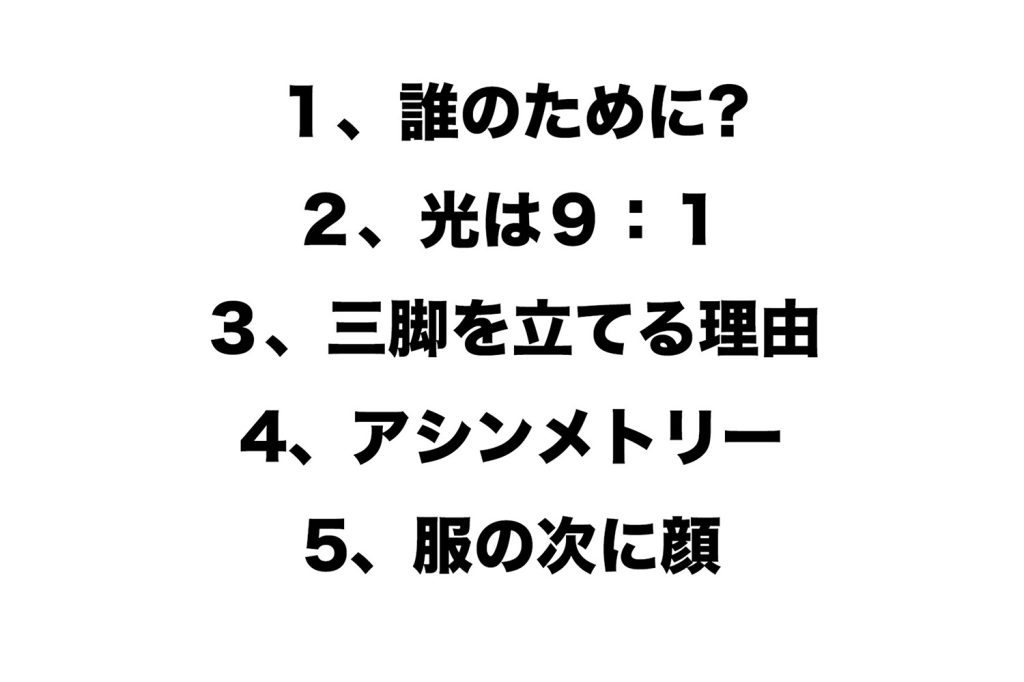
コマーシャルポートレートというだけに仕事なので、自分より大事なのはクライアントです。でもクライアントの向こうにはエンドユーザーがいる。だからエンドユーザーが何を見たいのか? どういうものが新鮮に見えるのかを考えて撮るようにしています。
見えているもの以上に提案しながら撮ると「そこまで考えてくれているか」と、クライアントもすごく信頼してくれます。だから「誰のために」というのを意識すると差別化できるようになるということです。
次に「光は9:1」ですが、僕はポートレートを撮るときに光の部分が9、影の部分がだいたい1という割合で撮ることが多いんですね。仕事でこれをやって「良くないね」と言われることはほとんど無いという僕の黄金比率なんです。
光源によっては光がフラットになりすぎて影がゼロになる場合もありますが、それだと強さが出ないんです。僕は必ず1は影にして締めるようにしています。それには光源と逆側にパネルなど黒いものを置きます。それを被写体のギリギリまで攻めます。
今度チャンスがあったら画角の外ギリギリに黒いものを1枚入れてみてください。それだけで今まで撮ってきた写真とぜんぜん違うものが撮れて写真が変わります。年齢や性別に関係なく良い感じになると思います。
次の「三脚を立てる理由」ですが、三脚は動けないから嫌なんだよねという人もたくさんいると思います。僕がポートレートを撮るときはほぼ三脚を立てていて、それは両手で被写体に指示を出せるからなんです。
手持ち撮影だと「ちょっとだけ顎を上げてください」と言ったときの「ちょっと」の具合がわからないんですね。だからブレ防止というよりも、手を使って微妙な顔の動きをしてもらったり、して欲しいポーズを自分でやって伝えるには手持ちでは難しいと思います。
そして「アシンメトリー」です。シンメトリーでバストアップのポートレートを撮ると証明写真のようになってしまいます。でも強さ的にこの顔で撮りたいとなったときにアシンメトリーにするだけで証明写真感が無くなるというのがコツです。
先ほどの木村拓哉さんの写真も手が入ることによってシンメトリーではなくなったんですね。どこかにアシンメトリーを作るように心がけます。
この写真は菅田将暉さんですが、アシンメトリーを一番象徴している写真だと思って持ってきました。洋服でアシンメトリーを出しています。どこかを崩したいとおもって、スタイリストに相談して服を崩したものです。本人にも気に入って頂けた一枚です。
※肖像権の関係で写真は掲載しておりません
最後は「服の次に顔」ということで、仕事においては被写体よりも主役はその商品だということを頭に入れいておくことが大切です。
ファッションで洋服撮影のときは、まずその服はどこが一番美しく見えるかを考えた上で、そのあとにモデルの顔がどうあるべきか考える。この順序が非常に重要で、逆だとクライアントから色々な注文が発生して痛い目を見るのはカメラマンなんです。
商品という主役がある。それを忘れずにということです。そうした流れがあってこそ、信頼を得た上でポートレートが撮れるわけです。
※肖像権の関係で写真は掲載しておりません
駆け足でしたが、この5つをやるだけで写真がかなり変わると思います。そしてポートレート写真が差別化されます。なぜなら、こういったことをする人がどんどん少なくなっているからです。機会があったら実戦で試してもらいたいと思います。
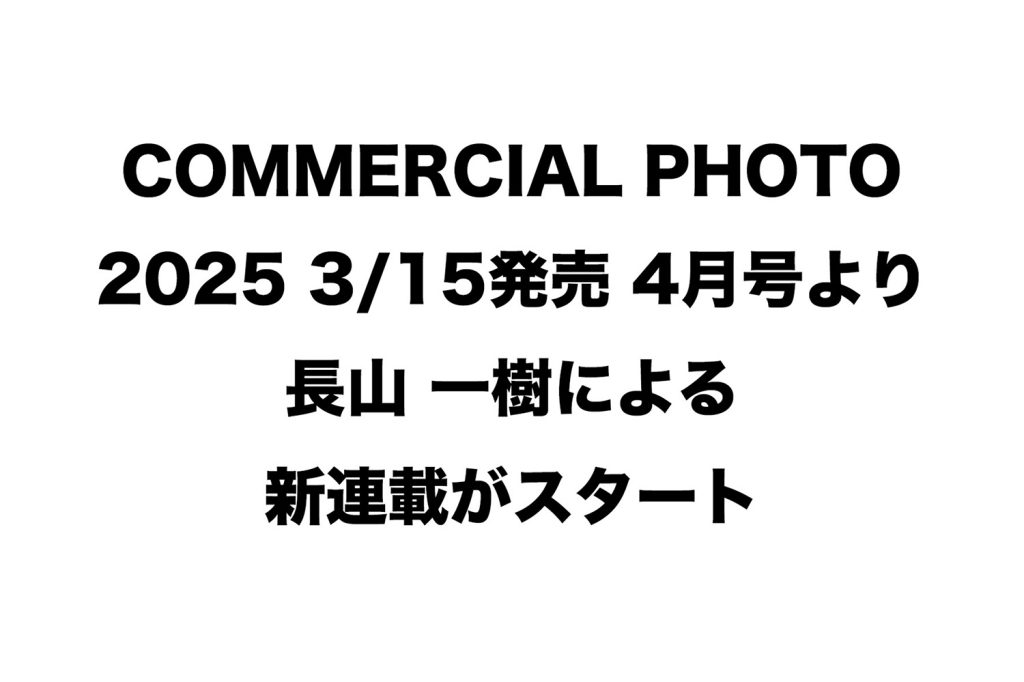
(以上)


