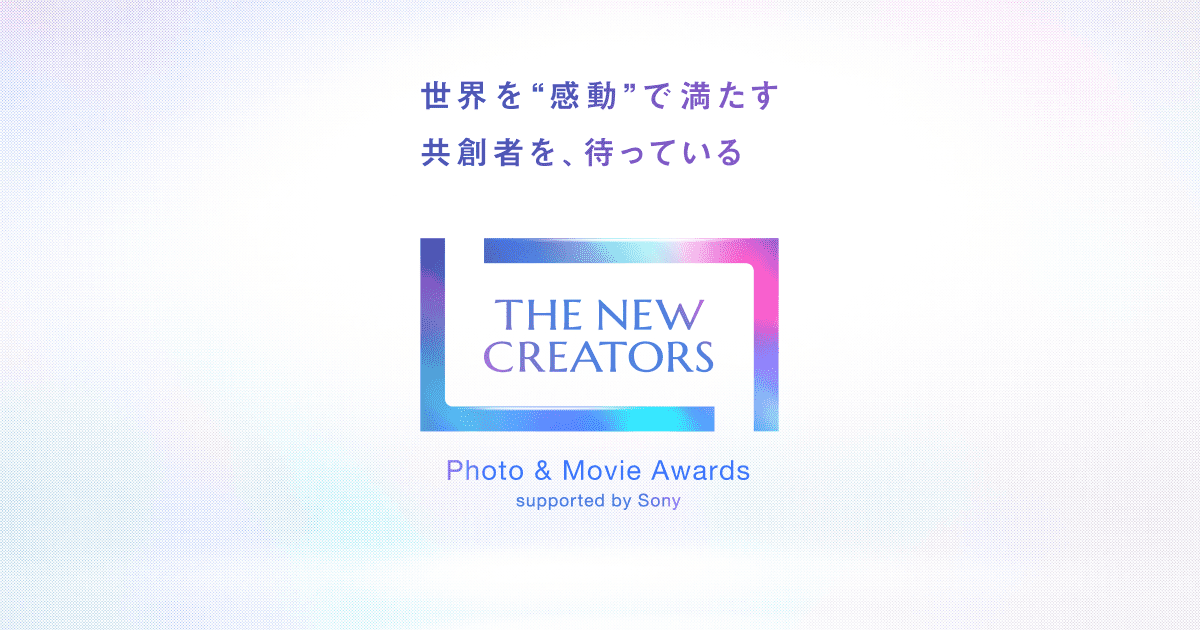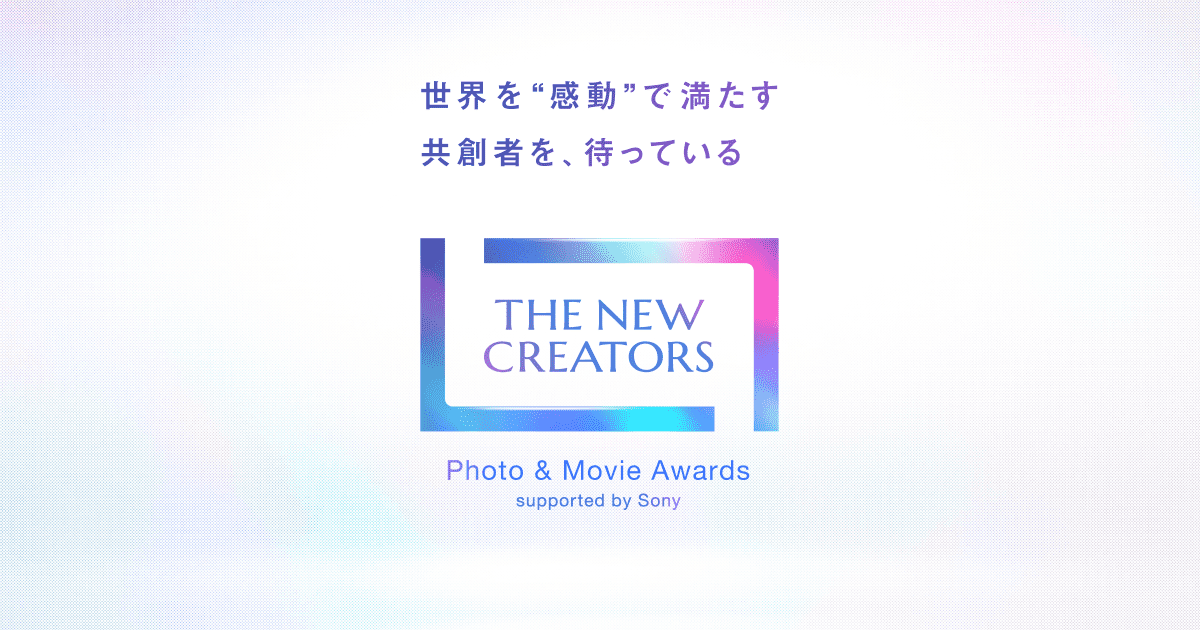さる7月26日(土)、ソニーマーケティング、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、ソニー・ミュージックレーベルズ 、ソニーPCLのソニーグループ4社が共同で新設した写真と映像のアワード「THE NEW CREATORS Photo & Movie Awards」の表彰式が開催された。この記事ではその受賞式の模様とグランプリ受賞者、審査員コメントを中心にレポートする。
このアワードは「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というソニーのPurpose(存在意義)のもと、ソニーのグループ企業4社が新しい才能を見出し、新たな創作活動を支援していくことで、クリエイターと“感動”の未来を共創していくことを目的として設立されたもの。昨年11月より作品募集を開始し、年齢や経験、撮影機材に制限のないオープン形式で、写真作品の3部門、映像作品の3部門の合計6部門を設け、幅広い作品が応募された。
●第1回の受賞全作品はこちらから
映像作品グランプリ
グランプリを受賞した河合ひかるさんは日本と中国にルーツを持ち、文化的に構築された国籍、人種、言語、家族、規範といった人々を属性づけ、カテゴライズする「境界線」、あるいはこれらの枠組みに回収され見過ごされてきたパーソナルで小さな「語り」に関心を持っており、作品の多くは詩的な写実映像を用いて表現されている。

審査員で映画監督の上田慎一郎さんからトロフィーを授与。
河合さんの受賞コメント

この作品は、自分の祖父に向けてありがとうという気持ちを伝えたくて、作ったセルフドキュメンタリーです。自分は母親とふたりで日本で育ってきたんですけれども、母が中国の生まれで、家族が全員中国に住んでおりますので、実質私はずっとひとりで生きてきました。
その中でコロナが流行った時に、毎年母と一緒に中国に帰省して、家族に会いに行ってたんです。私は中国語を全く話せず、しかも勉強してこず、なかなかアイデンティティに向き合えないような10代、20代を過ごしていたんですけれども、祖父がコロナに罹患してしまい、危篤状態になったと母に聞かされた時に、一度も会話をせずに大好きだった祖父と別れてしまうのは絶対に嫌だって思ったんです。
それで急いで古本屋に走り、中国語のテキストをたくさん買って、毎日音読しながら祖父に手紙を書き始めました。中国語を覚えてビデオ電話で自分の想い、感謝の気持ちを伝えたかったんですけれど、手紙を書き上げるより先に、祖父が亡くなってしまいました。その後も中国語の勉強を続けていたのですが、自分にしかない体験があったんです。それは、普通知らない外国語を勉強する時って上手に発音できないし、耳で聞いてもすんなり入ってこないと思うんですけど、単語帳に付いてきたCDを再生したら、その音声が全部聞いたことがある、すごく馴染み深い家族の声で再生されたんです。
綺麗な音声じゃなくて、家族があの時私にこういう言葉をかけてくれてたんだっていう単語を口にするたびに、家族との思い出が蘇ってきたんですね。だけど、私は悲しいくらいに中国語の発音が上手ではなくて、このギャップを何か形にできないかなと思い、この作品の制作に着手しました。そういったものすごくプライベートで自分のために作った作品を、こうして様々な方の目に触れて、評価をいただけたことが、自分のために作った小さな物語が大きな物語へと歩み出している、そういうことなのではないかなと思っております。
ひとえにこのアワードのコンセプトにも書いてある「共創者」というワードが私はすごく好きで応募させていただいたんですけれど、見てくださった方が共感してくれたからこそ、私の作品は強くなれるんだと思っています。そして、いろんな作品を見た時に、共感したり、人の気持ちがわかるよっていう風になったりだとか、あとは想像力を働かせるっていうのは人に備わった能力です。他の生き物にはない能力だと思ってます。
そのような想像力と共感が、きっと平和な世の中を作っていくためのヒントになるんじゃないかなと思っております。生意気なことを色々喋ってしまったんですけれども、そのような表現の力、共感力っていうものを信じて、私はグランプリの名に恥じないようにこれからも制作を続けてまいりますので、どうか皆さん温かく見守ってくださると大変ありがたいです。
●第1回の受賞全作品はこちらから
写真作品グランプリ

写真作品グランプリを受賞した花田智浩さんは福岡県在住のビジュアルアーティスト。2016年にベルリン写真専門学校を卒業し、生活ルーティーンによって引き起こされる思考停止に疑問を投げかけ、日常生活の中で見過ごされている物事に光を当てることを目的として活動している。受賞作は約100年前の大分県別府市の風景と現在の別府市を同じ場所で撮影して写真を重ね合わせたもの。

審査員で写真家の石川直樹さんからトロフィーの授与。
花田さんの受賞コメント

この作品を制作しようと思ったのは2022年に遡ります。大分県別府市のアパートでアーティスト・イン・レジデンスに参加しました。皆さんご存知かもしれませんが、大分県別府市というのは日本一温泉湧出量が多い場所でございまして、地元の人であれば毎日のように温泉に入ることができます。そこで生活していると、温泉は50年前の雨水だということを知りました。つまり、雨水が大地に染み込み、地熱によって温められ、温泉になっていくという過程を知った時に、何か時を感じるような作品制作をしたいと思いました。
しかし、別府の土地でやるということがベタすぎるんじゃないかとか、50年前の雨水を使った作品表現というのはあまりリンクしないんじゃないかとか、色々なことを思ったんですけど、2024年に別府が開湯1300年を迎えました。その時に、100年前の絵葉書を使うことによって、過去と現在の比較ができるんじゃないかと思い作品制作に取り組みました。その時に別府の人からすごく助けていただき、今回使った絵葉書も地元の人から貸していただいたりとか、「温泉染め」の技術を習ったりとか、いろいろな試行錯誤をいたしました。
その中でグランプリをいただいたので、本当に僕ひとりでは作品制作ができなかったと思っております。ひとつだけ訂正したいことがあって、ステートメントの方に温泉数が減少していると書きましたけれども、本当に山ほど温泉がありますので、ぜひこの機会に別府の温泉を訪れていただきたいなと思っております。
最後に、この賞の第1回のグランプリに選んでいただいたことに対して、すごく感謝をしています。そして、選んでいただいたことによって、やっぱり花田を選んでよかったと思っていただけるように、これからも活動していきたいです。
●第1回の受賞全作品はこちらから
審査員コメント

今回、映像部門は「イマジネーション部門」「ショート部門」「自由部門」の3つだったんですけど、ストーリーがあるものもあれば、ドキュメンタリーもあれば、ミュージックビデオみたいなものもあり、それを同じ土俵で審査するというのはすごく難しかったんです。その中で、「俺には作れないな」と感じる作品、自分はそれを基準にして選ばせていただきました。
つまり、その人にしか作れないオリジナリティ、独創性があるかどうかということ。グランプリ・入選と3本ありますが、全部が特定の個人の人にフォーカスを当てて作られた作品で、自分の好きな映画監督にマーティン・スコセッシという映画監督がいるんですけど、その人の言葉で「最も個人的なことが最も独創的である」という言葉があるんですよ。ポン・ジュノ監督がアカデミー賞を受賞した時に引用して話していましたけど、そういう特定の個人にフォーカスを当てて描いているからこそ、誰も真似できない作品になっているなと思います。
テーマは、自分の中のことや自分の身の回りとかだけではなく、ネット上で探してもいいんですよね。個人的に面白いなと思ったものを撮るというだけで、こんなに面白いものができるんだなというのを改めて学ばせていただきました。
僕も映画祭に初めて出たのは26歳くらいだったのですが、審査員の方のコメントに「うるせぇ」って思ってたんです。生意気だったので(笑)。今グランプリとか入選とか佳作に分かれてますけど、正直、何が選ばれるかっていうのは審査員によるので、他のコンテストだったら全然結果が違ってたっていうこともあると思います。僕は若い頃は審査員の言うことを半分受け止めつつ、半分「うるせぇ」って思いながら聞いてたので、半分学びつつ、半分「お前より面白いもの作ってやる」と思いながら頑張ってもらいたいなって思います。

今回はオープン形式ということ、いろんな作品が集まりました。どんな作品をどう比べていいものか、作品に正解はないし、どっちがいい、どっちが悪いというのはなかなか点をつけにくいことだと思うので、僕は単純に何の情報も入れずに作品を見させていただいて、一番グッと心が動いた作品に点数をつけていくという形にしました。
僕は普段音楽系の映像を作っていることが多いので、ミュージックビデオを見たりとか、ライブ映像とか、広告の映像を作ったりするので、音に対してすごく気を使っているような映像を作っているんですけど、グランプリの河合さんの作品は最初の自己紹介の部分で、中国語と映像がまだバラバラの状態で映像の作品が始まっていくんです。それが後半の部分でリアルに中国に行かれて、おばあさんがご自身の人生の深さを語られるシーンが来た時に鳥肌が立って。それまでバラバラだった音と映像がそこでリアルになった時に、「あ、彼女の中でもバラバラだった想いがひとつになったんだな」っていうのが強く感じられたので、感銘を受けました。すごいなと思いました。
他の作品を見ても技術的には皆さん素晴らしいと思います。どの作品を取っても、機材の使い方であったり、カラーグレーディング、みんなうまい。もちろんそれでご飯を食べていらっしゃる方も、多分いっぱい参加されているんだろうなと思うぐらいレベルは高かったです。
で、ここからはやっぱりどれだけ映像を続けていけるかだと思うんです。長くやらないと分からないことだったりとか、長くやることで実感することがあると思います。これから前に進んでいくことが重要になってくると思うので。やり続けられるために自分のやりたい信念だったり、自分というものをなんとなく持ち続ければ続けていけるんじゃないかなと思います。
これからはAIの時代になります。毎月のようにいろんなツールが出てきています。例えばすごくドラマチックな映像だったり、見たことのない映像表現というのがAIに取られてしまうかもしれません。だけども、人に届く映像というのは、やっぱり人が映った作品だと思うんです。なので第一歩は踏み出せたと思います。ここからは作り続けて、人が映っている作品を作っていってください。

花田さんのスピーチを聞いていましたけど、やっぱり「ここで撮るんだ」っていうような強い思いが伝わってきました。写真というのは、何を撮るかというより、なぜそれを撮るかっていう、そっちの方が写真として出てきますから。その思いが強い人たちが選ばれているのかなというふうに思いました。
賞を受賞すると、自分もそうでしたけど、孤独にずっと制作を続けてきて、背中を押してもらえるような、「こうやって続けていていいんだ」って思えるようなものだと思うので、これからもいい作品をたくさんつくって撮り続けていってください。今日は本当におめでとうございます。

THE NEW CREATORS Photo & Movie Awardsは第2回の開催も決定。作品募集は2025年11月頃を予定している。
●THE NEW CREATORS Photo & Movie Awards公式サイト