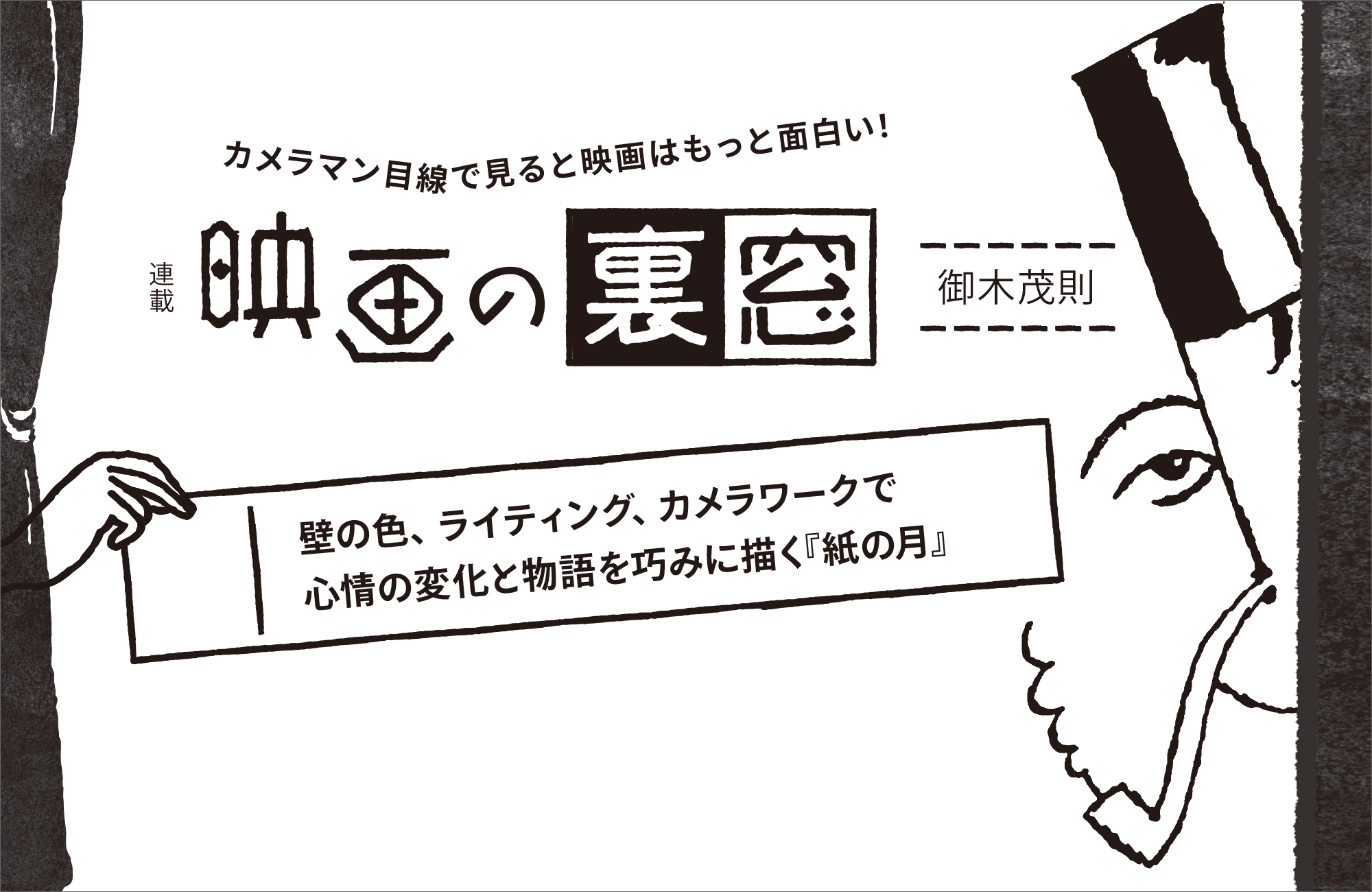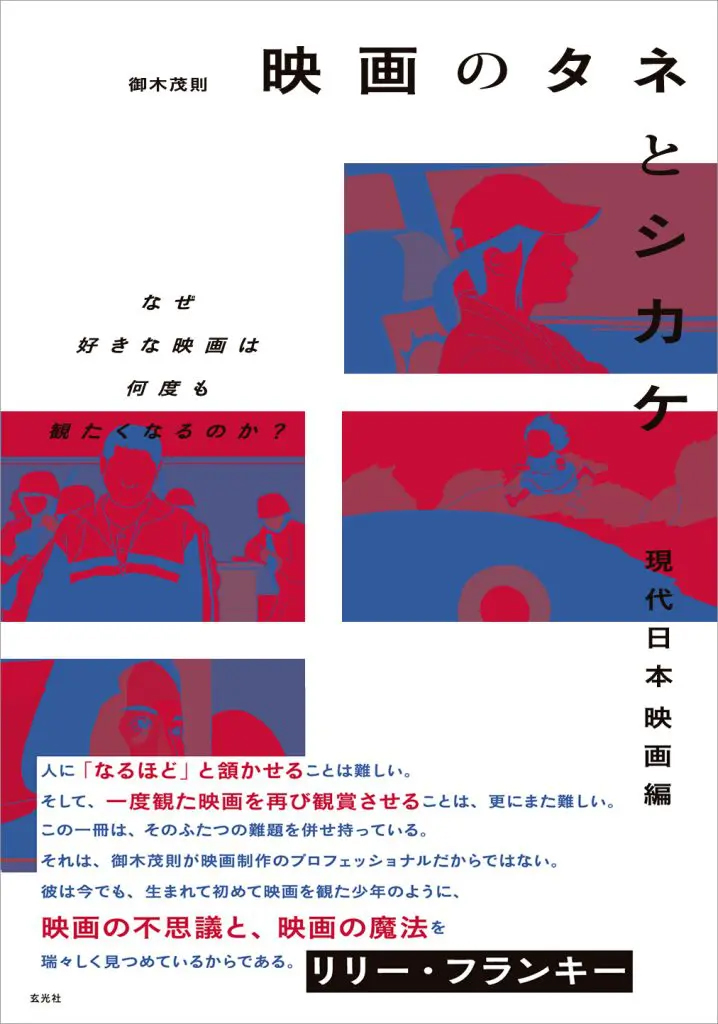御木茂則
映画カメラマン。日本映画撮影監督協会理事。神戸芸術工科大学 非常勤講師。撮影:『部屋/THE ROOM』『希望の国』(園子温監督)『火だるま槐多よ』(佐藤寿保監督) 照明:『滝を見にいく』(沖田修一監督)『彼女はひとり』(中川奈月監督) など。本連載を元に11本の映画を図解した「映画のタネとシカケ」は全国書店、ネット書店で好評発売中。
◉色味のコントロールと主人公の髪型と眉毛に着目して観る 『紙の月』(前編)
https://videosalon.jp/series/eiganoshasou_42/
実際の銀行と違って濃いグレーになっている異質な壁面
映画『紙の月』(吉田大八監督/14年)で、梅澤梨花(宮沢りえ)が勤めるあおば銀行月読支店は、横浜郊外にあるという設定ですが、実際には茨城県水戸市の旧銀行の建物の中に作られたものです。この銀行のセットは白をベースに、銀行員たちが座るデスクの周りには銀のラインが走る大理石調の柱、背後は幾何学的な装飾をした濃いグレーの壁面になっていることが特徴です。
実際の銀行は白をベースにして、アクセントで緑や青に橙、もしくは木を使ったデザインが多く見られます。この配色とデザインは来店者に対して威圧感を与えないことが目的と思われます。来客者側に黒や濃いグレーを使っている例はありますが、わざわざ行員側に使う『紙の月』の銀行のデザインは異質と言えます。
なぜ異質なデザインに気がつかないのか?
梨花がお金の横領を始めるときには、この異質なデザインを登場人物たちの背景にすることで、映像に独特なコントラストを作って、観客をドキドキさせる効果を上げています。そしてこの効果のためには横領をする前までは、観客に壁のことを意識をさせない必要があります。そのためにカメラ位置と人物の配置で、この濃いグレーの壁が主要な登場人物の真後ろにならないようにしています。
たとえば序盤(6分30秒〜)で初めて銀行のセットが映るシーンでは、窓口業務を行う行員たちを撮るときには、カメラ位置をグレーの壁に対して斜めや真横に置くことで、横にある白い壁が背景になるようにしています。
梨花のデスクはグレーの壁が背景ではなく、左側の壁になるように配置しているので、梨花を正面から撮ってもグレーの壁が背景にはならないようになっています。グレーの壁が人物の背景になってしまうときには、照明を調節して強い光を当てて、映像では薄いグレーに見えるようにして目立たなくさせています。
後々、グレーの壁は効果的に使われる
最初にグレーの壁が効果的に使われるのは、梨花が初めて横領をするシークエンス(37分30秒〜)です。このシークエンスは梨花が裕福な独居老人の平林(石橋蓮司)から、定期預金にする200万円を預かって銀行に戻ってきたあと、平林から梨花に電話がかかってきたことから始まります。
梨花と孫の光太(池松壮亮)が不倫していることを知らない平林は、大学の学費の支払いに困っている光太が、梨花にお金をせびったのではないかと勘ぐります。そして平林は光太にお金を貸すな、と梨花に告げます。平林の意地悪に見える態度に対して、梨花は平林の200万円を横領して光太に渡す決断をします。
梨花が200万円を横領するために、窓口係の相川恵子(大島優子)に平林の定期預金が取り消しになったと嘘をつくときの2ショットで、グレーの壁が彼女たちの背景に目立つように映されます。
グレーの壁がさらに効果的に使われているのが、梨花が定期預金証書を偽造するために未使用の定期預金証書を盗み、横領の方法が大胆になっていくシーン(66分45秒〜)です。このシーンではグレーの壁を背景にして歩く梨花を、カメラが横に移動をしながらスローモーションで捉える、印象的な引き画のショットがあります。
このショットではグレーの壁へ当てる照明を弱めて壁を暗く見せることで、映像のコントラストを強くしています。まだ梨花の犯罪は順調に進んでいるので、彼女をピカレスクロマンに登場する主役のように、格好よく見せています。
グレーの壁が最も印象的に見えるのが、梨花が横領していることに気がついたベテラン行員の隅より子(小林聡美)が、上司である次長の井上(近藤芳正)に報告をしているシーン(78分39秒〜)です。終業後の銀行にふたりだけが残っているのを見せる伏せ目の引き画のショットでは、ふたりの周りの照明が消されています。グレーの壁をさらに暗く見せることで、映像には圧迫感が生まれて、物語が破滅へと向かっていることを予感させます。
ボケていく様子を部屋の飾り変えで表現する
梨花の顧客で、浪費癖のある名護たまえ(中原ひとみ)は3回登場しますが、時間経過で彼女の部屋や玄関を飾り変えることで、彼女の内面の変化が描かれます。
最初(17分37秒〜)は、部屋には通販で買った物が溢れていますが、収まるところに収まり整理はされています。次(58分42秒〜)は玄関では鉢植えが割れていて、室内ではテーブルの上は散らかり、食器棚の中の食器がなくなっています。名護がボケ始めていることがわかります。
そして最後(84分45秒〜)は、親族がお手伝いさんに頼んで片付けているようですが、同じ商品が何個も部屋中に積み上げられていることで、名護のボケがさらに進んでいることが分かります。
名護は梨花の合わせ鏡?
この名護が最後に登場をしたあとのシーン(86分54秒〜)は、梨花が光太と暮らすために買ったマンションになります。部屋は梨花と光太が思いつくままに買ったと思われる物で溢れて、インテリアにはまとまりがありません。
そしていくつかのシーンを挟んだあと(90分22秒〜)、梨花が自分の家に戻ってきて、散らかり放題になっている居間を見て、自分の家が名護の家よりも酷い状態になっていることを自覚させられます。
梨花は名護のことを冷ややかな目で見ていましたが、梨花の感覚と日常が歪んできていることを自覚させる名護は、梨花の合わせ鏡と言える存在です。
梨花の倫理観の麻痺を描く照明
梨花が横領を平然とできるようになってきたことは、照明によっても巧みに表現をされています。資産家の小山内夫婦の家の居間で、梨花が彼らの孫への積立貯金の相談をされるシーン(66分19秒〜)と、偽造証書を作るシーンを挟んだあと、梨花が再び小山内夫婦を訪れて、偽造した証書に判子を捺させるシーンになります。
このふたつのシーンは時間帯が昼で、場所も同じ小山内家の居間なので、庭からの外光として当たる照明には変わりません。変えられているのは、梨花の顔の暗部に当たる照明で、1度目と比べて2度目では梨花の顔は暗くなっています。
このときの梨花は満面の笑みを浮かべていて、彼女の背景にあるボケている庭木には、光を当ててキラキラと輝かせています。梨花の顔の明るさだけを暗くして、映像のバランスを崩すことで、彼女の倫理観がおかしくなっていることが描かれます。
梨花の心に合わせてカメラが動く
『紙の月』では、物語のシチュエーションに合わせてカメラが動きます。オープニングの回想シーンを経て、現在パートで動かなかったカメラが動き出すのが、駅の改札口で梨花が光太と偶然再会をするシークエンス(14分30秒〜)になります。梨花の心がときめくことに合わせて、カメラは動き始めます。
カメラは梨花と光太が逢瀬を重ねる過程、ラブホテルへ行くとき、クリスマスのイルミネーションが灯る夜の街をふたりが歩くときなどでも動きます。カメラの動かし方は移動車に載せて動かすなど、オーソドックスな方法を使っています
梨花と光太がホテルのスイートルームで豪遊をするシークエンス(61分〜)では、カメラの動かし方が大きく変わります。彼らの気持ちの高揚に合わせて、カメラは空間を自由自在に動き回れるステディカム、さらに小型クレーンやズームレンズを使って、ふたりとともにはしゃぐように動き回ります。
破滅に向かう後半の銀行でのカメラワーク
スイートルームでのシークエンスが終わると、梨花と光太の逢瀬ではカメラが動かなくなります。カメラは物語の次の展開である横領が起きる、銀行の中で動くことが多くなり、カメラは梨花が横領をしているときに動いています。
後半になると同じ銀行の中ですが、カメラの動くタイミングが変わってきます。梨花の横領に隅より子が気がついたことで、最後の展開になる梨花の破滅が始まるときです。カメラは隅の動きに合わせて動くことが増えます。『紙の月』のカメラワークは、この映画の三幕構成(不倫・横領・破滅)に準じていることが分かります。
参考資料 :『紙の月』Blu-ray、Blu-ray特典ブックレット、『紙の月』脚本
「映画のタネとシカケ 現代日本映画編」〜なぜ好きな映画は何度も観たくなるのか?(著・御木茂則)全国書店、ネット書店で好評発売中
ビデオサロンの好評連載「映画の裏窓」をベースに図版を作成して、大幅に改稿した書籍「映画のタネとシカケ」。前著から約2年。今度は世界から評価されている、2000年以降の日本映画を取り上げた「映画のタネとシカケ 現代日本映画編」が好評発売中。