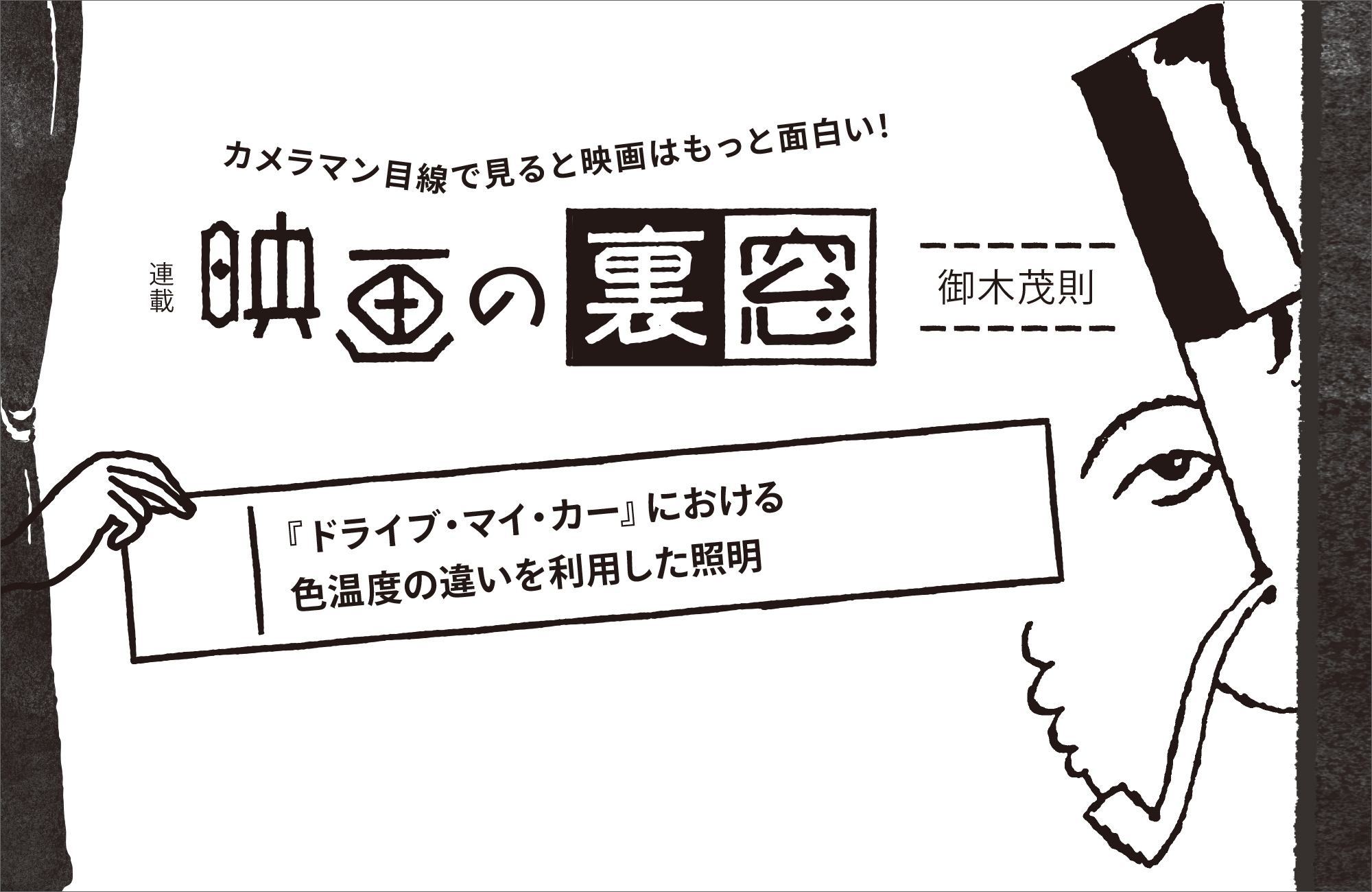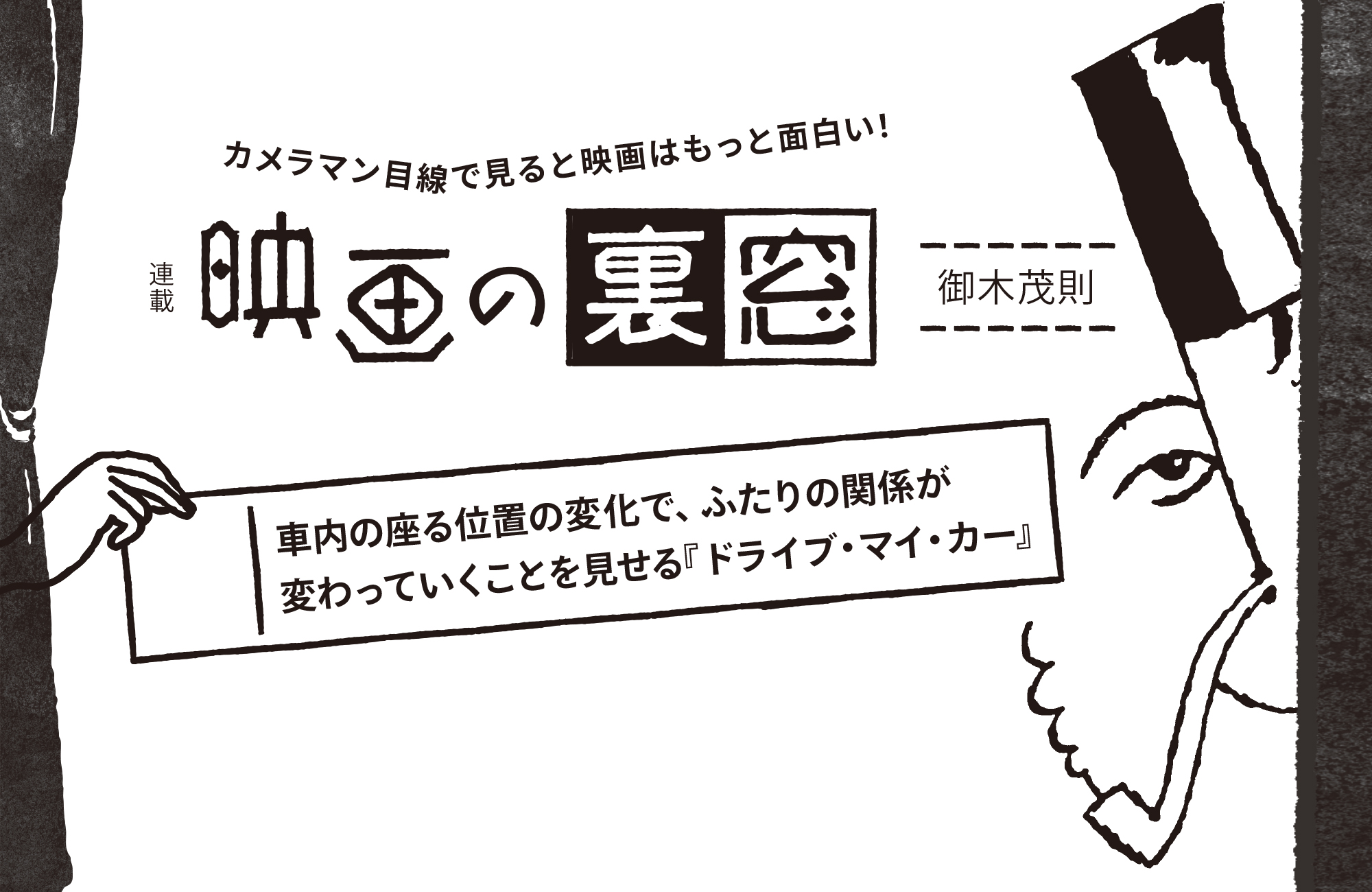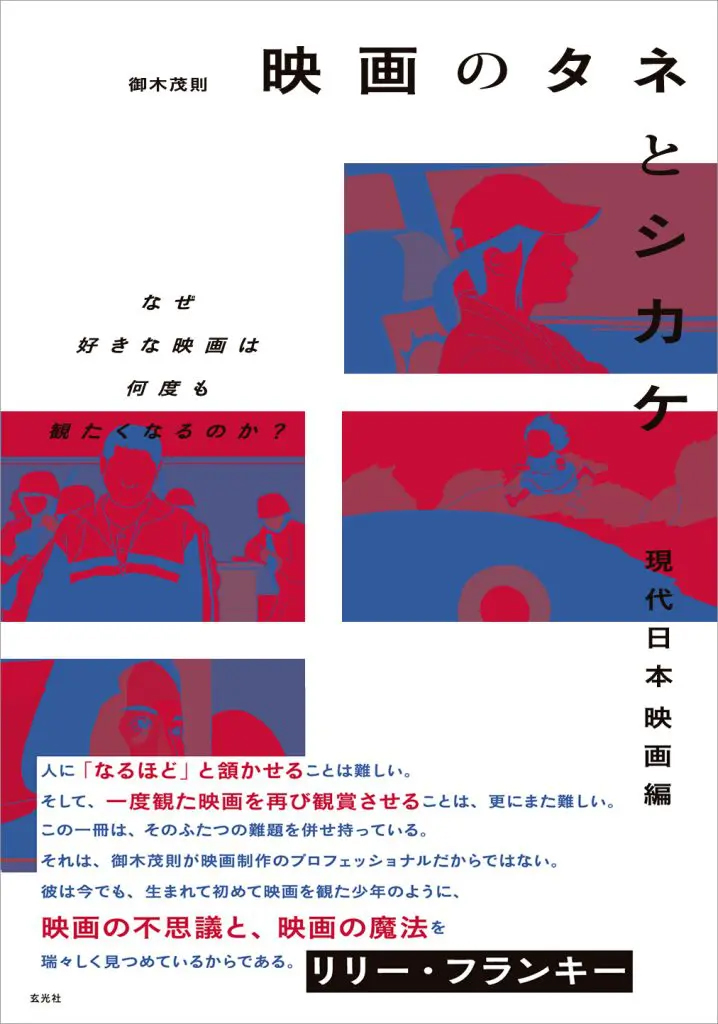御木茂則
映画カメラマン。日本映画撮影監督協会理事。神戸芸術工科大学 非常勤講師。撮影:『部屋/THE ROOM』『希望の国』(園子温監督)『火だるま槐多よ』(佐藤寿保監督) 照明:『滝を見にいく』(沖田修一監督)『彼女はひとり』(中川奈月監督) など。本連載を元に11本の映画を図解した「映画のタネとシカケ」は全国書店、ネット書店で好評発売中。
濱口竜介監督が、今までに撮った長編映画はドキュメンタリー映画が3本、劇映画が8本あります。2021年に公開された10本目の作品になる『ドライブ・マイ・カー』は、村上春樹氏の短編集「女のいない男たち」の一編「ドライブ・マイ・カー」を中心に、村上氏からの了承を得て「木野」と「シェエラザード」のエピソードを加えて脚本にしています。
俳優・舞台演出家の家福(かふく)悠介(西島秀俊)は、脚本家である最愛の妻、音(霧島れいか)と深く愛し合う生活を送っています。ある日、家福は出かける前、音から今晩帰ったら話があると言われます。深夜に家福が帰宅をすると音は部屋で倒れています。音は家福に何を話したかったのか、秘密と喪失感を残してこの世を去ります。2年後、家福は演出家として招かれた、広島で開かれる演劇祭に愛車で向かいます。家福は2カ月間の広島滞在中、演劇祭の事務局からの要望で、愛車の運転を渡利みさき(三浦透子)に任せることになります。みさきの運転と寡黙さを、家福は気に入ります。ふたりが似た葛藤を持つことが次第に明らかになります。
小説と映画では妻の描き方が異なる。映画では生きている姿が描かれる
映画『ドライブ・マイ・カー』と原作の小説「ドライブ・マイ・カー」は、どちらも家福の妻が残した秘密と喪失感が物語の核となりますが、見せ方は異なります。
小説では家福の妻の名前は出ず、登場もしません。妻の不倫相手だった高槻と何度もバーで会って話をする中と、家福がみさきを聞き手にした会話の中で妻の話をすることで、彼女の不在と謎を浮かび上がらせます。
映画『ドライブ・マイ・カー』(以下『ドライブ』)では、妻には音という名前があります。そして前半35分まで生きている姿が描かれます。観客は生きている音の姿を見たことで、家福の主観で語られる音の話にどこか違和感を持ち、家福が何かから目を逸らしていることを感じさせます。
車内のカメラ位置で見せていく、家福と音、ふたりの違和感
音が生きているときには、車内でのカメラの位置からも観客に違和感を感じさせます。家福と音が一緒に車に乗るシーンは2回あります。
最初は家福が音をテレビ局まで送るシーン(3分57秒〜)です。家福と音の乗る車が走る客観のショットを、ふたつ続けて見せ、そのあと車内では家福と音の単独のショットを、ななめ後ろから映します。車内での会話からはふたりは仲の良い夫婦に見えますが、顔がチラリと見える後ろ姿で映すことで違和感を与えます。
次は家福と音が、幼くして失った娘の法事へ行った帰り道(21分21秒〜)です。車の運転は音がしています。最初はフロントガラス越しに、正面からふたりを単独のショットで映します。彼らが娘の話を始める直前に、再びふたりをななめ後ろから映す単独ショットになります。
家福と音を後ろ姿で見せるこのカメラ位置は、ふたりが娘を失ったことがきっかけで何か隠し事があることを匂わせます。
異なる色温度の照明を当てる、ミックス光照明を効果的に使う
光の色は色温度というはK(ケルビン)という数値で表せます。6000Kを超えると青い色味、2700〜3000Kになると赤ぽっい色味になります。自然光を例にすると、昼間の太陽光の色温度5000〜6000Kで白い光、曇りになると色温度6500Kで高く青い色味、日の出や日の入りの太陽光は1850Kで色温度は低く赤い色味になります。
人間の脳は優れた調整機能があるので、光源の色温度が高くても低くても、目では白いものは白く見せています。この色温度、光源の色を無色化することを「色の恒常性」と言います。このため人間は日常生活では、色温度の変化に気がつきづらいのです。
映像の色味を意図した色再現をするためには、カメラ側で色温度を設定をする必要があります。たとえばカメラ側の設定を5500Kにすると、昼間の太陽光は白く、曇りの光は青っぽく、日の出の光は赤っぽく映ります。カメラ側の色温度の設定値は、5500Kと3200K、中間の4300Kが使われることが多いです。
『ドライブ』の照明はその場にある光源を生かして、必要最低限の照明を足して、映像を自然な印象に見せるプラクティカル照明です。要となるシーンになると、その場にある光源の色温度とは異なる色温度の照明を当てる、ミックス光照明を効果的に使っています。
『ドライブ』で最初にミックス光照明を使うのは、喪服を着た家福と音がお寺で娘の法事をしているシーン(20分47秒〜)です。このシーンの中で仏間で並んで座っているふたりを、カメラは横位置から、胸元から上ぐらいを見せるバストサイズで撮っています。ふたりの後ろと横からは障子越しの青みのある自然光が当たり、正面にある仏壇側からは照明で、赤みのある光を足しています。
この時点ではこのミックス光照明が、意図的なものかはまだ分かりませんが、このあと繰り返し使われることで、意図は明確になっていきます。
ふたりに異なる色味の光を当て、妻の白目には光を当てない
次にミックス光照明が使われるのは、家福と音が夜に自宅のマンションへ戻って、ふたつのフロアーライトを点けたあと、すぐにソファーの上で愛し合い始めるシーン(23分23秒)です。照明は部屋全体は青系に少し緑色が混ざった光、それにフロアーライトの赤ぽっい光が足されています。
ここでのミックス光照明は、ふたりに異なる色味の光を当てています。家福と音が抱き合っているのを、正面からそれぞれ映すふたつのショット(24分46秒〜)では、家福には赤っぽい光、音には青緑色の光が当たっています。
ふたりが愛し合っているのを見せるショットですが、異なる光の色味は、ショットの途中で音がカメラを見つめてくることも加わり、不穏でミステリアスな印象を与えます。家福が仰向けになって、音が上に跨るのを俯瞰から映すショット(26分56秒〜)では、家福には右側から青緑色の光、左側から赤ぽっい光を当てています。音の背中には青緑色の光が当たり、彼女の肌の白さで色味が強調されています。この不気味な色合いのショットは、ふたりの間に何か決定的な溝があることを感じさせます。
家福と音がソファーに横たわっているのを、正面から映すバストサイズのツーショット(25分12秒〜)では、音の瞳に当てる光の角度に工夫があります。
音の瞳の黒目には点光源を小さく映し込んでいるので、瞳の位置は分かりますが、白目には光を当てないようにしています。黒くなった音の瞳からは、彼女が何を考えているのか読み取られさせたくない、立ち入ることのできない領域があることを感じさせます。
高槻が物語のキーパーソンであることを照明からも暗示する
音が亡くなったあと、ミックス照明は、音と不倫関係にあった高槻が登場する4つのシーンで使われます。
最初は駐車場で高槻が家福を呼び止めて、バーに誘うシーン(69分34秒〜)です。家福と高槻に当たる青い光ですが、高槻の背景を黄色っぽい光にしています。また高槻の顔を暗くして表情を見えづらくして、彼の捉えどころのなさを光の明暗からも表しています。
バーで家福と高槻が音の話をするシーン(70分30秒〜)では、バー全体の光は少し赤っぽい色味、ふたりにはカウンター側から青い色味の光を当てています。
高槻が建物の入り口で家福を呼び止めて、芝居の稽古に遅れたことを謝るシーン(100分27秒〜)では、外からは青っぽい自然光が当たり、室内から照明で赤っぽい光を足しています。
最後はふたりが再びバーで話をするシーン(115分47秒〜)です。バー全体の光は赤っぽい色味で、家福と高槻にはトップからの照明を当てて、ふたりの身体の輪郭を強調しています。このトップからの光は、家福だけ青っぽい色味にしています。このシーンで色味に違いがあるのを分かりづらくしているのは、繰り返し同じようなミックス照明を使ってくどくなるのを避けたためと考えられます。
音が登場するシーンで使っていたミックス照明のニュアンスを、高槻が登場シーンにも使うことで、高槻が物語のキーパーソンであることを、照明からも暗示します。
参考資料 :Blu-ray『ドライブ・マイ・カー』と特典映像「女のいない男たち」(村上春樹)『ドライブ・マイ・カー』パンフレット「カメラの前で演じること」(濱口竜介) 「アジア交流ラウンジ イザベル・ユペール×濱口竜介」(東京国際映画祭YouTube)「『ドライブ・マイ・カー』撮影報告 映画撮影230号」(四宮秀俊)
後編はこちらから
「映画のタネとシカケ 現代日本映画編」~なぜ好きな映画は何度も観たくなるのか?(著・御木茂則)全国書店、ネット書店で好評発売中
ビデオサロンの好評連載「映画の裏窓」をベースに図版を作成して、大幅に改稿した書籍「映画のタネとシカケ」。前著から約2年。今度は世界から評価されている、2000年以降の日本映画を取り上げた「映画のタネとシカケ 現代日本映画編」が好評発売中。