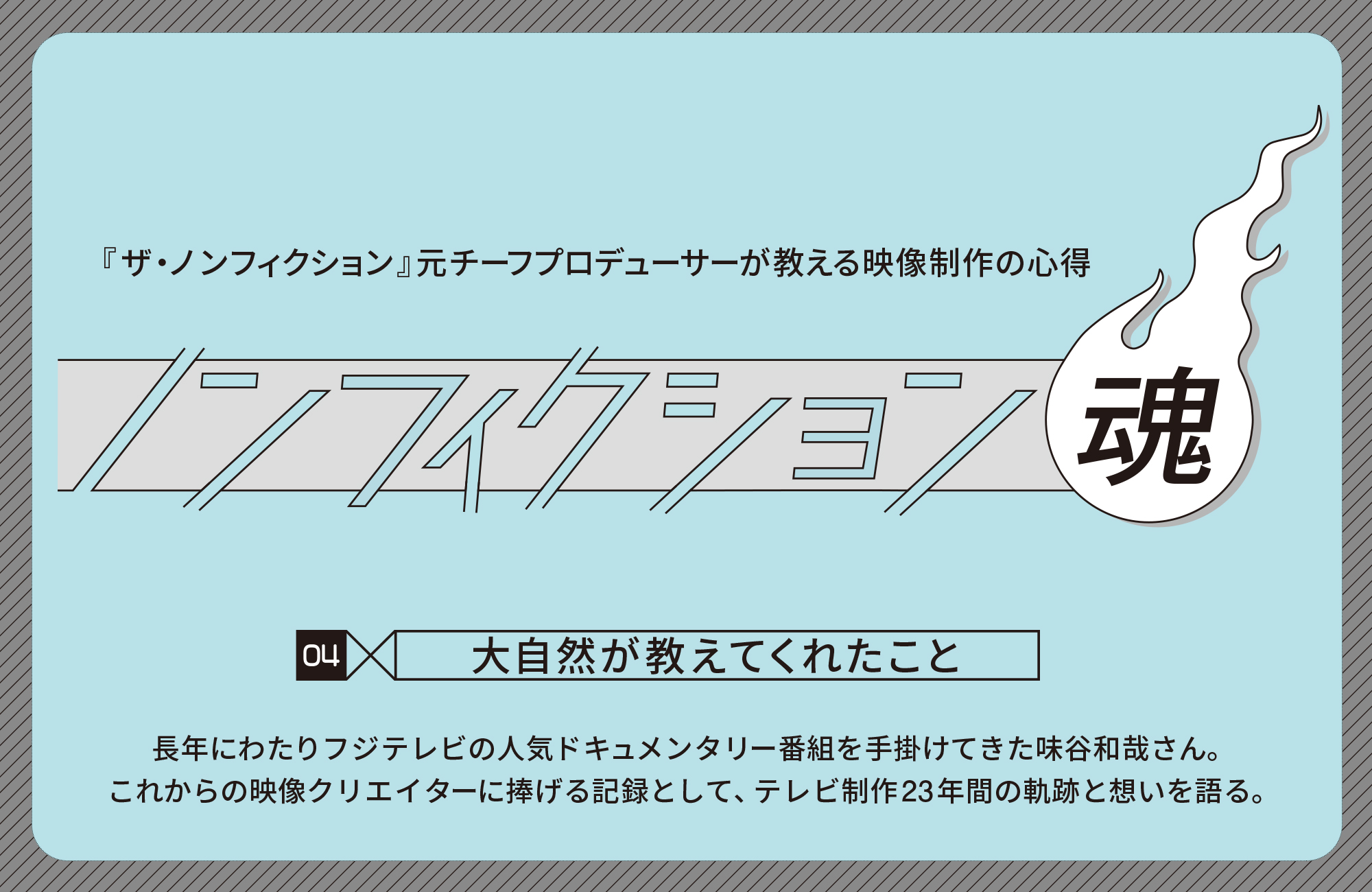長年にわたりフジテレビの人気ドキュメンタリー番組を手掛けてきた味谷和哉さん。これからの映像クリエイターに捧げる記録として、テレビ制作23年間の軌跡と想いを語る。
文 味谷和哉
1957年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、読売新聞大阪本社 社会部記者を経て、1992年フジテレビ入社。以来ドキュメンタリー畑一筋で、ディレクター、プロデューサーとして制作に携った作品は500本を超える。2003年〜15年まで『ザ・ノンフィクション』チーフプロデューサー。文教大学非常勤講師。
●主な作品と受賞歴
▶︎ディレクターとして
1993年1月 『なんでやねん西成暴動』
1993年7月 『娘のことを教えて下さい』(FNSドキュメンタリー大賞佳作)
1996年7月 『幻のゴミ法案を追う』(FNSドキュメンタリー大賞グランプリ)(ギャラクシー賞奨励賞)
▶︎プロデューサーとして
2007年6月 『花嫁のれん物語 〜地震に負けるな能登半島〜』(ニューヨークフェスティバル銅賞)
2007年7月 『負けんじゃねぇ 〜神田高校に起こった奇跡〜』(ギャラクシー賞奨励賞)
2010年10月 『ピュアにダンスⅣ〜田中家の7年〜』(USインターナショナル フィルム&ビデオフェスティバル GOLD CAMERA賞(金賞))(国際エミー賞 ノミネート)他、国内外受賞多数
1日中車で走っても景色が全く変わらない。短冊のような虹が出る。星だらけの中に夜空がある。川の中を雲が流れる。そんな場所に2カ月もいたことがあります。チベット高原。そう、今は中国の一部ですが、昔は「王国」と呼ばれたラマ教の聖地です。
紀行番組のディレクターとして訪れたチベットの圧倒的な大自然
前回は『ザ・ノンフィクション』の主題歌「サンサーラ」が生まれたインドの話をしましたが、その翌年、ディレクターとしてゴールデンタイムの紀行番組を制作することになりました。
それまで新聞記者として、大阪府警本部の「長屋」と呼ばれたウナギの寝床のような場所にいたので、何よりもその大自然には衝撃を受けました。
まず空気が薄い。中心都市「ラサ」で標高3500m。富士山の頂上にいるようなものです。さらにロケでは、5000m近くの場所にも行き、「高山病」にも悩まされました。酸素は平地の半分程度しかありません。いわゆる「酸欠状態」です。そして、何よりも圧倒的な大自然です。
空の碧、雲の白、川の澄み切った色。何もかも平地とは違います。基本、点在する町以外はテントを張って、ランドクルーザーで移動して、動植物や現地の人々を撮っていきます。ある夜などはテントから出た瞬間に星の数が多すぎて明るいので、「ウァーッ」と絶叫したこともあります。菜の花の色があまりにも黄色いので、その「純粋さ」に涙が零れたこともあります。
道を走っていたら、5mはあろうかという茶色い見たこともない動物が道を塞いでいるので、何かわからずスタッフ全員「何だあれは」と思わず声を上げました。その正体はそれが飛んで初めてわかりました。巨大な鷲が羽を広げて、向こう向きで、道のど真ん中で休んでいたのです。高地ならではの光景でした。何もかも、想像を絶していました。
新米ディレクターとしてベテランカメラマンと向き合うプレッシャー
さて、番組です。インドからの付き合いで、俳優の榎木孝明さんがチベットの自然に触れながら、最後は世界で最も高地にある鳥の営巣地に向かう、という企画。今ではなかなかチベットの企画もお目にかかりませんが、テレビマンとしてまだまだ新米の時に、こんな体験をさせてもらったのは、ラッキーでした。
しかし、喜んでばかりもいられませんでした。何より、この企画の肝は「どれだけ自然のいい映像を撮れるか」であるため、ディレクター以上にカメラマンが大切になってきます。そのカメラマンはエベレストにも番組で登頂したことのある「猛者」でした。
世界中の自然を撮ってきているプロ中のプロ。20歳以上も年上のカメラマンに、紀行番組初心者のディレクターが太刀打ちできるわけがありません。経験も技術もかなわない相手とどう向き合うか、それは大自然に立ち向かう以上に精神的にはきついことでした。
最初の1カ月はロケハンとロケを兼ねて、主役なしでチベット高原を駆け巡りました。私は、そのカメラマンの仕事ぶりをじっくり観察していました。最初はほとんどAD扱いされて相手にもされず、彼の指示のままにロケは進んでいきました。見ているだけで仕事はさせてもらえませんでした。
そして、1カ月後主役の榎木さんとプロデューサーが現地に乗り込んできて、ここからが本格的なロケの始まりです。最初に中心都市「ラサ」の中華料理店でスタッフ全員の結団式をしました。通訳、ドライバーや野営時の食事係など総勢20人が円卓を囲んで食事をしました。
宴も終盤になったころ、カメラマンがこの1カ月のロケハンロケの総括を行いました。そこで私は屈辱的な仕打ちを受けます。
カメラマンはみんなの前でこう言いました。「味谷ディレクターはまだまだですね」名指しで批判されたのです。しかし、それに対抗する言葉は私にはありませんでした。その通りだからです。未熟でした。
プロの眼にはそう映ったのです。プロデューサーに励まされ、その場はやり過ごしましたが、「頑張ります」としか言えませんでした。ここからのロケは、主役も入りいかにディレクターとして認めもらえるかの正念場です。



常識を覆されたチベットの家族制度
途中、常識を覆された事実がありました。チベットの遊牧民は「一妻多夫」という家族制度を取っていました。「一夫多妻」は聞いたことがありましたが、「一妻多夫」にも理由がありました。男はヤギなどを連れて遊牧をするため、半年に1回くらいしか家に帰ってきません。妻は定住しており、そこで何人かの夫を持って子をなし、家族を増やしていくのです。自分がいかに小さな常識の中で、暮らしてきたことか、と少々恥ずかしくもありました。
榎木さんも、この制度に納得して、インタビューをしてくれました。そして、この俳優さんにもロケ中驚かされたことがありました。私と榎木さんは同じテントで寝ていました。よくわかったのは、「男前は寝ていても男前」だということです(笑)。
人間死ぬときは死にますから
それはさておき、ある時夜中に雷鳴が轟きました。夜中であるのに、稲光で昼間のように明るくなり、それは徐々に我々のテントに近づいてきます。大平原で金属があるのは我々のテントだけです。雷が落ちたような音も聞こえて、耳が痛いくらいの雷鳴が襲ってきます。私はぶるぶると震えが止まらず、榎木さんに言いました。「榎木さん、僕たち死にますよ」。すると、彼は平然とこう言いました。
「人間、死ぬときは死にますから」
この言葉を聞いて、楽になりました。表面はソフトですが、胆力のある俳優さんです。
その後、幻想的な塩湖や、鏡の様に空を映した大きな湖など、ロケは続きました。己の未熟さ、小ささを思い知ったロケでした。カメラマンにも必死でくらいつきましたが、最後まで敵いませんでした。しかし、最後に一言だけ、こう言われてうれしかったことを、今でも覚えています。
「まだまだだけど、あの塩湖の演出はよかったよ」