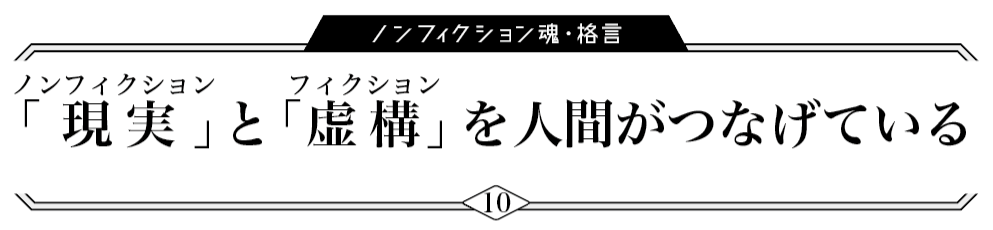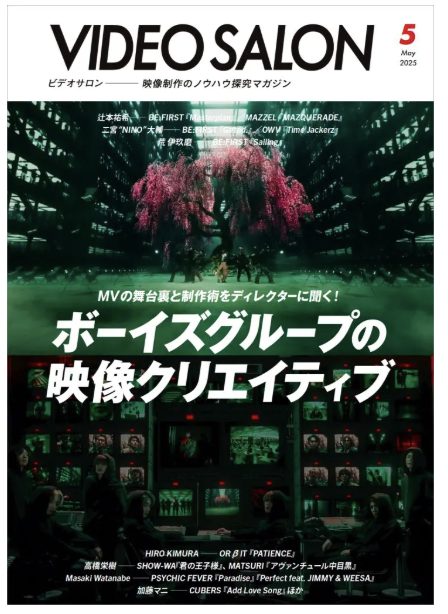長年にわたりフジテレビの人気ドキュメンタリー番組を手掛けてきた味谷和哉さん。これからの映像クリエイターに捧げる記録として、テレビ制作23年間の軌跡と想いを語る。
文 味谷和哉
1957年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、読売新聞大阪本社 社会部記者を経て、1992年フジテレビ入社。以来ドキュメンタリー畑一筋で、ディレクター、プロデューサーとして制作に携った作品は500本を超える。2003年〜15年まで『ザ・ノンフィクション』チーフプロデューサー。文教大学非常勤講師。
●主な作品と受賞歴
▶︎ディレクターとして
1993年1月 『なんでやねん西成暴動』
1993年7月 『娘のことを教えて下さい』(FNSドキュメンタリー大賞佳作)
1996年7月 『幻のゴミ法案を追う』(FNSドキュメンタリー大賞グランプリ)(ギャラクシー賞奨励賞)
▶︎プロデューサーとして
2007年6月 『花嫁のれん物語 〜地震に負けるな能登半島〜』(ニューヨークフェスティバル銅賞)
2007年7月 『負けんじゃねぇ 〜神田高校に起こった奇跡〜』(ギャラクシー賞奨励賞)
2010年10月 『ピュアにダンスⅣ〜田中家の7年〜』(USインターナショナル フィルム&ビデオフェスティバル GOLD CAMERA賞(金賞))(国際エミー賞 ノミネート)他、国内外受賞多数
現実か虚構か、どちらかわからない場面に遭遇したことありますか?
今年2025年2月、そんな体験をしました。場所は石川県七尾市。昨年元日の大地震で大きなダメージを受けた場所です。
2006年から7本のドキュメンタリーを放送したシリーズ企画
七尾市にはちょっとした縁があります。そこにある和倉温泉の旅館を『ザ・ノンフィクション』は追い続けているからです。2006年から撮影開始、昨年まですでに7本のドキュメンタリーを放送しています。
旅館の名は「多田屋」。番組名は『花嫁のれん物語』です。今から19年前にそれまで何本か仕事をしたことのある大里正人ディレクターが持ってきてくれた企画です。
この地方には婚礼の日に、仏間にかけられた加賀友禅の「花嫁のれん」を花嫁がくぐってその家の人になる、という風習があります。いわゆるイニシエーション(通過儀礼)ですが、私はとても興味を持ちました。「日本」を感じたからです。しかも大里ディレクターは、人の気持ちを描くのがとても上手い手練れです。

老舗旅館の御曹司に見初められた若女将の奮闘記
ストーリーは東京で看護士をしていた女性が、この老舗旅館の御曹司にテニスサークルで見初められて嫁ぐことになり、この「花嫁のれん」をくぐって多田屋に嫁ぎ、若女将としてデビューするまでをとにかく1年間追いかけよう、ということで話はまとまり、番組は動き始めました。まさか、この時は20年近くもその後、この企画が続くことになろうとは、当初は私も大里ディレクターも知る由もなかったのですが、それが「多田屋」さんとの長いお付き合いの始まりでした。その後、何度も訪れることになります。
初めて挨拶と打ち合わせに訪れた時のことを、よく覚えています。静かな能登湾の内海は波も小さく穏やかにたゆたっています。そこに沈む夕陽は息をのむほど美しかったのです。しばらく声が出ませんでした。そして、「多田屋」の人々もその景色のように穏やかで、心が和みました。暖かい毛布にくるまれたような歓待ぶりでした。そこには日本の原風景があり、とても懐かしい気がしました。私はこの旅館と番組から、沢山のことを学ばせてもらいました。
女将デビューの日の粋な計らい
初回放送した番組には忘れられないシーンがあります。嫁いだ若女将の弥生さんが、1年の厳しい女将修業を終え、女将として初めてお客さんの各部屋を挨拶に回るデビューの日のことです。
旅館側の「粋な計らい」でお客さんの中に、弥生さんのご両親が招かれていたのです。もちろん、若女将は知りません。ふすまを開け「当館の若女将でございます」と両親の待つ客室に入った弥生さんは、父と母に気づき、驚きます。そして何も話せなくなり、泣き出すのです。
それまでは親子としてしか接していなかった両親。それが今は、お客と女将という全く別の役割として対峙している。泣き続ける娘に母親は言います。親子の間にある敷居を指さし、「ここに大きな川があるように感じたのかもしれない」と。
「孤独」「自立」——。私はその後、その涙の意味を考え続けてきました。弥生さんにも直接聞いたことがありますが、ご本人もはっきりと理由が分からないようでした。それはそうでしょう。これは心の奥底にある潜在的なものから出た涙でしょうから、分からなくて当然です。私も結局ははっきりとした結論が出ないまま、今に至っています。
でも、ひとつ言えることはその涙の後、弥生さんはしっかりとした旅館の女将になっていくのです。その涙も一人前になるためのひとつの「通過儀礼」だったのかもしれません。
女将と並行して父と子の成長物語も
この番組では弥生さんの女将としての「成長物語」と並行してもうひとつの「成長物語」があります。それはご主人・健太郎さんと、当時の多田屋の社長であるその父・邦彦さんとの関係性です。決して仲が悪いわけではないのですが、仕事一筋の父とは子供の頃から、コミュニケーションがあまりなく何故かギクシャクした遠い存在でした。
父は和倉温泉全体を引っ張るほどのやり手の旅館経営者。その跡継ぎとして越えたくてもなかなか越えられない存在だったのです。しかし、彼はネットを利用した自分なりの新たな戦略で、果敢に父親に挑んでいきます。
このふたつの「成長物語」がこのドキュメンタリーの見どころとなってゆき、その心の変化を丁寧に大里ディレクターが掬い上げていったのです。そのドキュメンタリーのディレクションの真髄をある時、健太郎さんから直接聞いたことがあります。
「僕はこれまで、父親とはあまり話したことがなく、父が何を考えているのかが分からないことが多かったのです。でも大里さんに取材に入ってもらって色々話を聞いているうちに父との距離が縮まった気がするんです。その意味でも取材を受けてよかったと思います」と。
メディアは人と人を結びつける触媒
直接は話せなくても取材者が入ることでふたりの距離が縮まる。それまで考えたことのない「目からうろこ」の考え方でした。私自身取材者は邪魔者ではないのか、と常にどこかに罪悪感をもって取材したことも多かったので、「役に立っている」と言われたことは嬉しいことでした。メディアはまさに語源の通り、人と人を結びつける「媒介」「触媒」でもあるのです。ドキュメンタリーを作る人間として、彼には教えられました。
番組テーマ曲「ハナミズキ」がプラットホームに鳴り響く
そして、この番組にはもうひとつヒットの秘密があります。それは、テーマ曲「ハナミズキ」(一青窃・作詞作曲)。健気に人間としての成長を夢見る夫婦には、ぴったりの楽曲で、プロデューサーの私が指定することもあるのですが、これは音効さん(増子 彰さん)に一本取られました。
そんな足掛け20年の月日が積み重なり、昨年の大地震で甚大な被害を受け、「多田屋」はまだ再開のめどが立っていません。そして、2025年2月——。「多田屋」の現会長・邦彦さんの訃報が届きます。73歳。見かけも生き方もかっこいい男性でした。和倉温泉の総湯に入っての心不全でした。
日本海側に大雪警報が出ている中、仕事を終えて新幹線で金沢まで行き一泊。翌早朝七尾線で雪の中、七尾へ向かいます。私が訪れていた頃は新幹線がなかったので、いつもは能登空港からバスでした。
葬儀にはぎりぎり間に合いましたが、お焼香を上げる時、目線を合わせただけで健太郎さん、弥生さんにかける言葉もありませんでした。その帰り道です。
七尾駅に金沢から列車が入ってきました。折からの雪が舞っています。プラットホームには私だけです。その時、「ハナミズキ」のメロディーが突然流れてきたのです。理由もなく、しばし号泣する自分がいました。これはフィクションではないのか、とーーー。おそらく、あの時の弥生さんもそうだったのではないか、と。