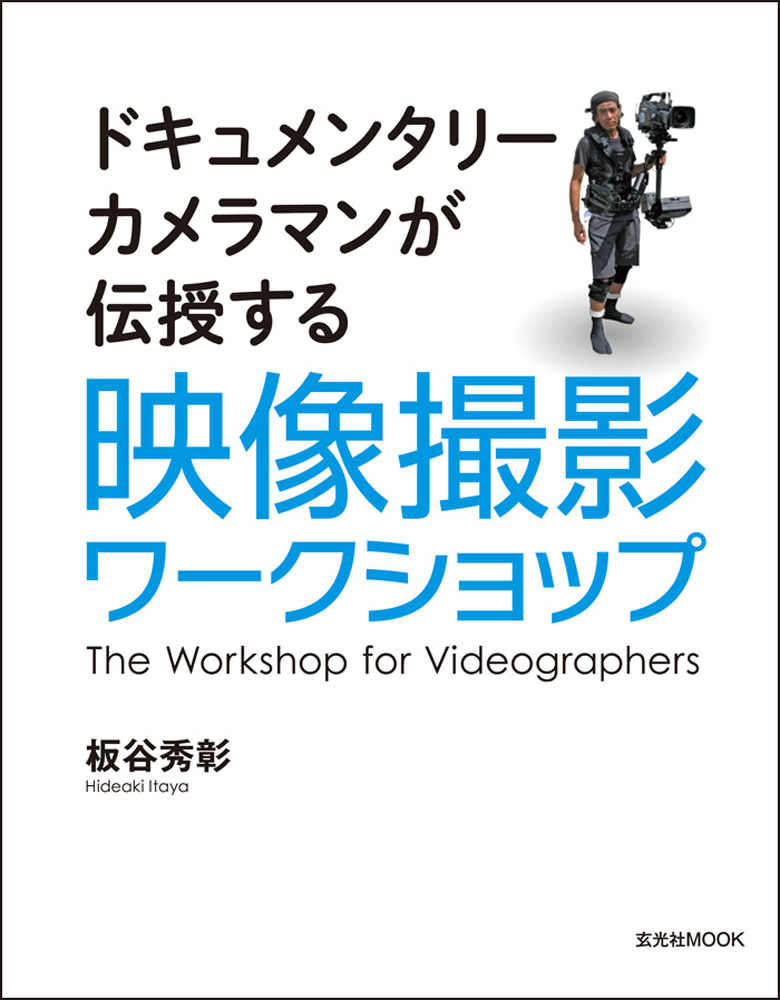10年以上にわたってビデオサロン誌上で続いてきた髙間賢治さんと板谷秀彰さんの連載。それぞれ映画とテレビというフィールドで長く活躍されているお二人ですが、実は1970年代の駆け出しの頃に出会い、ある作品で一緒に仕事をしたこともあったそうです。それが明かされたのが誌面上だったので、担当編集は「え? そんなことお二人から聞いてないんですけど」と原稿を読みながら驚いてしまったのでした。そんな関係でしたのなら、連載終了を機会にお二人の対談をしてみたらどうでしょうか? と持ちかけてみたところ、お二人から快諾をいただき、この特別企画が実現しました。(2018年6月25日収録)
お二人は年齢はどちらが上なんでしょうか?
板谷 ぼくは1951年生まれで67歳。
髙間 僕は1949年生まれだから、2歳上ですね。
髙間さんの初期の歴史については、今度映画が公開されるので、それを見てもらうといいですね。(1969 年の若松プロダクションのことを女性助監督の目から描いた映画「止められるか、俺たちを」のこと。2018年10月公開予定。監督:白石和彌、主演:門脇麦、井浦新、脚本:井上淳一、撮影:辻智彦)
髙間 お恥ずかしい話ですが。
その映画には髙間さん役の人が出てくるんですか?
髙間 そうなんです。若松プロの1969年ごろにいた人たちが実名で出てくるんです。僕が撮影助手で出てくるという。
それは業界に入った最初期ということですか?
髙間 そうそう。大学生の頃からアルバイトを始めて映画研究会にいたら、福間健二(後に詩人、翻訳家、映画評論家、映画監督)がいて、“ダブルけんじ”と言われていて。彼は高校生の頃から若松孝二に心酔していて、若松プロに出入りしていて、ちょうど福間が脚本書いて持ち込んだら、「じゃあ、お前主役やれと言われて」、一緒に行った僕のほうは、「撮影助手やれ」ということで。
大学生の頃ですか?
髙間 そう。大学3年、1969年かな。
髙間賢治さん
バイトから撮影現場へ
髙間さんは芸術系とか映画関係の学校ではなくて、普通の大学なんですよね。
髙間 僕は建築設計とかやりたいなあと思っていたんだけど、高校の時に文化系、理科系って分けるじゃない? そのときに化学のテストが0点でさ。文化系しか行けなくて。文化系っていったって何をやるかなと思って。うちは家具の工場をやってたから、長男だし、将来後を継がなけきゃいけないから、経済でもやっておくかというくらいなもので経済学部に入って。そのうち転部しようと思ってたんだけど、結局工学部には空きがないと入れないということが分かって。単位は早くとってしまって、3年、4年は撮影のアルバイトばかりでしたね。後継ぎということで、就職活動もしなかった。でも家具というのは当時どんどん下降していく産業だったのね。伸びていたのは大塚家具くらいなもんで。
当時の若松プロはどこにあったんですか?
髙間 僕が最初に福間に連れられていったときは、宮益坂を上がったところに仁丹ビルがあって、その裏あたりにあった。そのころ映画でいうと「胎児が密猟する時」とかね、それはそこで撮影されたんです。でもすぐに原宿のセントラルアパートに移ってね。僕が仕事をし始めたころはそっちだった。セントラルアパートは当時錚々たるクリエイターが集まるところだったからね。
そうですね。ということは当時の日本の最先端だったんですね。その頃は板谷さんは?
板谷 僕は芸大に入りたいと思って受験したんだけど落ちて浪人して。予備校の講師に「造形大学というのがあって、そこに写真とか映像の科目があって、そこはどう?」って言われて。1年浪人しているから、造形大学を受けたら受かったんですよ。ぼくは写真学科に入ったんだけど、石元泰博さんとか、わりといい先生に恵まれて。カメラは大学に入ってから、ニコンFを買ってもらった。レンズは50mm1本。最初僕は、写真のように機械を使って作る芸術というのは一段下だと思っていたんですよ。本当に才能があれば、油絵とか彫刻とかファインアートでやっていけるはずだと。ただ、自分にはそこまでの才能もないし、デザインはどうだろうと思っていた。その当時は横尾忠則さんが出て来たころで、デザインが単なる商業的なものではなくて、表現になっていて、そういうものに憧れていたから。でも、写真は頭になかったんですよね。石元先生に課題を出されて撮っていくと、コテンパンに言われるんですよね。「何でそんなことを言われるんだろう」と思ったんです。だって、あるものを撮ったんだから、それをどうこう言われても、俺のせいじゃないよ、という感じがあるじゃないですか? それなのに石元先生は、こだわりの強い人だから、微に入り細に入り、あれこれと言うんですよ。たかが1枚の写真にこれだけいろんなことが言えるって、一体この人は何なんだと思った(笑)。悔しいからこちらも必死にやるじゃないですか。幸いなことに、映像専攻はできたばかりで30人くらいしかいないんですよ。そのうち映画志望もいるから、だから石元先生のゼミは10人くらい。一年生のときから、一流の先生が本気で相手をしてくれたということが、自分のためにはなりましたね。
髙間 今考えると贅沢な話だねえ。
板谷 そうなんですよ。当時は規則もゆるかったから、暗室に入って夜通し写真を焼いても、守衛の人もとがめないし、やりたい放題だった。それで写真が面白くなったんですよね。そのうちアルバイトで撮影助手の仕事が来て。16ミリフィルムでお祭りを撮ってるTBS関連のプロダクションがあって、そこにアルバイトに行ったんですよ。ただ、撮影助手といっても、運転手、荷物運びのようなもの。そこでカメラマンをやっている人がかなり年配の世代でおもしろい人で、フィルムカメラマンっておもしろいんだなと思った記憶はあった。でもそれを仕事にしようとは思ってなかったですね。当時は単純にアルバイトのつもりで。ただものすごく忙しくて、就職するもなにも、卒業式のときには地方ロケに行ってたくらいだから(笑)。就職試験も受けなかったし、居心地がいいほうにずるずる行ってしまった感じですね。
板谷秀彰さん
お二人とも似たような感じで現場に入っていますけど、高間さんが最初が映画で、板谷さんは最初がテレビ関係だったというのがその後の運命を決めていますか?
板谷 でもぼくは大泉の東映でもやっていて、映画関係にも触れていたんです。当時、高間さんにも会ってますし。僕も映画がすごくやりたかったんですよ。映画をやるのが夢。でも、もう当時の撮影所には夢がなかったですね。東映にいた20代前半のころ、撮影チーフをやっていた30代後半の人が、ボロボロのカローラ、それも走るんだろうか、これは? という車に乗ってきていて。この環境にこのままいてはダメだなと思って。僕は高間さんみたいにねばれなかった。
髙間 閉鎖的で徒弟制度もあって、みたいな世界だからね。
その当時、お二人は出会っているんですか?
髙間・板谷 うーん、作品はなんだっけ?
板谷 なんかで助手させてもらいましたよね。「月山」(村野鐵太郎監督・1979年)が終わったころかな。
高間 「月山」が終わって、1979年に仙台で「さよならの日々」という自主映画を撮るときに板谷さんに助手やってくれないかと声をかけて、でも都合が悪いって断られたんだよね。でも声をかけたということはすでに知ってたということだから、その前にきっと一緒に仕事してるんだよね。
板谷 やってますよ、小さい作品を。
海外ロケと機材のこと
板谷さんはその後テレビの世界に行くわけですが。
板谷 テレビしかないんですよね。ラッキーなことに1980年代になって、ドキュメンタリーとか海外の取材ものは、お金が出るようになった。ついてたなあと思いますね。
髙間 僕も最初に海外ロケに行ったのは、テレビの取材番組。企業を2社ずつ取材して、別の人がスタジオで出演レポーターのト
当時のテレビと映画というのは現場はそれほど離れてなかったんですか?
髙間 東映にも大映にも映画部とテレビ部があって、映画を撮れなくなった人がテレビにいくという傾向があった。テレビの世界って若い人がいるのかと思ったら、結構年寄りがいて、テレビだったら早くカメラマンになれるかと思ったら、テレビのほうが年取った人が50歳くらいで助手をやっていて、カメラマンにもなれないんだけど、母親をみなきゃいけないから、助手をやってるんだという人もいましたよ。
テレビロケといっても16ミリを回していたんですか?
髙間 当時はテレビドラマといっても、ポータブルのビデオカメラがなかったから、ロケは国際放映が下請けして、16ミリで刑事ドラマを撮っているカメラマンが16ミリを持って行くんですよ。TBSのスタジオのなかではテレビカメラが回っていましたね。
板谷 映画というのは、もともと撮影所があって、撮影部があって、昔からカメラマンを養成するシステムがあったと思うんですよ。でもテレビはまったくなかったから、フィルム経験者のカメラマンを使うしかなかった。映画を撮っている人は、テレビはあまりやりたがらなかった。必然的に盛りを過ぎた人がやっていた。ぼくが入り込んだドキュメンタリーとか海外取材ものの現場も、そういうベテランの人たちは海外ロケというと「日本食はあるの?」というように抵抗を示す人が多かったから、ぼくみたいなのが重宝されたんです。
当時のビデオロケの機材はどんな感じだったのですか?
板谷 1インチ、背負子でしたね。カメラとカメラのバッテリーが別でしたから、カメラマンとバッテリーで2人、VTRが1人、あとはVEで合計4人。バッテリーは1時間ももたない。現場に行くと最初にコンセント探して、まず充電してという感じですよ。
髙間 最初のビデオの仕事は、鳳蘭と藤本義一の対談だったと思うけど、宝塚で、3/4(しぶさん)か1インチ、ポータブルVTRで収録した。バッテリーは自分で担いだよ、たしか。
板谷 3/4インチになってはじめて 2人体制でロケができるようになったんですよ。カメラマンはカメラがわりと小さいものが出てきてまだ良かったですけど、海外ロケなんかは、VE 1人で音も録って、ミキサーもデッキも持ってたから大変でしたね。
髙間 オーストラリアに一緒にいったVEはベッドに寝た形跡がなかったね。
板谷 昔は海外ロケにVEさんは半田ゴテとか持って行ってた。
髙間 ヨーロッパで200Vなのにそのまま突っ込んでボッと煙があがって壊れちゃうとか、あったね。コンセントにさそうとおもったら、形が違うじゃないかと。世界中同じコンセントだと思ってたからね。
板谷 今の僕らの仕事からすると、特にVEとか音声の人たちの仕事はかなり違いますよ。
髙間 16ミリだと今度はフィルムが重くて、2ケースとか持ち上がらないんだよね。これがなけりゃどんなに便利だろうなと思ったよ。
板谷 飛行機ではX線のかぶりが大問題で、僕は事故はなかったけど、当時たまにあった。箱に鉛のフィルムを貼るんだけど、そうするとまた重いんですよ。
2004年のバリカムが最初だった
劇場公開映画というのは35ミリだったんですか?
髙間 映画は35ミリって決まってたの。板谷さんに一緒にやろうと声をかけた映画も予算3000万円だったけど、35ミリで撮るのは決まってた。というのも映画館は35ミリ上映しかないから。16ミリで撮ると、35ミリにブロウアップするときの光学費用が莫大なんで、35ミリでケチケチ撮っていたほうが安いんですよ。映画の場合は、カメラはアリフレックス一択で、当時はBL1型かな。その後、BL2、3、4、535というふうに進化していくんだけど。
板谷 ハリウッド映画の本流はパナフレックスですけど、日本で当時パナフレックスを使えたのは、ほとんどないですよね。
髙間さんはわりと早くデジタルで映画を撮り始めたんですよね。
髙間 13年前に「ライフ・オン・ザ・ロングボード」(喜多一郎監督/2005年)を撮ったのが最後で、それ以降はどうしても35ミリのフィルムじゃないととこだわる監督以外は、デジタルになりましたね。
一番最初のデジタル撮影の映画は?
髙間 「ロード88 出会い路、四国へ」(中村幻児監督/2004年)ですね。あれはバリカム(パナソニック)で撮った。ただ当時はフルHDの1080ではなくて720。阪本善尚さんが作ったフィルムルックっていうのがあって、それでやったから、わりとビデオっぽくなく仕上がった。最終的にはフィルム仕上げですけどね。
板谷 抵抗はありました?
髙間 それほどなかったね。フィルムルックで撮れるということもあって。しかも、その前に低予算のものはもっと小さいカメラ、たとえばパナソニックのDVX100とかで撮ってたから。
髙間さんが自前でカメラを買われたはそのDVX100ですか?
髙間 そうだね。HDじゃなくて、SDの4:3。DVX100は40万円くらいだったかな。それで自主映画を撮ってたのかな。それでたとえば、「ホーリーランド」という、金子修介さんとその弟子たちが監督する連続ドラマを撮った。アクションシーンはスローをやりたいから16ミリで撮影したいと言うんだけど、そんな予算はない。だから、ドラマ部分はDVX100、スローだけ16ミリでやろうと提案した。色を合わせるのに苦労しましたね。
「アイデン&ティティ」という映画の冒頭で11人のミュージシャ
そのあとは、カメラもHDになって、だんだんいいものになってきて、今はキヤノンのEOS C100を2台。それから僕の助手がREDを何台も買って、1台放出するというので、安く買ったりして。今は4、5台カメラを持ってます。
一台のカメラだけで番組を作ることがなくなった
板谷さんのほうは、連載でも自分のカメラを買ったことがないということを書かれていましたが。
板谷 僕の場合は、ビデオの歴史そのものだからね。ビデオの場合は5年もたない。今年に入ってからは、HDの仕事はしていないくて4K。それくらい流れが早いです。それまではHDCAMテープだったけど、ここ4年はテープを触ってないですね。
メインのカメラは4K納品であれば、4K/60pじゃないとダメという縛りがあって、局とかプロダクションが持ってくるけど、それ以外、サブに使うカメラについては縛りは何もない。だから、GoProとOsmoは自分が持っていくので、サブだけは自分の所有ですね。さらにデジタル一眼、ドローンと、メインのカメラ以外のカメラが増えている状況です。昔はカメラは1台で撮るのが普通で、複数台使うのは特殊な事情でしたけど、今はカメラ1台で番組を作るということはまずない。
メインのカメラはショルダーですか?
板谷 そうですね、そこは昔から変わらない。ビデオグラファーだとデジタル一眼をジンバルに載せて作品を創っている人が多いけど、さすがにそういうスタイルはないですね。というのも、テレビのドキュメンタリーの場合、音の問題があるんです。小さいカメラの問題ってバッテリーと音で、これを犠牲にしないとカメラが小さくならないんですよね。GH5とかαとかミラーレスカメラの動画性能はものすごくいいんだけど、音を録ろうとすると、いろいろくっつけていくことになって。だったら、普通のカメラを担いで撮ったほうが楽ということになるんです。
撮影の現場はテレビの映画も、ディレクターは若い人が多いですが、撮影はベテランが多いですね。どうしてなんでしょう?
板谷 たしかに若い人は少ないですね。
髙間 カメラマンは経験が大きいからね。だんだん年齢が上がっていくのでは? ぼくなんかもう40年やっているわけじゃない。それ以上の本数の映画をやっているわけで、たとえば三谷幸喜さんとやった現場でも、三谷さんがちょっと説明しただけで、ぼくがすぐ理解するもんだから「こんな説明でよく分かりますね」と不思議がってた。だって何本もやっていると、全然的外れなことってなくて、どこかの引き出しに入っているわけで、監督が何を言いたいのかはすぐに分かる。
板谷 カメラマンというのは、ゼロからものを創っていくクリエイターじゃなくって、条件を組み合わせて最善なものを作っていく人だから。たとえば何もない五線譜に音符を置いていけっていうようなことを言われれたら、カメラマンはちょっと無理なんじゃないかな。ある程度、条件を言ってくれれば、これで判断すればいいんだなということが分かる。
予算のことも大きくて、この予算のなかでどういう照明を持っていくべきか、他にどんな手を使ったらいいのか、少ない予算でみんなが幸せになるように考えるというのがカメラマンの役割かもしれない。
スケジュールにしても、スタッフの体力を考えて判断するっていうことはよくある。撮影しているのは生身の人間だから、疲れれば仕事の質は落ちるし、それは精神論では解決しないんですよね。撮影は事故につながる危険な要素もあるし。
撮っている状況と写っているものの乖離
髙間 経験がないときは、自分が危険な状態にあって撮影しているときは、危険で危なっかしい表現の映像が撮れていると思ってしまうことがある。
板谷 そう、酔ってしまうんですよ。
髙間 できあがって見てみると、その時の状況の雰囲気はまったく映像に反映されてなくて「なんでこんな画を撮ったんだろう」みたいなね。つまり、撮っている状況と写っているものの乖離ね。そういうことの繰り返しによって、現場でどう撮ったらいいのか判断できるようになる。
たとえば最初の映画の「月山」で吹雪のなかで歩いてくるシーンを撮って、本当に寒くて雪のなかで撮ったんけど、画をみたら、たんなるぽやーんとした映像で、白に白だから雪が映らない(笑)。そういう経験をして行くことの繰り返しですね。
この素材はもう撮れたと思わないこと
ドキュメンタリーでは経験の積み重ねで得たことってどんなことがありますか?
板谷 ドキュメンタリーは、いろいろな素材を撮っていって、それが最終的に作品になっていくわけですが、「この素材はもう撮れた!」と思うと、もうそれ以上撮らないんですよ。だから、「これもあれも撮れていない」という気持ちでいたほうが、翌日以降にいいものが撮れることがある。
1日のスケジュールが終わって、スタッフで飲んでいるときに、「あれはダメなんじゃない?」「もう1回撮り直したほうがいいんじゃない?」と言うことがよくある。
それは板谷さんがディレクターに言うんですか?
板谷 逆の場合もありますね。そこから議論になって、なんでダメなのかという話になる。たとえば田舎に行って、地元のおじさんにインタビューしたとして、「あの聞き方はよくない。こういうふうに聞いたほうがよかったんじゃなない? 」と。そこで言い争いになるけど、そういうやりとりをすることで、撮れる素材が良くなっていくことがあるんです。
髙間 それで、翌日、もう1回おじさんのとこに行くわけ?
板谷 そういうときもありますね。別の人に同じケースで聞く場合に、それを反映して工夫するということもあります。
ドキュメンタリーの場合、ぶっつけ本番だから、ぼくがこっちから撮りたくても、ディレクターがこっちから話していたら、その場所に行けないという物理的なこともありますから。後から分かることが多いんですが、「この話の内容であれば、こっちをバックにしたほうが絶対いいよ」とか。たとえばその人が「この村は…」と話しているときに、背景に村が見えていたほうがいい、というようなことがありますよね。映像としては、ピントが合っていて、絞りも構図も的確で合格だったとしても、もっと良い映像はあるんじゃないかということは常に考えるべきだと思いますね。
髙間 劇映画ではきちんと撮れたというカットはそこをリテイクすることはまずないんだけど、「ライフ・オン・ザ・ロングボード」で夕陽がきれいな浜があって、そこで主人公の大杉漣さんが娘と語るシーンを撮ろうということになったんだけど、その日は曇っていてきれいな夕陽にならなかったんですよ。で、そのあと、「日を改めてもう一度、撮らせてください」と僕が言ったら、大杉さんも「いいよ」と言ってくれた。でもね、その晩、大杉さんは「高間さんはああ言っているけど、おれはやりたくない」と監督に言ったんだよね。つまり、重いシーンだからもう二度とやりたくないと。
板谷 芝居をやる側の気持ちとしては、それは分かる気がしますね。ビジュアルの問題なのか、芝居の問題なのかということですね。カメラマンはビジュアルを重視したくなるけど。
髙間 そのシーンは後から夕陽に見えるようにカラコレした。いい景色によりかからなくても済むことのほうが作品としては良かったかもしれない。景色がいいねということではいい映画にならないですから。
音にも深度がある
板谷 僕がよく一緒に組んでいる音声さんがいるんだけど、彼が、映像で被写界深度を考えるように音にも深度があるって言うんです。バックが違うと音が違うし、そのバックの音をどれくらい入れ込むかという計算があると。だから音のことも考えてカメラ位置と方向を考えろと言ってくるんです。たとえば渋谷で駅をバックにして語るのと、スクランブル交差点をバックにして語るのとでは、音って全然違いますよね。ドキュメンタリーでの音の表現とはそこだろう、と。あとは「交差点で人が通ったり、車が通るのをうるさく感じさせないのは俺の腕だ」っていうわけ。
つまりカメラマンが背景を考えるのと同じだということですね。ピント、露出が合っているノーマルの画の一つの上の世界があるとすると、音も単に声がきちんと録れているだけでなくて、背景との深度を考えた音というのがあるらしい。たしかに彼が録った音は違うんですよね。
髙間 劇映画でも撮影と録音部の関係というのはあるよ。録音部がかわいそうだなと思うのは、カメラ2台で、引きと寄りを同時に撮るとき。役者はみんなピンマイクを隠しているけど、ガンマイクでも録ってるから。引きの絵があるとマイクを差し込めないんだよね。だから、後で「寄り」だけも撮るからといって納得してもらうけどね。
現場で「寄り」と「引き」を同時に撮ったほうがいいのか、「寄り」と「寄り」を同時に撮ったほうがいいのかは、判断のしどころだね。そうやって音の問題も考えてカットを作って行く。
でも、感情的な芝居で何回もというのは役者がかわいそうだから、少ない回数でやりたいんです。たとえば会話するときに片方だけ撮っていく場合、セリフの食い合いができなくなる。録音部が後で編集できなくなるから困るって言うの。僕はそのほうがリアルだから食い合うようにやってくれと言うんだけど。昔の日本映画のように台本に監督が線を引いて、このカットはロングでとか、全部指示していって、それしか撮らないとすると、芝居の感情の流れが続かないでしょう。全部、役者が作っていかなければならないから、芝居が変わってしまったり、落ち着いた芝居になっちゃう。同時に回しても、音が1本であればかまわないけわけで、そういう撮り方をしたいんですよね。
撮影と音の関係というのは、ドキュメンタリーでも劇映画でも深いものがありますね。
興味深い話になってきたところで、残念ながら会議室が時間切れ。このあとは近くの居酒屋に場所を移して二次会になったのでした。申し訳ありませんが、そちらはオフレコでお願いします。
髙間さん、板谷さん、長い間の連載、本当にお疲れ様でした! 連載は終わりましたが、お二人とも現役のカメラマン。ぜひ呼んでいただけるのなら、撮影現場にお邪魔したいと思います。
【関連情報】
板谷さんの連載をまとめた本がこちら
映像撮影ワークショップ
B5変型判 192ページ
定価:本体2,000円+税
ISBN978-4-7683-0503-4