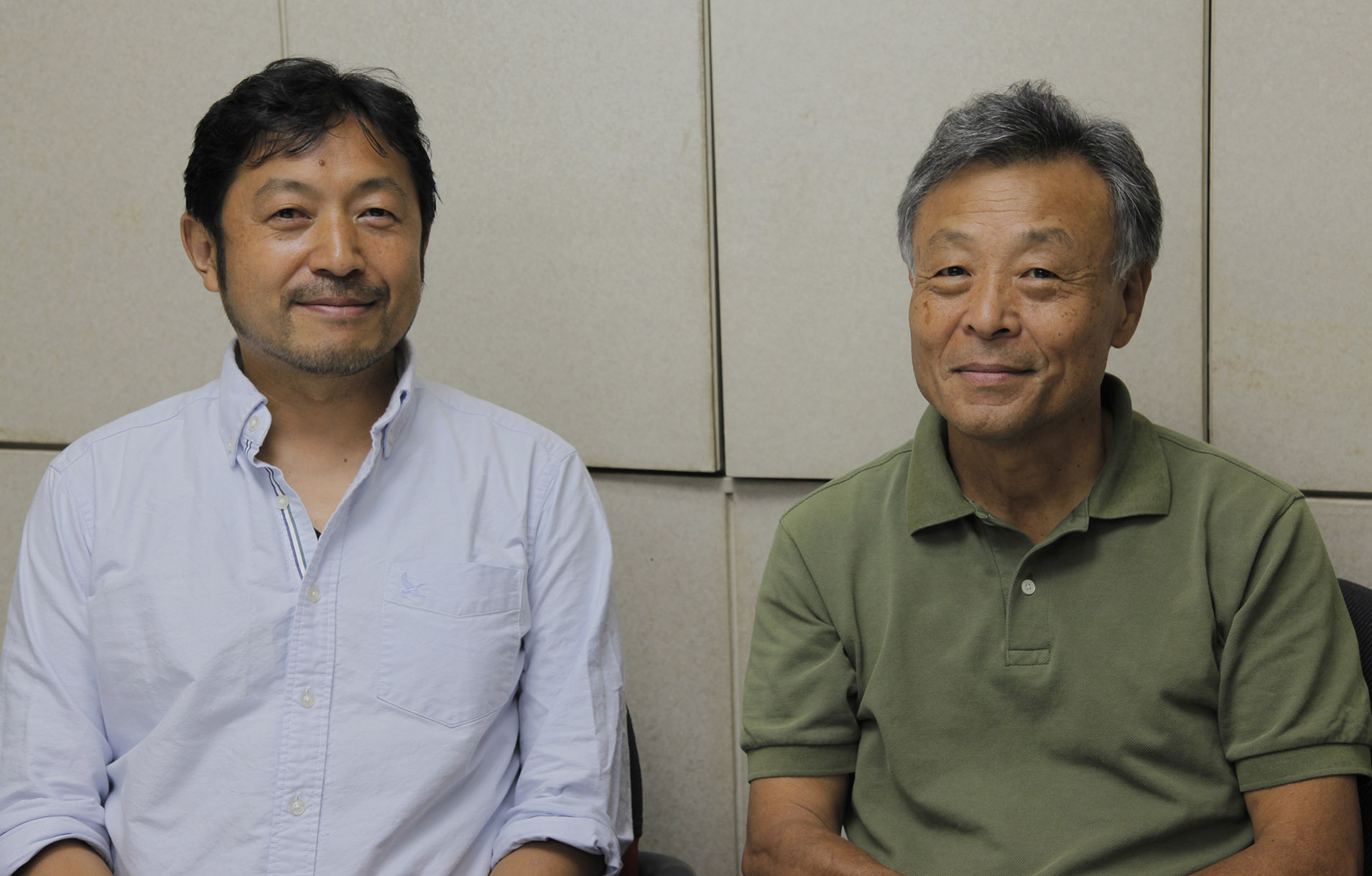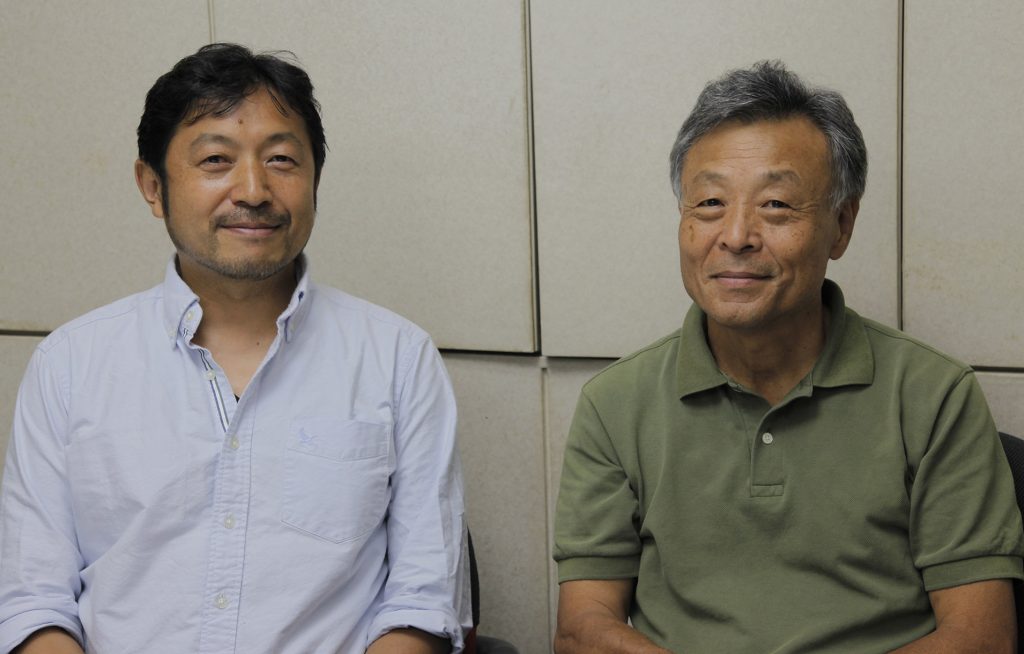ビデオサロン誌上で2011年10月号から2018年まで続いてきた連載「撮影監督 髙間賢治のデジタル映画制作記」。同じく長期連載してきたドキュメンタリーカメラマン板谷秀彰さんとの対談を7月に公開しましたが、その続編とも言うべき対談第2弾。髙間さんの撮影人生のスタートは1969年の若松プロで撮影助手としてでしたが、その頃の若松プロの制作現場を描いた映画『止められるか、俺たちを』が10月に公開されます。その撮影を担当した辻智彦カメラマンとの対談をお届けします。(2018年8月14日収録)
髙間さん(右)と辻智彦さん。
若松孝二監督と髙間さん、辻さんの関係
お二人はご一緒の撮影現場を経験されたことがあるんですか?
辻 『ワイルドライフ』というテレビドラマがあって、そのときに髙間さんから一度Bカメとして誘っていただいたことはあるのですが、スケジュールが合わなくて実現しませんでした。
髙間 誘ったんだっけ(笑)。
辻 若松プロの『17歳の風景』(2005年)という映画で若松孝二監督と初めて組んでやるというときに、僕はそれまでドキュメンタリーをやってきて劇映画は初めてでよく分からなかったので、撮影監督協会の大先輩の髙間さんは若松プロ出身ということはみなさん周知の事実なので、無謀にも電話したんです。「こんど若松孝二監督の映画をやることになりまして」と言ったら、髙間さんが一言「ご愁傷さまです」と(笑)。
高間 そうなんだよね、みんな不幸になるんだよね(笑)。若松さんがカメラマンを褒めたことはないんだよね。でも、辻さんだけは褒めて、それから最後まで辻さんを使い続けたね。そもそもなんで若松さんに呼ばれたの?
辻 その前に、『日本心中』というドキュメンタリーの映画があったんですよ。それを映画館で上映したとき、監督は大浦信行さんという美術家の方で、映画界では名前が知られていなかったので、有名人を呼んでトークイベントをやろうということになって、そのゲストの一人として若松孝二という名前が出たんです。
高間 へえ、それで呼んだの?
辻 呼んだんですよ。ゲストで来てくださって、「君がカメラマンか、若いなあ」みたいな調子で。大浦監督と若松監督のトークの時に、壇上で突然、若松監督が「次に『17歳の風景』という少年が旅をする映画を撮ろうと思うんだけど、今日上映した映画のカメラマンがその映画の撮影をすることになっている」といきなり言われたのがきっかけですね。
髙間 若松さんらしいね。大浦さんと若松さんは知り合いだったの?
辻 知り合いではないです。事前にDVDを送ったんですけど、すぐに大浦さんのところに返事が来て、映画面白かったと言ってくれたそうなんです。
僕は学生時代から若松孝二監督の映画のファンだったんです。1960年代の映画は名画座で観て衝撃をうけて、1990年前後は『キスより簡単』とか『われに撃つ用意あり』とか、若松孝二監督の二度目の最盛期で、若松孝二ファンになったんですけど。
髙間 僕なんか一回も若松さんの作品撮ってないからね。髙間はマジックアワーとかなんとか難しいことばっかり言ってるからダメだ、って。僕は一番経済的に撮るカメラマンですよ、って言っても信用しないもん。
辻 でも僕には「うちから出たカメラマンはすごいやつばっかりなんだよ」と言ってましたよ。「髙間ってやつは、撮影監督システムを日本に持ち込んだんだ」と。それは僕に対する暗黙のプレッシャーだったと思うのですが。
髙間 一度ね、清水さんというプロデューサーに若松さんとやりたいですか? と聞かれて、やりたいですよ、と言ったらね、谷崎の『瘋癲老人日記』だっけ? 撮ることになって、その年の新年会にお邪魔したら、「いやーまいったなあ」と若松さんが買い物から帰ってきて、テレビみたら、奥山(和由氏/松竹のプロデューサー)さんが失脚したというニュースが流れていて。それでダメになっちゃったんだよね。
辻 もしその話が続いてたら髙間さんが撮る予定だったんですか?
髙間 でも、僕が入ろうとしたときには照明部が先に決まっていて、もしやるとなったら、そこでひっかかって、多分すんなりはいかなかったと思う。
『17歳の風景』で突然、辻さんをスカウトしたのはどういうことだったのでしょうか?
髙間 若松さんとしては、決まりきったアングルで撮るカメラマンにはもう飽き飽きしてたんだよ。でも自分の言うことは聞かせたい。鈴木達夫カメラマンは尊敬してたと思うけど、「長田(勇市カメラマン)は全然言うこと聞かないんだ」って言ってたし、田中一成カメラマンのことも煙たがってたし。
そうそうたるカメラマンが若松プロ出身だったんですね。
髙間 そこから出たというか、みんなちょっと寄り道したという感じだね。
辻 そうですね。ずっといるということはないんですね。
髙間 僕はそこの学生アルバイトから始まっているから出身といえば出身だけどね。
辻 髙間さんはどれくらいまでいらしたんですか? 『天使の恍惚』(1972年)まで?
髙間 そうかなあ。そのちょっと後くらいまでかなあ。
辻 若松プロは所属するわけではなく、仕事があれば集まるという感じでしょうけど。
そのあと髙間さんが『月山」(1979年)でデビューするまではどうされていたんですか?
髙間 イラストレーターの林静一が若松プロで1本撮るというとき(『夜にほほよせ』)、林さんがカメラマンは鈴木達夫さんにしてくれということだったけど、「そんな高いのはダメだ、おれの友達にいいのがいるから」ということで吉岡康弘さんを紹介して。その映画では僕は吉岡さんについて助手をやったのね。それでしばらくして、吉岡さんが初台から用賀に引っ越すときに、「まだ部屋があいてるよ」というので、僕も引っ越して吉岡さんの個人的な助手のようなかたちになった。そしたら、若松さんが「あいつはもう吉岡さんの助手だからうちでは使いにくいよ」ということになって。そのあと若松プロでは、芦澤(明子)さんとかも伊東英男さんの助手をやるようになったんじゃないかな。
監督は雑だけど画は端正だった。人物がもう少し飛び出してきていた
辻 伊東英男さんというのはどういうカメラマンだったんですか?
髙間 東京映画出身で、おとなしい人でね。若松さんが「伊東さん、カメラはここ」と言えば「はい」と言ってそこから撮る。若松さんの場合、カット割りをこまかく説明するタイプじゃないじゃない。言われるがまま、何も言わずにカメラを動かしている感じでしたね。レンズは50、70、100mmで大半が50mm、アップが70mm。おとなしい端正な画だったね。
辻 若松監督と一緒にやって分かったんですけど、ものすごく雑な人ですよね。でもあの当時の映画って雑だけど、画はわりと端正じゃないですか? だから伊東さんとどうやって撮ってたんだろうと思って。
髙間 その端正なのは伊東さんの性格じゃないかな。
辻 『17歳の風景』をやったあとに昔の若松孝二監督の映画を見直したんですよ。『17歳の風景』はわりと風景と少年がとけあったりしてるけど、ちょっと情感に流れすぎていた。つまり人が迫って来ていないと思ったんです。昔の若松監督の映画をみると、人物がもう少し飛び出してくる感じを受けます。ドラマ作りの違いもあるんですけど。それで反省して、『連合赤軍』(『実録・実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』2007年)では、迫っていくようなカメラに変えたんです。その違いについては若松監督は何も言わなかったですけどね。
髙間 当時は、狭い部屋でしか撮れないけど壁を抜くわけにもいかないから、わりと50mmで撮っていくということがあって、迫ってくるように見えるのは物理的な問題だったような気もするけどねえ。どんと引いて望遠で撮るということでもないし。しかもそのときのシネスコだから、人物を真ん中におくと、ちょっと前に出てくるように見えるのかもしれないね。
辻 そういうこともあるかもしれませんね。
髙間 驚いたのは、伊東さんはカメラマンとしてのNGがなかったこと。カメラの操作を失敗したからもう1回というのはまったくなかった。だから僕はそういうカメラマンのNGがあるというを知らなかった。他のカメラマンの現場にいったら、カメラマンがもう1回と言うからびっくりしてさ、こっちに落ち度があったかなあと思って「何が悪いんですか、どこを改善しますか?」と聞いたら、カメラマンがむすっとしてさ、おれがもう1回て言ったら、もう1回やればいいんだよと。カメラマンとして失敗することがあるってことを知らなかった。
でも、伊東さんは何にも教えてくれなかったから、カメラの掃除の仕方、レンズの掃除の仕方、何も知らなかった。よそのカメラマンについて初めて、アパーチャーにゴミがついていないか見るということを知ったくらいで。
カメラマンとしてのデビューとは
辻 髙間さんがデビュー作である『月山』を撮る経緯というのは?
髙間 よくあるパターンですよ。助手としてついているカメラマンが怪我したりとか都合がつかなくて代わりにやるとか。伊東さん自身も、昔の東京映画で師匠の三浦光雄さんが『猫と庄造と二人のをんな』を撮っているときに亡くなって、その助手だった伊東さんがカメラマンになった。
辻 三浦さんと言えば、若松監督は賞を全然喜ばない人なんですけど、僕が三浦賞を取った時は喜んで「この三浦賞というのはな、三浦光雄というすごいカメラマンがいて、その人を記念して作った賞で、三浦さんという人は、伊東さんの師匠にあたるんだ」と言われていた。
髙間 その三浦さんが亡くなって伊東さんがカメラマンをやるようになった。僕も吉岡さんについて、『鬼の詩』(村野鐵太郎監督)で助手をやって、そのつぎ何をやるの? と吉岡さんが村野さんに聞いたら、『月山』をやりたいと。氏子総代と吉岡さんが知り合いだったから口をきいてあげて。ところが吉岡さんが肝炎になってしまって、プロダクションのほうでは別のカメラマンをスタンバイしたんだけど、村野監督は僕を使ってくれた。監督と脚本家とシナリオハンティングに行ったときにも僕も同行したということもあって、カメラマンは髙間だろうということで、デビューしたんだよね。でも現場では四面楚歌ですよ。
辻 大変だったですか。
髙間 大変ですよ。秋の撮影が2週間くらい。帰ってきて冬の撮影があって、それから正月開け、5月に実景をとりに行ったり。最後のほうは監督と僕ともう一人、編集の人と四人で車で行ったり。
辻 現場はうまくいったんですか?
髙間 撮影に入る前に吉岡さんが言うんだよね、一番の敵は監督だぞって。その通りだったんだけどさ(笑)。村野監督は怒鳴っていることをエネルギーにしているような人だから。でも、まだそのときは助監督をいじめる方向にむかったんだけど、次の『国東物語』では僕をいじめる矛先にして。カメラマンいじめてどうするんだと思うんだけど、それで地獄の撮影になって。
当時は陰険な現場が多かったし、撮影部と照明部があって、カメラマンがやりたい照明ができない現場の在り方に疑問を感じていた。それはその前の若松プロでも同じだけど。アメリカ映画をみると、照明していないようだけど、しないとこうは写らないようなあという照明がしたいと思っていた。そのころからアメリカの撮影現場にいってみたいという気持ちがあったんだよね。
辻 若松プロでの磯貝(一)さん(照明)と伊東さん(撮影)の関係は?
髙間 そこはおたがい何も言わなかったね。あるシーンで背景に階段があるから照明部はそっちにも当てようとする。若松さんが「そんなところ当てなくていいんだよ」と怒鳴る。たしかに、そこは本来見せたくないんだから当てなくてもいい。そのことを若松さんも短気だからうまく伝えられない。このシーンでは一つの抽象的な空間として撮りたいんだから、その階段は見せなくていいでしょ、そういう意思疎通が現場でできていなかった。
辻 若松さんはそういう説明はできない人ですからね(笑)。
『止められるか、俺たちを』が生まれたきっかけは髙間さんだった
その当時の若松プロの制作現場を描いた『止められか、俺たちを』が生まれるきっかけを教えてください。
辻 最初のきっかけは実は髙間さんなんですよ。若松孝二生誕80年祭(2016年)というのがあって、そのあと飲んでいるときに、髙間さんがめぐみさんの話をして、白石和彌監督に「めぐみのしゃしん」という写真集を渡したんです。白石さんが若松プロに入ったのは90年代半ばですけど、そのころ若松プロにはゲバラの写真とめぐみさんの写真が並んであって、めぐみさんの存在自体は僕らも知っていたのですが、何をしていた人なのか、どういう人なのかも全く知らなかった。
白石さんにとっては、若松プロが全盛をきわめた1960年代、70年代というのは神話化されているんだけど、それを具体化する手がかりみたいなものがあの写真集だったんです。
その写真集というのは高間さんが個人的に作られたものですか?
髙間 そう、めぐみが死んでね、何か残そうということで。当時、僕は写真も撮っていて、そのネガが手元にあったから思い出に残るものはできないかなと。秋山道男が中野本町で事務所をもっていて、その下が印刷屋だったからそこで刷ってもらった。500部、20万円くらいで作ったかな。
辻 その写真集にあるめぐみさんが今回の映画のイメージになっていますね。
髙間 脚本をかいた井上淳一が当時のことをインタビューしたいというから。あまり僕がさわりたくないところばっかり突っ込んでくるけど、もう逃げるわけにはいかないだろうと思ってさ。腹をくくって恥さらしをしてしまったということですね。
辻 そんな感じで白石監督と井上さんとか何人かでインタビューに行って、それで当時の若松プロがどんな感じだったのか浮き彫りになってきた。
実際に試写でごらんになって、いかがですか?
髙間 細かい点でここが違う、あそこが違うはあるけど、当時のことを再現できるわけでもないし。でもそういう点を省いていくと、僕がいた当時、秋山道男、小水一男(ガイラ)がいなくなっていった。そのことは当時、あまり深く考えてなかったんだけど、今回の映画をみて、なるほどそういうことだったのか、と分かった。その点については、ガイラも道男ちゃんもインタビューでは何もしゃべってなかった。なぜ若松プロを離れていったのかというところは脚本の井上さんの創作の部分。でも、それは僕としてはすごくよくわ分かった。
懐かしいと思うと同時に、吉積めぐみという人物がいたんだということが、一つの映画として残るというのは嬉しいなと思った。
当時の空気を我々は知らないのですが、この映画はそのあたりのニュアンスは近いものがありますか?
髙間 それは難しいよね、俳優も現代の俳優だし。今はそんなに破綻しているような人、いないじゃないですか? 足立さん、ガイラ、沖島さん、道男、みんなさあ、外見もそうだけど性格もハチャメチャなんだよ。そのなかで僕だけが普通の人、それが若松プロだった。そのハチャメチャなところは随分マイルドになっている。
辻 そういうハチャメチャに違う人が集まる磁場があったというのが面白いと思います。若松さんは昔からあんな感じですね。難しいことは言わないし、何を言っているか分からないときもあるし。でもそういうところに人が集まって来る。今回の映画の脚本もそうですけど、髙間さんが普通の人という立ち位置で描かれていますが、逆に居心地の悪さみたいなものはあったんですか?
髙間 すごく珍しい世界を見ていたという感じだね。こういう世界もあるんだという。
辻 ぼくは昔の若松プロは知らないけれど、当時の方々から、「お前らがもっと若ちゃんを突っつかないからダメだ」と言われていたんですが、当時は若松監督も30代で若かったし、まわりも3、4歳しか違わなかったから兄貴と弟くらいだったと思うんです。だから若者集団で映画を作っていたという感じ。自由さがあった。僕が関わったときは、すでに若松監督は67歳だから30歳以上違うんです。当然関係性は変わってくるんですよね。でも、若松監督の立場からすると、ずっと同じ気持ちで、若者達と一緒に映画を作ってきたという言い方はできると思うんです。
髙間 若松さんも同じことを繰り返しやれているわけじゃなくて、どんどん変転していっているからね。若松さん自身はそんなに政治的でもないんだけど、足立さんがストーリーを作って政治的に傾いていって、そこから行き詰まった感があって、そこからどう脱出するかもがいていた。プロデューサーをやったり、試行錯誤した時期があった。
辻 1990年以降は一時期は松竹の奥山和由プロデューサーで、鈴木達夫さんをカメラで使って、原田芳雄さん主演の『寝盗られ宗介』(1992年)やったり。その後、僕がやり始めた頃の若松監督は原点回帰というか、自前で、雑でも、低予算でもやりたいことをやるという映画作りに戻った。
ドキュメンタリーとドラマ
辻さんは『17歳の風景』のあと若松監督とは?
辻 実は『17歳の風景』と二本撮りするような感じで、『完全なる飼育 赤い殺意』(2004年)もやれと言われて、撮ったんです。実はそれがさんざんだったんです。コンテもなく、ドラマの撮り方もわかってないのに撮影に入ってしまった。『17歳の風景』はそういうドラマの撮り方を排除するという方針だったから、よかったんですけど。照明はベテランの方をつけて、その方の照明で撮影するだけだったんですけど、撮影としてはひどいことになってしまった。それでもう若松監督とは終わりかなと思っていたんです。でも『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』(2008年)で呼ばれて。そこからは『キャタピラー』(2010年)「11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』(2012年)と若松プロでの自前の映画作りになっていき、撮影もやらせていただくことになりました。
辻さんはドキュメンタリーを志望して、現在もメインはドキュメンタリーですよね。
辻 仕事のはじめはドキュメンタリーですね。映画が好きで、日大芸術学部映画学科に入りました。学生って変なものをいろいろ見たくなるじゃないですか。普通の映画じゃないのが好きになっていった頃に、昔の若松プロの60年代の映画に出会ったんです。これはスゲーなと。ところが、あるときドキュメンタリーの小川紳介さんの映画がアテネフランセで特集上映していたことがあって、それを見てびっくり仰天したんです。監督が画面に出ているんですけど、それを撮っているカメラが宙に浮いた感じになって空が映るんです。でも監督はそこにいるんだから、このカメラワークを指示しているわけではない。そのカメラワークに驚いた。撮影はたむらまさき(田村正毅)さん。それから田村さんの撮影のものを見るようになり、ドキュメンタリーが面白いと思うようになりました。ドキュメンタリーをやるんなら、監督ではなくてカメラマンだと思ったんです。そのほうが「表現」できると思ったので。それからずっとドキュメンタリーの現場だったのですが、若松監督に出会って、偶然にも劇映画を撮ることになってしまったということですね。
劇映画は助手として入ったこともなく?
辻 そうなんです。だから最初は現場で助監督が言っている用語が分かんなかった。「ぬすむ」とか「どんでん」とか言われてもわけが分かんないから、知っているふりをして、じゃあどんでんで(笑)。
髙間さんは逆に劇映画から始まってドキュメンタリーも撮影されていますよね。
髙間 もちろんやってるよ。略歴には書いてないんだけど、たとえば羽仁進さんと、どろんこ保育園とか野良猫のドキュメンタリーとったり、的場徹さんと小児科医のドキュメンタリーとかね。アメリカの一年の研修から帰ったら、羽仁進さんと中国、モスクワにいってくれないか、と言われて。そのうち、羽仁さんがあなたと6ヶ月契約したいと言うんだよね、お金がないのに(笑)。それで茨城のどろんこ保育園のドキュメンタリーを撮影した。それはテレビでオンエアしたかな。
蛍光灯照明のきっかけはドキュメンタリーの現場だった
髙間 実は、その撮影時に色評価蛍光灯というのを50本買ってもらって、もう少し明るくしたいということで、1本のところ2本つけられるようにして蛍光灯をそれに差し替えて、ライトなしで撮影した。その色評価蛍光灯を知ったきっかけは、博多の小児科医のドキュメンタリーをやったのがきっかけでね。そこは室内は蛍光灯なんですよ。当然、外と中で色温度が違って外がピンク色になってしまう。それを直すためには、窓にグリーンのフィルターを貼ればいいんだけど、夏になると窓を開ける。どうしようか、と。秋葉原に行って探したら、これは色評価用で、グリーンが出ない蛍光灯だと言われて。ポラでテスト撮影をしてみたら、たしかにグリーンは出ないんで、これはいけるんじゃないかと。博多に行って、その蛍光灯に全部つけかえて撮影しました。それを保育園のドキュメンタリーでも大量に使いましたね。
辻 髙間さんといえば、僕が学生の頃には蛍光灯照明というイメージがあった。『1999年の夏休み』(1988年)『ビリィ★ザ★キッドの新しい夜明け』(1986年)『風の又三郎 ガラスのマント』( 1989年)とか。ちょうど「撮影監督 髙間賢治」という名前がばーんとでてきたころで。でも、その蛍光灯照明のきっかけはドキュメンタリーの撮影にあったんですね。
髙間 そういう蛍光灯が当時からあったんだよね、でも映画人は誰も知らなかった。対策方法を知らなかった。映画の照明部は蛍光灯全部消して、一から照明作っていた。当時はロケで駅の蛍光灯なんてそのままだからグリーンになっちゃて、すごいことになって。俳優のほうにはバッテリーのタングステンのライト当てるというようなことをやっていたんだから、不勉強だったよね。
辻 アメリカの撮影現場を見に行きたいと思ったのは、その照明ですか?
髙間 きっかけはね。村野鐵太郎監督がなんで行かないんだと強力にプッシュしてくれたので。アメリカンシネマトグファーという雑誌があって、それを見ていたら、カメラがあって、その横に時代劇の衣装を着た俳優がカメラの横に立ってるんだよ。カメラの横だから映らないはずなのに不思議だなと思っていた。どうやって撮っているのか現場を見てみたいという気持ちはあった。
辻 アメリカで研修を受けて一番衝撃を受けたことは?
髙間 いろいろなことが日本と正反対だと思った。日本はテストテストで役者を追い詰めてその頂点で本番をやる。アメリカは役者をリラックスさせて、テストはなくて、即本番。そのかわりそのシーンを何回も撮る。カット割りがなくてワンシーンワンカット。カメラマンがライティングやっている。カメラマンしかメーターを持っていない。絞りを決めるのはカメラマン。すべてが合理的に現場が回っていた。
辻 1年間の研修は大きかったですか?
髙間 あれがなかったら僕は今、カメラマンをやっていないね。だって人脈も何もないんだもん。ちょっと変わったカメラマンがいるぞ、ということで金子さん(金子修介監督)とかが興味をもってくれたわけで。
辻 金子監督の『1999年の夏休み』とか、『ビリィ★ザ★キッドの新しい夜明け』にしても、蛍光灯照明の印象が強いですね。
髙間 『ビリィ★ザ★キッドの新しい夜明け』はプラクティカルライティング、つまり蛍光灯があるべきところ、厨房とかボトル棚の裏とかに、色評価蛍光灯を使っただけであって、それで照明したわけではない。ただそのときに照明の安河内(央之)さんが、これからは蛍光灯でいけるぞ!と思ったらしくて、『1999年の夏休み』のときに蛍光灯を20本買って来て、これで照明するんだと言う。ぼくはそうしようと思っていたわけではない。ただうまく行ったんで、『風の又三郎』は40Wの蛍光灯を5本集めて、ベニア板の箱に入れて、それを15個くらい作ったかなあ。全部助手につくらせて、セットに並べてという感じでエスカレートしていったんですよ。
今見ても古くない、というか、今の低予算映画の撮り方そのもの(笑)
髙間さんが、『撮影監督ってなんだ?』(1992年)という本を書かれてから、日本の撮影現場は変わって来ているんでしょうか?
髙間 撮影監督システムっていうのがあるんだということが、知識としては知られるようになって、撮影も照明もひとつの仕事をしているんだから、協力しあって、どうすればいいものになるか考えていこうという傾向になったんじゃないかなあ。今は、これみよがしな照明はなくなってきて、自然になった。
僕が撮った1990年前後の映画を今見ても、全然古くなってないなあ。当時は誰もやらない先進的なことをやっている感じだった。だって当時の映画の現場で言えばもっとライト使えばいいんだからさ。ところが、僕が撮影する現場はお金がない。『ラスト・キャバレー』(金子修介監督、1988年)も、自動販売機がならんでいるから、その光を利用して撮ろうという感じだからね。
つまり、今の低予算映画の撮り方に近い?
高間 まったくそうだよな(笑)。古くないというか、今とおんなじだという。今、みんなこれやってるじゃんという(笑)。
辻 そうですね。だから、今僕たちが見ても役に立つというかね。溝口健二の『山椒大夫』(1954年)とか見ると、すごいけど絶対無理。諦めの気持ちしかない。
高間 ランプを持って歩くシーンも、今まではランプはランプ(被写体として)、ランプの光が顔にあたっている光は別に当てて作る、廊下を歩くシーンはスライダックで順番に開けて閉めて、みたいなことを照明で作っていた。だってランプの光だけじゃ映らないから。『1999年の夏休み』では、そんなのはやってられないから、ランプの光を光源にして撮ってしまおうと。
辻 でも、廊下をランプを持って歩いていくと、廊下と壁とか上下左右に光の十字架のようなものが写り込んですごい効果を出していました。
髙間 あれは計算したんじゃなくて、撮ってみたら面白かった。部屋のなかも人が動くとランプの光の影が動くじゃない。それが効果として面白い。昔は影を出しちゃいけないから、影があっても光をあてて消していたくらいで。人物の光が上にいくというのはタブーだった。考えてみたら頭より低いところに光源があれば、影は上にいくわけで。
辻 僕なんかデジタルの撮影になってから映画の撮影に入って来たので、フィルムは数回しかやっていないのですが、フィルムとデジタルで変わるところはありますか?
髙間 僕の場合は、撮り方もライティングもあんまり変わらない。デジタルだからライトが少なくていいでしょと言われるけど、フィルムの時代も充分に少なかったからね(笑)。ライトが多いのは好きじゃない。もちろん必要あるときは使うけど、夜は暗くていいわけだし。
それよりもフィルムをケチケチ使うことに嫌気がさしていた。デジタルならそういう心配がない。気が楽なんだよね。
5ストップしかない時代のビデオでの撮影方法
辻 『17歳の風景』を撮った時、僕はドキュメンタリー出身だから、自転車で向こうから戻ってくるというシーンで、向こうに行く時もカメラを回していたら、若松監督はそういうのを喜んでましたね。
髙間 フィルムだったらそうはいかないからね。
辻 若松監督は「うちのカメラマンはずっとカメラを回してるからな」って自慢してたけど、なんでそれが自慢なのかわからないですが(笑)。
髙間 そういう意味では若松監督にとっても、辻さんにとっても幸運な出会いだった。
辻 出会うタイミングがちょうどよかったのかもしれませんね。ラフ、雑、よくいえば自由な映画作りに、僕みたいにあんまり劇映画の作り方がわからない若者を連れてきて仕込めばいいやという。
髙間 若松さんはビデオが出て来た時代にビデオで撮りたがってた。ビデオだといろんな加工もできるし。「俺にもビデオ撮らせろ」と言ってたくらいだから。
辻 最初に頼まれたときに「僕はドキュメンタリーのカメラマンでビデオしか回してないから、ビデオ撮影しかできない」といったんです。そしたら、「俺もビデオが好きだから、ビデオで撮らせるから」と。
髙間 でも『17歳の風景』で夕暮れのシーンで、ビデオっぽくなく、いい感じの映像なんだけど、その現場のメイキングの映像がさ、当然同じ時間に撮ってるんだけど、全然違うんだよね。あれはどういう工夫をしたの?
辻 僕はビデオの貧弱な時代からやってるじゃないですか。ビデオでどうやったら深みが出せるかはわりと研究して来たほうだと思うんです。ベータカムは階調が5ストップしかくらいしかない。ただ『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』(1999年)というヴィム・ヴェンダースの映画があって、あれはHDCAMで撮っているんですが、これは可能性があるなと思って。それで『日本心中』というドキュメンタリーはDVCPROなんですが、現場にカメコンをもっていって、ワンカットずつ調整しながら撮っていました。さすがに『17歳の風景」はワンカットずつはやっていないんですけど。ハーフND3枚を大きなマットボックスで3枚回せるものがあるので、ワンカットずつ、ハーフNDをつけて空の輝度を落としていってラチチュードに収め、手前にはポーラ(PLフィルター)を入れて。あとはシャッターを1/100か1/125に入れたりとか。
髙間 なんでポーラをいれるの?
辻 アスファルトの反射を嫌って、アスファルトが黒くなるようにしたかったんです。それからおもにフェイストーンで、テカリを出したくなかった。ポーラとハーフNDフィルター、これにシネライクガンマのカーブを利用しながら、そのパラメータを微調整していきました。
当時は5ストップしかないから、そういう大変なことをしましたが、今ならLogやRAWで12とか14ストップもあるので、それを利用すればいいと思います。当時のビデオはフィルムからするとあまりに貧弱だったので、いかに質感を出すかということで苦労しました。
シャッターを入れるのは?
辻 自転車で旅する話だったので、ちょっと硬い印象を出したかった。『日本心中』という映画で俳優が歩き回るシーンで、シャッターを入れるとなんか感じがよかったんですよ。あんまりやりすぎると『プライベート・ライアン』(1998年)みたいな感じになって面白くないんですが、微妙にシャッターを入れておく。ドキュメンタリー撮っているときから、蛍光灯下だとシャッターを1/100にするじゃないですか。なんかそのほうが動きがいいなという感触があって。
ドキュメンタリーの経験が生かされているんですね。髙間さんはドキュメンタリーと劇映画で撮影に違いはありますか?
ドキュメンタリー、ドラマ、CM、それぞれの撮影方法を他ジャンルに生かす
髙間 僕は劇映画、CM、ドキュメンタリーをやってるでしょ。ドキュメンタリーをやっていても、その中でドラマをつくっていくという感覚があるし、CMやっていても、ドラマ撮影の技術が役に立つし、CMで商品カット撮っていると、その光物の撮影の丁寧さなんかはドキュメンタリー、ドラマに応用することができる。劇映画にしても、全部こっちで作り込むんじゃなくて、流れに任せて撮っていくというドキュメンタリーのスタンスを生かすことがある。つまり他のジャンルでの撮影方法が役に立つ。そういう考え方でやってますね。
辻 なるほど。柔軟性のなせるわざですね。ぼくは最初、俳優をどうやって撮ったらいいのかわからなかった。ドキュメンタリーの場合、向こう向いてしゃべっている人がいる場合、カメラマンが向こうに回りこまなければ顔は見えない。ところが俳優さんはドキュメンタリーでもこっちむくんですね、カメラを意識して。
髙間 ちゃんとした俳優はそうですよね。映ってなんぼですから。だからカメラも楽ですよ。いい位置にすえればいいんだから。
辻 僕は最初それが分からなかった。『キャタピラー』で寺島(しのぶ)さんとやったときに、若松さんが「このカメラマン、みんな押さえるから、カメラ気にしなくていいから」と言うんです。だからドキュメンタリー風にこっちで俳優が見えるようなカメラワークをしたんですが、それはうまくいきました。いい俳優はスタイルに合わせられるんだなと思った。
カメラマンのスタイルとは?
辻 撮影のスタイルの話でいうと、髙間さんが最近撮られた『心に吹く風』(ユン・ソクホ監督/2017年)は、最近の映画ではめずらしく、あれだけ端正に撮られた映画というのはないですね。物語はある意味、ベタなところはあるんですが、映像美を含めた世界観が確立していて、そういう映画としては群を抜いていた。
髙間 ユン・ソクホ監督の美意識が大きくて、自分でも5Dとかを回しているし。ああいう話は、一つの世界感にとじこめて納得させないと、今の人には通じないと思った。
辻 最近、あれだけ端正に撮られた映画というのははあんまりないですね。定期的にこういう映画がないとリファレンスがなくなっちゃうと思ったんです。やはりオーソドックスがないと。
髙間 ぼくが考えるよりも、監督の指示のほうが全体に「引き」だった。でも、僕が撮るとどうしても端正な構図になる。そこを崩そうというのがかえって難しい。自分が好きな構図になってしまう。これからは、そこをわざと外す努力をしていかないと。
辻 これから挑戦していくということですか?
髙間 もちろん作品に応じてね。バストサイズつくるときに、落ち着いた構図を選択しないことによって、新たな情感がうまれるかもしれない。
辻 髙間さんほどのベテランになっても、これからスタイルを変えていこうという姿勢がすごいですね。髙間さんは次から次へと若い監督と組んでいますが、人気がありますね。
髙間 同世代とはあんまりやらないもん。そもそも同世代の監督は呼んでくれないから。ベテラン監督は若いカメラマンと組めばいいと思う。若い監督は若いカメラマンじゃなくて、僕とならいつもとは違うスタイルになるのでは? 監督が考える以外のことを出してくれるんじゃないか? という期待があるのではと思う。
辻 ベテランのカメラマンの中には若い監督と組むと、もめる人も多いですね。
髙間 そりゃ、監督の言うこと聞かない人でしょ。
辻 髙間さんはそういう話はないですね。
髙間 僕と正反対なのが木村大作さんだと思う。木村さんの映画は、見れば、すぐに分かる。どんな映画でも、どんな監督と組んでも木村さんのスタイルがある。でも僕はそれではつまらないと思うんだよね。確立した方法があるとしても、同じことをやっていたら、自分がつまらないんじゃないかと。それよりも監督がこれをやりたいといえば、じゃあ、やってみましょう、といって挑戦したほうが自分もおもしろいと思う。
たしかに今回の映画制作記の連載を読んでみると、髙間さんは様々な監督といろいろな手法を試してみるという映画人生ですね。
髙間 だって連ドラを30年もやったら飽きちゃうじゃない? 映画は1か月、2週間というのもあるけど、監督ごと、映画ごとに違う世界を見ることができる。自分で違う世界を作っていけばいいんだから。
辻 名カメラマン、ネストール・アルメンドロスの言葉で、カメラマンは旅人だと。イマジネーションの宇宙を渡り歩く旅人だというような発言がありました。
注:ネストール・アルメンドロスの著書『キャメラを持った男』の冒頭で、「撮影監督の仕事」について、「(撮影監督の)いま一つの利点は、しばしば旅をする機会に恵まれるということだ。そして撮影クルーから撮影クルーへ、監督から監督へ、移ってゆけるということは、多彩で、冒険に富んだ人生をもたらしてくれる」と書いている。
髙間 そういうイマジネーションをもっている人、オリジナリティがある人が監督なんだよね。自分にはその才能はないし、たまには口出しするけど、それよりもカメラマンとして、いろいろな監督の世界を具現化するということが面白いんだと思う。
カメラマンかカメレオンか分からないけど(笑)、監督によって色をどんどん変えていく。そうすると自分の個性というのはどこにあるんだろうと思うことがある。でも、どこかにその人の個性はあるんだと思う。
辻 僕もどこかで書いたことがあるのですが、監督、演出家というのは世界を創造する神様のような存在で、カメラマンというのはその世界を生きる人間なんだと。でも、ぼくは人間のほうが面白いよ、と思います。
髙間 それは名文句だね。僕がヴィルモス・スィグモンドが好きだといったら、ある人が「あの人は自分というものがないよ」と言うのね。たしかに彼にはこれといった特色はないけど、全部の作品において作品がちゃんと成り立つように撮っている。それはそれでいいんじゃないかと。
ビデオサロンの連載はここ7年くらいの高間さんの活動報告のようなものでしたが、今回の辻さんとの対談で、髙間さんが目指している理想のようなものが浮き彫りになったような気がします。本日は長い時間、ありがとうございました。