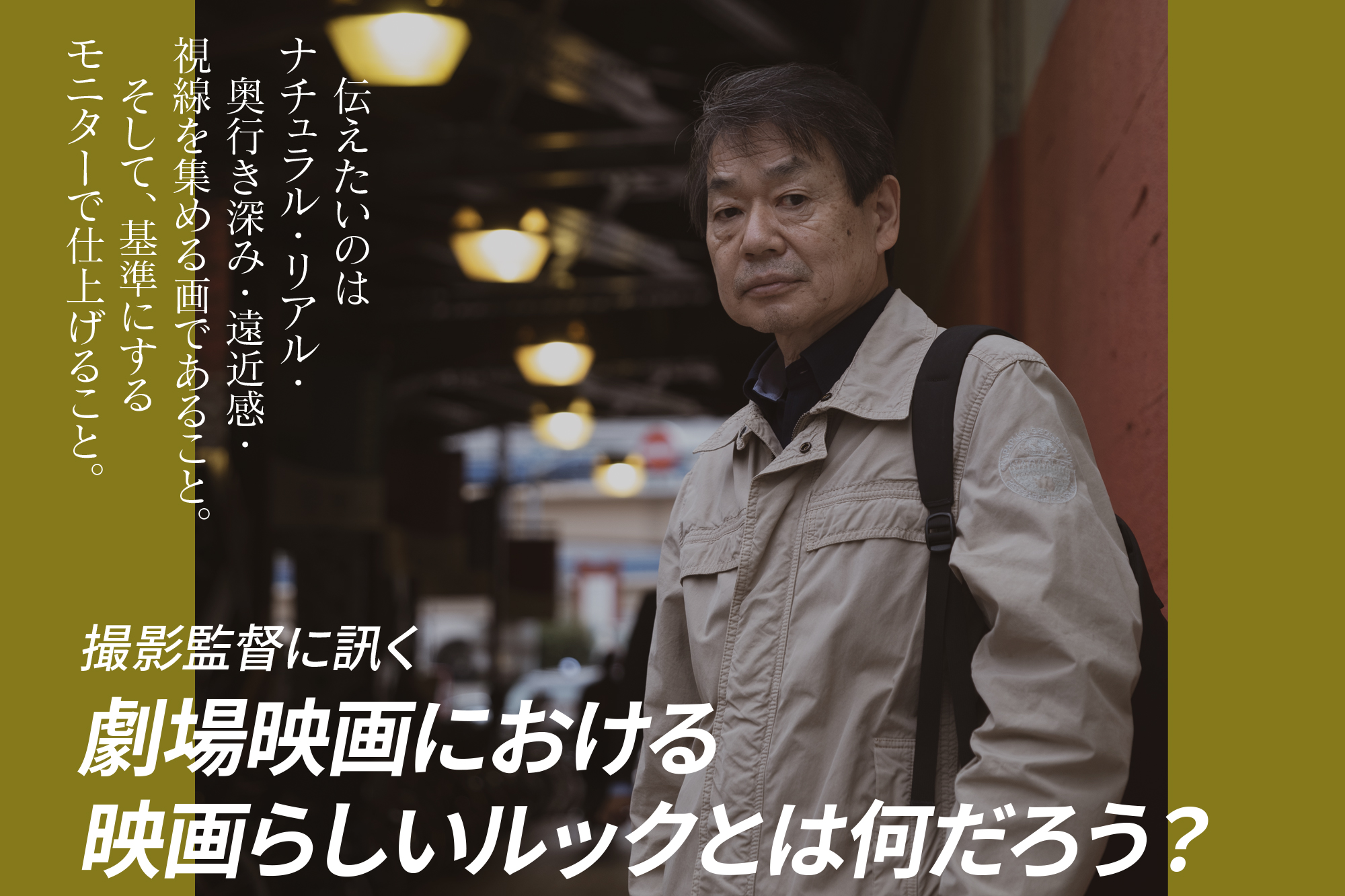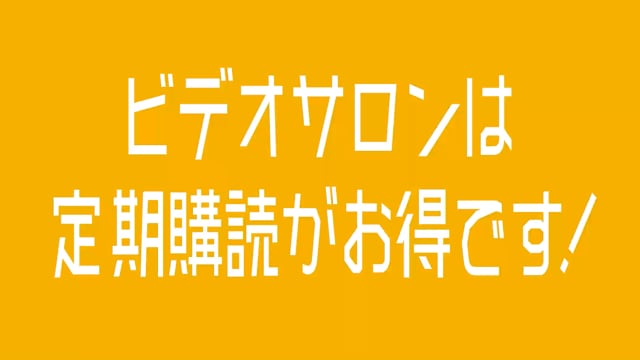日本アカデミー賞・優秀撮影賞を3度受賞し、2015年以降、デジタル撮影に移行している柴主高秀さんに、本丸である映画のルック作りについて伺った。
取材・文●前田有一
●VIDEOSALON 2021年1月号より転載

撮影監督 柴主 高秀
しばぬし・たかひで 映像制作会社を経てフリーの撮影助手になり、映画制作に携わる。長田勇市に師事。1996年、フリーカメラマンとして独立。『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』(2009)『日本のいちばん長い日』(2015)『関ヶ原』(2017・最優秀撮影賞)で日本アカデミー賞・優秀撮影賞を3度受賞。デジタルで撮影した主な作品は『ラブ&ポップ』(1998)『アカルイミライ』(2003)『どろろ』(2007)『駆込み女と駆出し男』(2015)『日本のいちばん長い日』(2015)『溺れるナイフ』(2016)『関ヶ原』(2017)『検察側の罪人』(2018年)『あの頃、君を追いかけた』(2018)『空母いぶき』(2019)。『燃えよ剣』(2021)など。
「最近フィルムルックってよく聞くけれど、僕らプロの認識と一般で一番違うのは、僕たちはそれを”最終媒体”について語っている、ということです。最終媒体とは、僕らならスクリーン、つまり反射映像ですね。決してモニターやディスプレイに映すわけじゃない。自分が撮っている画が、最終的に反射映像としてどう見えるか、常に考えて撮影しています。例えばデジタルでいくらフィルムっぽい映像を撮っても、意図通りにスクリーンに映らなければなんの意味もない。
それを大前提として言いますが、現代の映画館はほぼすべてデジタル上映です。若い人はそもそも、本物のフィルムで上映した映像を見たことがない人もいるんじゃないかな。だとすると、デジタルとフィルム。最終媒体におけるその個性の違いをどうやって見分けるというのか。もしかしたら、全くわからないかもしれない。
そうした、本物を体験していない世代に”フィルム風”と言ったとしても、果たして正確にイメージを伝えられているのだろうか、そんな不安が常にあります」
日本アカデミー賞・優秀撮影賞を3度受賞(『関ヶ原』17年最優秀撮影賞、『日本のいちばん長い日』15年、『ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜』09年)した柴主高秀氏は、「フィルムルックな映像はどう撮ればいいのか」という、いささか乱暴すぎたかもしれない質問に対し、そんな風に切り出した。
「映写時ではなく、どんな画が撮れるか、つまり撮影面に関して言えば、今ではフィルムもデジタルも、何ら変わるところはないと思います。ただ、それでもフィルムルック……あるいは”映画的な画”を撮るという意味で言えば、心がけている方向性はありますね。それは、やや抽象的ではありますが、ナチュラルでリアル、それでいて奥行きのある映像にすること。何より、監督の見てもらいたいところに視線を集めるように撮るということ。それを、現場から仕上げの工程まで、一貫して考えています」
柴主氏が撮る映画は、デジタル撮影に移行したのちも、フィルム時代と同様に色気のある、まさに我々が思う”フィルムルック”な画づくりを特徴としている。役者の顔面にバシっと人工光を当てる、のっぺりとしたテレビドラマ風とは対極にあるムーディな映像美だ。
例を挙げると、余命24時間となった名もなき人々の死にざまを描いた感動作『イキガミ』(08年)。彼らは国家繁栄のため、国からランダムに選ばれ”排除”されるとの世界観だが、こうしたSF現代劇は慢性的予算不足の邦画が最も苦手とするジャンル。映像も中身もチープに仕上がるのが関の山で、コミック実写化としても、うまくいったためしがない。
だが柴主氏は、浅い被写界深度と、彩度を抑えた重厚感のある映像でその難関に挑み、荒唐無稽な設定に息詰まるリアリティを与えることに見事成功している。まさに「ナチュラルでリアル、それでいて奥行きある」映像なのだが、その秘訣は決して機材にのみあるわけではないという。
「確かにアマチュアとプロではカメラは違うでしょう。しかし、撮影方法は何も変わりません。アベイラブルな、つまり”そこにある光”を利用して撮影する。僕の場合もそれが基本です。映画にはまずドラマと設定があり、それを支えるシチュエーションを作るのが僕らの仕事。自然光やアベイラブルライトを見て、どこに露出点を切ればいい雰囲気を出せるのか、考えに考え抜くということです。例えば昼間の薄暗い部屋で、光源は外から入り込むぼんやりとした光しかない状況を想像してみてください。室内には薄暗い中に人物がいて、動いて何かをやっている。HDR等でその場の薄暗い暗部を意識しないで撮影すれば明るくきれいに映ります。でもね、僕はそういうことを望ましいとは思わない。むしろその部屋の暗部・闇を生かしたダークで自然なシチュエーションで撮影をしたいんです。だから人工的な光は極力使わない方向で考えます」
照明効果やフィルターの使用、スタジオ撮影すら禁じる撮影ルール「ドグマ95」を定めたデンマークの映画監督ラース・フォン・トリアーほどストイックではないにしても、映画界には自然光や、アベイラブルライトを利用する撮影こそが好ましいと考えるクリエイターは珍しくない。柴主氏も、その場にある光を生かす撮影の魅力を強調する。
「たとえば『関ヶ原』(17年)なんかは本格時代劇ですから、ロケハンでは1600年代からある本物の寺院とか重要文化財とか、そうした場所をいくつも回るわけです。その多くは観光地になっているので、どうしても人口的な光、照明が当たっていますよね。ではそれを消したらどんな光が残るのか。それこそ400年前と同じ、今も昔も変わらない寺やお城の姿が見えてきます。なるほど、この時間帯でこう見えるなら午後ならこうなるな、だったらこの場所で撮影するなら何時ごろがいいだろうと。僕はそういう発想をするんです。
特に時代劇では、古からそこに存在した光を使って撮影することで、本当にリアルな姿を写し取ることができるはずだと。それこそ、嘘偽りのない撮影になるんじゃないかと考えています。もちろん監督から、表現として足りないと言われれば光を補うこともします。しかし基本的には自然な光を利用した撮影のほうがふさわしいだろうし、いかに監督の演出を邪魔しないように仕事をするかが僕らの腕の見せ所ですからね」
とはいえ、デイライトかナイターか、屋内か否かでも難易度は大きく変わってくるだろうし、限界もあるはずだ。
「確かに、電気のない時代の話ともなれば、夜のシーンを自然光で撮ることは難しい。まして屋内ともなれば月光も入ってこないわけで。ではそこで何がキーライトに使えるのかと考えると、それこそ蝋燭くらいです。実際そうした撮影現場もありましたが、相当悩みました。本物の蝋燭を使うことももちろん可能ですが、『燃えよ剣』での幕末、池田屋での斬り合いのシーンのように総勢50人が動き回るスペースを照らすともなれば、とてつもない数が必要になる。確か池田屋全体で40〜50本あったんじゃないかな。
それら全部にいちいち火をつけたり消したりとなれば、それだけでもかなりの手間です。それをする人手もなければ火事の危険性だってある。池田屋はセット撮影でしたが、『関ヶ原』のときは世界遺産の姫路城でのロケも行いましたから、言うまでもなく火気厳禁です。したがって本物の蝋燭は使えません! まして城内にはACコンセント(電源)がないため遠く離れたジェネレーターから電源を引くこととなりました。結論としては電球蝋燭を製作し、CG部の協力で炎の部分だけCGで差し替えることにしました。これは致し方ない。しかし作品全部がそうではないし、蝋燭の光じたいは生かしているわけですからね。お客さんが見て、その光が本物か否か、簡単にわかるようにはしていないつもりです。
こうした作業はフィルム撮りでもできますが、スキャニングの工程が余計にかかる分、コスト的にもやはりデジタルならではの強みですね。こうしてCG部の助けも借りつつみんなで研究して、だからこそ映画は総合芸術というわけです。そうして得た知見、ノウハウは次の作品、今回で言えば『燃えよ剣』にも生かされています」
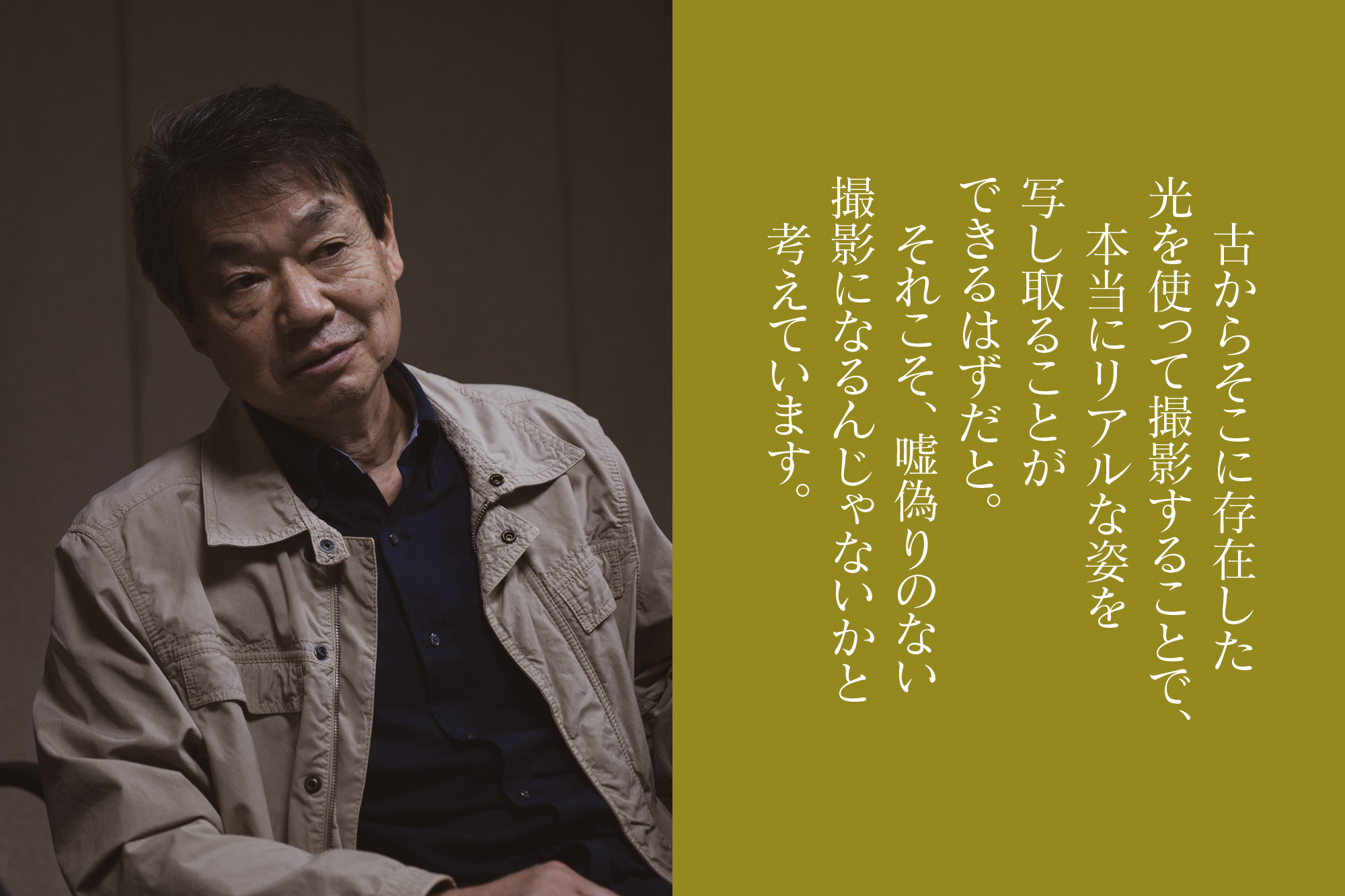
原田眞人監督との作品作り
こうした職人気質の柴主氏を高く評価してきたのが映画監督の原田眞人氏だ。原田監督は柴主氏が本格的にデジタル撮影に移行するきっかけとなった『駆込み女と駆出し男』(15年)以降、『燃えよ剣』(21年)まで5作品連続でカメラを任せている。その間、『関ヶ原』(17年)と『日本のいちばん長い日』(15年)では、前述したとおり日本アカデミー最優秀撮影賞も受賞したわけだが、これには二人の相性の良さが要因としてあるようだ。
「これまで多くの監督と組んできましたが、原田監督とは映像に対する感覚、センスが似ていると感じています。原田さんはものすごく映像を重視する人です。例えばレンズ(焦点距離)を指定してくることもあります。そして監督の場合は、ロケハンの時に見て気に入った直射光の向きや具合などをしっかり記憶していて、撮影に入ってからもその光が出たとたん、別のシーンをやっていても中断して大急ぎで移動して撮りに行ったりする。こっちとしては本当にやりがいがあるしありがたい、徹底してこだわり抜くタイプです」
興収29億円の『検察側の罪人』、24億円の『関ヶ原』など原田眞人監督&柴主高秀撮影監督のコンビは、これまで名だたるヒット作を手がけてきたが、柴主氏はそうした高評価の要因を「エンターテインメントだがドキュメンタルな原田監督の作風と、リアリズムにこだわる自分の映像のマッチングにあるのでは」と分析する。
「原田監督の現場はハリウッドシステム、つまり2カメ体制で、一回一回行けるところまで通しで撮ります。カチンコの音ではなく監督のアクションの声で全てが始まるし、誰かがNGを出しても芝居を止めない。一人が失敗しても別の誰かがいい芝居をしているかもしれないぞ、というわけです。だから僕らもカメラを回し続け、それを捉えなくてはいけない。そんな現場を体験して感じたのは、これは私が思っているだけかもしれませんが、監督の演出は役者の芝居や動きに制限をかけない、ある意味ドキュメンタリー的な撮影方法でもあるのかもしれない。
そしてもう一つの特徴はワンチームということ。普通、日本映画というのは、たとえば撮影と照明は比較的きっちり分かれていて、それぞれがクリエイティブな仕事をしていこうっていう伝統があるわけです。でも原田組の場合は、撮影監督システム的な考えがあるように思う。映像についての全責任は撮影監督のお前だぞ、というところから始まり、その上で監督がやりたいことを、僕と話し合って決めていく。そうやって現場を一つの目的意識に統一し、照明や美術の人たちと協力して実現させていく。どちらのスタッフが上とか下という感じはなく、一丸となってやる。こういう仕事の進め方は、原田組独特のものですね」
もっとも、カメラマンは様々なタイプの監督と組むため、職人としてあらゆるニーズに対応できる必要がある。アベイラブルライトとは真逆の方向性を求める作品も時にはある。
「原田監督のドキュメンタルな演出の時代劇には、余計な作りこみをしない撮り方がいいと判断したのですが、根岸吉太郎監督の『ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜』(09年)なんかはオールセットなので、当然照明が入ってきます。太宰治の世界観をああいう形で映像化する根岸監督の意図だろうということで、こちらも全力で支えました。それでも、最初にも言ったとおり映像作品は監督が見せたい部分に視線を誘導することが何より大事で、その意味ではどの作品も同じように撮っている意識もあります。なんたって光を当てなきゃ映らないものに対して向き合っている点では変わらないわけですから。どちらのやり方にも良さはあります」
自身の映像志向と、必ずしも一致する現場ばかりではないのは当然だが、そんな『ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜』でも柴主氏はやはり日本アカデミー優秀撮影賞を受賞しているのだからプロ中のプロだ。
「この作品もデジタルでしたが、実は僕はデジタルになってから、露出計は使っていないんですよ。それよりも大事なのは、自分の映画の中で全ての基準となるマスターモニターをカメラに取り付けておくということ。いろいろなメーカーから様々な商品が出ているけれど、僕はTVLogicの液晶モニターを使っています。有機ELなど新しくて高スペックなものに惹かれる人も多いでしょうが、僕らの場合、あれほど黒が締まってしまうと、逆に最終媒体である反射映像との差が大きすぎて、現場で映写時の雰囲気を再生できない。だからあえて液晶を選び、カメラテストを繰り返します。

▲前田有一氏
撮影現場では視聴環境と同じ基準でモニター
具体的には撮影素材をカメラごと、ポスプロを行うグレーディングルームに持って行きます。そして収録したものをスクリーンに映しながら、カメラ側のマスモニと全く同じように見えるよう、調整作業を行うわけです。有機ELだとコントラストの差が大きすぎて、この調整作業がうまくいきません。カメラやレンズもそうですが、要するに機材はあくまで自分がやりたいことを実現するために最適なものを選ぶべきで、そこを明確にしないと迷うばかりだということです」
グレーディングルームなどとは無縁で、スクリーンに映す機会さえないアマチュアや愛好家でも、撮影機材側のマスターモニターと、最終的に映すことになるテレビやパソコン側のモニターを極力合わせておく、もしくはどの程度の差があるかをしっかり把握しておくことが大事なのだという。
「本当はね、この雑誌みたいに紙媒体、これが一番わかりやすい。誰が見ても同じように見えるからね。でも、もしこれがパソコンのモニターだったら、それこそWindowsかMacか、どこのメーカーの液晶モニターかで全く違ってきてしまう。同じ写真を表示したって、きっと同じようには見えないでしょう。だから僕らが、いま撮ってるものが最終媒体でどう見えるのか、そこにやたらとこだわっているのは、結局その違いを知っておかないと、フィルムルックも何も語れないし、再現もできないからです。
これがもしスクリーンではなくPCでの再生用だったとしても、誰のどのモニターで映すのか、常にその最終媒体を意識して、同じように見えるものを撮ろうと努力することが大事なのです。そうした意識をもってやっている人は、それが必ず作品に出てきますよ。僕だって、今では自宅のテレビは自分の色に変えています。なぜかって、自分が撮った映画のDVDを再生したとき、テレビで見ると全然撮影時の意図と合っていなかったから。
昔、二つの番組を同時視聴できるテレビでNHKの大相撲中継を映してみたことがあります。地上デジタルとBSですね。すると、BSはそれこそどことなくフィルムの雰囲気に近いんです。深みがあって、色もよく乗っている。同じ映像ソースのはずが、地上波と衛星波というだけでこれだけ変わってきてしまうとなると、はてフィルムルックとは一体何なんだという話になりますよね。そうした経験を一度でもしてしまうと、テレビだってきっちり合わせておきたくなるんです」
 ▲ロケハンで撮影した映像をスクリーンに投影しながらグレーディングし、LUTを作りながら現場で使うモニターの見え方も合わせ込んでいく。映画『関ケ原』で利用したのは東京現像所のカラーグレーディング・コンフォームルーム「DI meister Ⅱ」。
▲ロケハンで撮影した映像をスクリーンに投影しながらグレーディングし、LUTを作りながら現場で使うモニターの見え方も合わせ込んでいく。映画『関ケ原』で利用したのは東京現像所のカラーグレーディング・コンフォームルーム「DI meister Ⅱ」。
フィルムからデジタルへ移行時にした挑戦
エンドユーザーの目に、自分の目に映っているのと同じものを届けたい。そのために最適な機器を選んできたという柴主氏に、フィルム時代からデジタルに移行するまでの、分岐点となった作品について聞いてみた。
「完全に移行したのは15年以降ですが、古くは98年の庵野秀明監督作品『ラブ&ポップ』で、軽快なカメラワークを実現するために一部ハンディカムなどを導入したことはあります。09年の『ヴィヨン〜』もデジタルだし、でもデジタル移行の分岐点となったのは黒沢清監督の『アカルイミライ』(02年)でしょうね。あれだけのハイライトでコントラストを意識させる、デジタルならではの映像を監督と作り上げることができたのは大きな収穫でした。予算が限られる中、黒沢監督ほどのクリエイターがやりたいことを詰め込もうとすれば、デジタルでしかできない表現で、となる。
あの作品がチャレンジングだったのは、フィルムと同じことをやるのはやめようと決断したことです。どうせやるなら徹底的にということで、サチュレーション(彩度)も抜いてるんです。……というと、ただの脱色でしょ、なんて思うかもしれませんが違います。システムが変わってしまった今のデジタルカメラでは、あの作品のトーンは出せません。あれは当時使っていたソニーのF900っていうHDCAMが、カメラコントロールユニット(CCU)とビデオエンジニア(VE)がマルチコードでつながっていたからこそ出せた色なんです。具体的にはRGBの各色素を個別に抜くことができたので、脱色でなく退色に見せるような効果が出せた。こんな風に、ある時代の機器だからこそできることもあるので、やはりいろいろ試すのが大事ですね。そしてこの作品で研究したことを、5年後には『どろろ』(07年)で、数十億の製作費でやったりしています。試行錯誤の経験は必ず生きますよ」
現在は、そうしたプロの蓄積を反映したLUTを当てることで、アマチュアでも手軽に再現しやすい時代になった。柴主氏は、LUTについてどう考え、プロの現場で活用しているのだろうか。
「僕は『関ケ原』ではオープン用に二つ。全部で10個くらいはLUTを持っていましたね。LUTは脚本を読み、ロケハンに行った後に作ります。撮影場所に対して作るので、監督の要望、世界観が定まってからです。なので、ロケハンで写真などを撮っても見返すことはあまりない。記憶に頼る部分が大きいです。というのは、ロケハン時点で監督の要望を聞き、すでに対処法を考えてあるからです。
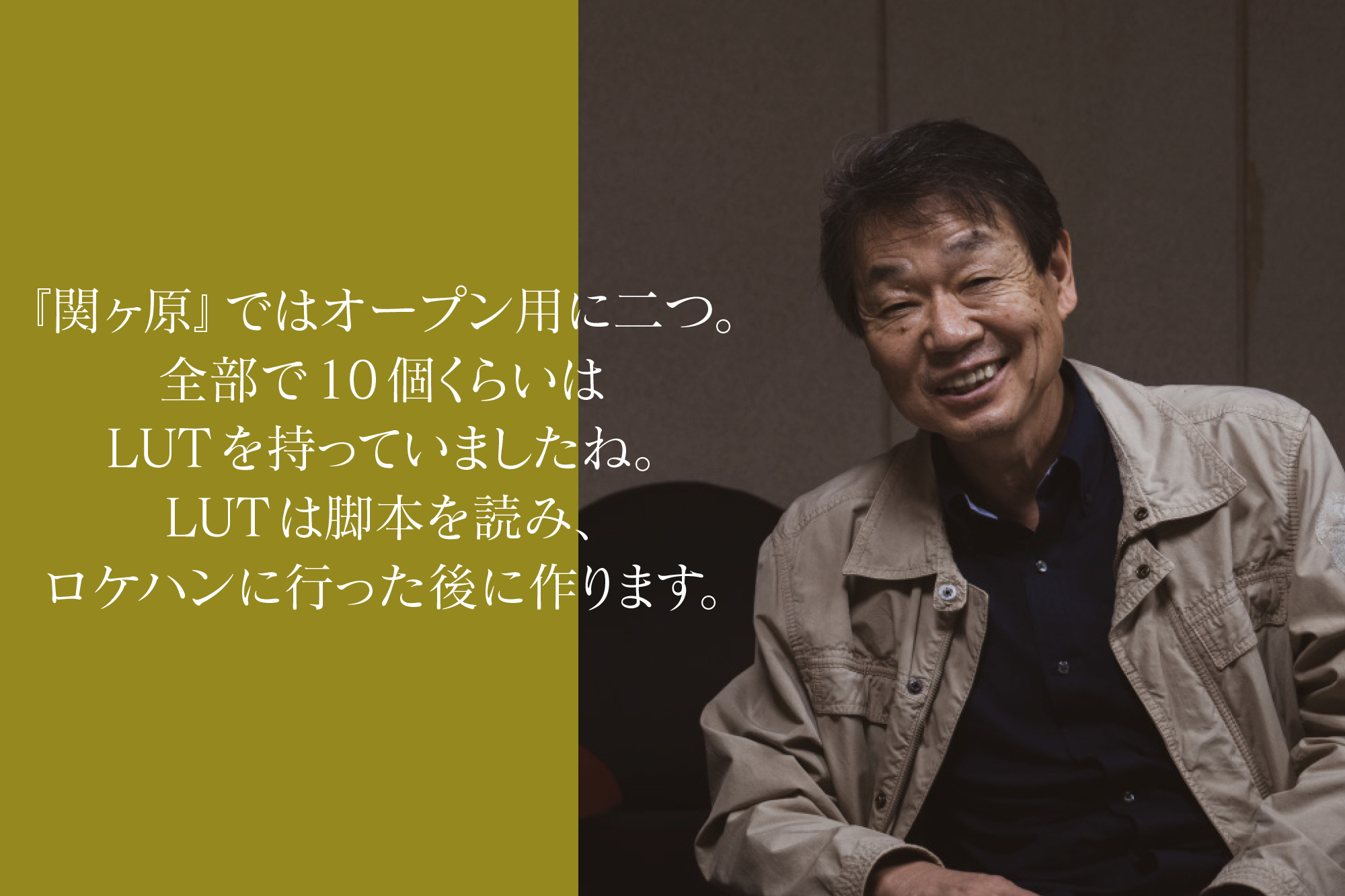
たとえば会議室のシーンなら、この蛍光灯にはGが含まれてるな、ならそれを生かしてさらにRも加えるか、みたいに。色温度もこれは4800°Kあるけど4500°Kにしようとか、そういう計算を現場でしておいて、後でスクリーンで映してカラコレ(色彩補正)して希望通りに調整してLUTを作る。それを入れて同じになるかテストする。そんな感じです」
ただし、柴主氏はフィルターで色を染めるような、フラットな画作りは好きではないという。奥行きと深みのある映像のためには前景と背景の色味を同じにする必要はなく、個別に変えられるシステムを考えることが大事だという。
「そうやってコントラストをつけることで色にも厚みが生まれ、いわゆる深みと奥行きのある映像になる。そこに程よい被写界深度を与えてあげるといいんです。僕の場合はいつも絞りはニッパチ(2.8)、解放くらいです。実は僕はフィルム時代、柔らかく映る──コントラストがあまりつかないフィルムを使って撮影し、それを正反対の固いポジに焼き付け上映することで自分のスタイルを作っていきました。
それを現代に置き換えると、例えば僕は40年も前のツァイスのレンズを使っている。今どきのレンズに比べればシャープネスなんてないですが、むしろ要らないんです。それで撮った画に、固めのLUTを当てるんです。すると、柔らかいレンズが作り上げた中間層がものをいう。さっき言ったようなスタイルが再現できるというわけです」
そんな独自のスタイルを、自らメガホンを取って世に問う日は来るのだろうか。そう問うと、照れくさそうに笑いながら彼は言った。
「いやいや、それはないですよ。僕はホンを書いたり芝居をつけたりはできないからね。でも、映像に対する情熱や発想は負けないって思いはある。だから充分今もクリエイティブな仕事ができているし、仕上がりには絶対に妥協しない気持ちでやってます」
●VIDEOSALON 2021年1月号より転載