

ハードルが高く思われがちな国際映画祭だが、参加者はどんな魅力を感じているのか?
今回は、映画祭のプログラミングディレクター、プロデューサー、監督という三者にそれぞれ立場から、国際映画祭に参加した“当事者”としての声を聞いた。

矢田部吉彦氏 東京国際映画祭プログラミング・ディレクター
汐巻裕子氏 プロデューサーピクチャーズデプト代表
井樫 彩監督 映画『溶ける』『真っ赤な星』監督
■やたべ・よしひこ/東京国際映画祭の「コンペティション」部門、「日本映画スプラッシュ」部門のプログラミングを手がける。■しおまき・ゆうこ/海外セールスなどを手がけるピクチャーズデプト代表。プロデュース作品に最新作『旅するダンボール』や『サケボム』など。■いがし・あや/1996年生まれ、北海道出身。学生時代に制作した『溶ける』が第70回カンヌ映画祭に出品。オムニバス『21世紀の女の子』の公開も控える。
Q1 日本のクリエイターは国際映画祭に無関心かも?
A. 「日頃から、映画の現場にいて、日本のフィルムメイカーと海外のフィルムメイカーでは、国際映画祭に対しての向き合い方に大きな違いがあると感じています。私は映画プロデューサーとして、特に若い世代の日本のフィルムメイカー全員に言いたいのは、もし将来、本当に海外で勝負する気があるのなら、自分の足で国際映画祭に行かなきゃダメだということです。自分の作品を海外のオーディエンスに見せて、その反応を肌でダイレクトに感じながら、じゃあ次の作品でこうしよう…と、アイデアを考えることが、その後の映画づくりへの経験値になると思っています。
日本の映画業界ってちょっと変わっていて、苦労を重ねて作った映画を海外の映画祭に出品することが“ご褒美”のように考えているところがあると思うんです。映画祭側から渡航費をはじめとした予算が出ないんだったら行きません、みたいなことも耳にするんですけど、それはちょっともったいないんじゃないかな…と。例えば、ひとつの映画祭に参加するための渡航費に15万円ぐらいかかるとしても、そんな予算は参加したフィルムメイカーのその後の活動を考えれば、すぐにペイできると思いますよ。私は、国際映画祭にはお金を払ってでも行く価値があると感じています」(汐巻)

▲海外セールスや海外戦略プロデュースなど、これまでに多数の実績を持つ汐巻氏
Q2 日本と海外の映画祭で大きな違いはある?
「違いとしてとても大きく感じたのは、海外映画祭は、オーディエンスもメディアもそうなんですが、政治や人権問題、LGBTQなどに対する意識がものすごく強いということ。作品上映時のQ&Aや海外メディアから映画における表現をより多方面から論評されます。
初めての長編映画『真っ赤な星』でイギリスのレインダンス映画祭に参加した際は、作品を絡めて、#MeTooやLGBTQをはじめとするマイノリティについてなどを質問されました。映画ではミニマムな個人の世界を描いているが、個人というのは大衆であり、それは社会問題にも繋がっていく、また最初から大きなテーマありきで作ってはいなくても、結果的に大きなテーマ性を帯びる…という話をしました」(井樫)
 ▲レインダンス映画祭のQ&A。映画の内容だけでなく、その映画から見えてくる“今の世界”にも言及されたという。
▲レインダンス映画祭のQ&A。映画の内容だけでなく、その映画から見えてくる“今の世界”にも言及されたという。
Q3 映画人の夢?カンヌ映画祭って何が違うの?

「2017年に、『溶ける』という作品で第70回カンヌ映画祭の「シネフォンダシオン」部門(学生作品のコンペティション部門)に出品しました。初めてカンヌ映画祭に行くまでの認識は、“きらびやか”というイメージがある程度でした。ただ、実際にカンヌに行って映画祭に参加してみると、映画産業としてのスケールの違い、表現の多様性(日本の作品はやはり“エンタメ”系が多い印象ですが、カンヌで観た作品たちはどれも“芸術”の比重が大きかった)、映画が文化としてちゃんと根付いていることなど、『こんなにも大きな世界があるのか!』ということを身をもって感じることができて、それと同時に自分がいかにちっぽけであるかを認識しました。今もまだまだ勉強中の身ですが、自分の作品で参加したカンヌ映画祭で“世界を見る”という貴重な体験ができたことは、今後も映画を撮っていくにあたり、糧になっていると思います」(井樫)
 ▲カンヌ映画祭に参加した井樫監督。クリエイターをはじめ、会場ではさまざまな出会いも。
▲カンヌ映画祭に参加した井樫監督。クリエイターをはじめ、会場ではさまざまな出会いも。
Q4 映画人という肩書きを忘れて旅行としても楽しめる映画祭は?
「我々の業界の中でも、『どの映画祭に行くのが面白いか』ということはよく話題にのぼりますが、『スペインのサン・セバスチャン国際映画祭が一番』という話はよく聞きますね。映画祭としては、ラテン映画が最も集まる場所としてちゃんと機能していて、(スペイン語圏である)中南米エリアの作品のワールドプレミアが行われることも多いですし、かなりワールドワイドなラテン映画の祭典にもなってします。…と言うより、何より“メシ”がうまい(笑)。メイン会場はビーチの横にあって環境も良いし、ワインもうまいなんて最高ですよね。ただ、東京国際映画祭(TIFF)の直前にあるので、僕は絶対に行けないんです(苦笑)。TIFFを辞めたら行きたい思ってるんです」(矢田部)
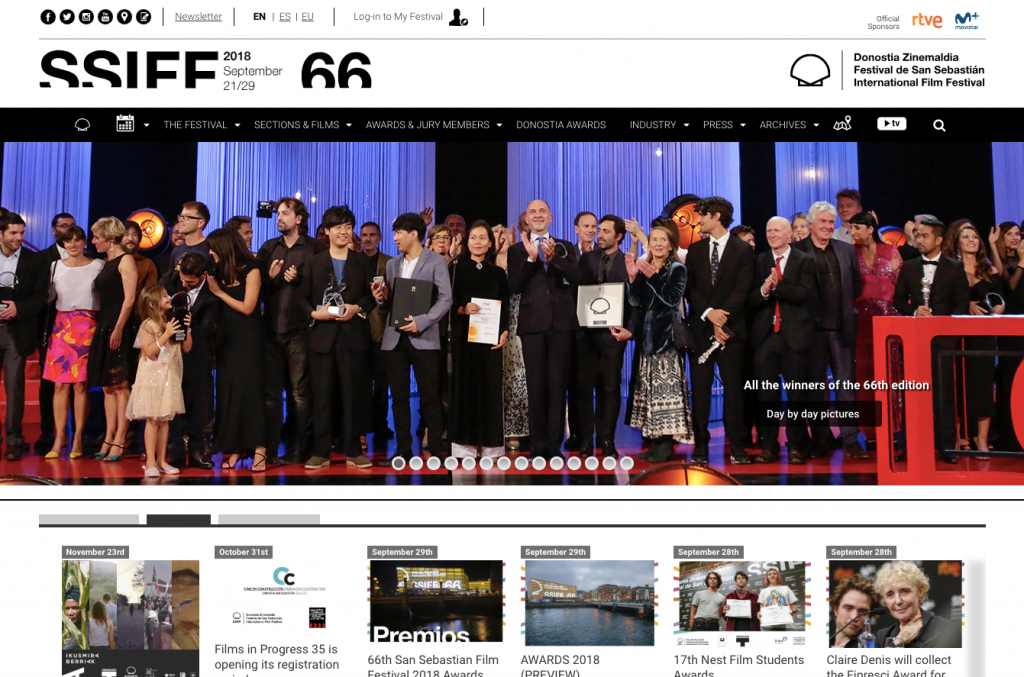
▲プロが薦める映画祭はサン・セバスチャン!(※画像は公式サイトのスクリーンショット)
Q5 最近勢いに乗っている知る人ぞ知る映画祭は?
「アジアの映画監督たちの間で話題になっているのが、インドネシアで人気の観光地・ジョグジャカルタで毎年11月に開催されているジョグジャ・ネットパック・アジア映画祭。昨年の東京フィルメックスでグランプリを受賞した『見えるもの、見えざるもの』のカミラ・アンディニ監督ら、インドネシア出身の監督たちが中心になって運営している映画祭なんですが、とにかくアツいと評判になっているんです。実は、国際交流基金アジアセンターとTIFFによるオムニバス映画共同製作プロジェクトである『アジア三面鏡2018:Journey』も、TIFFでのワールドプレミアに続いて、同映画祭でプレミア上映されたんです。TIFFやフィルメックスに参加した国内外の映画作家たちの間でも、『次はどこの映画祭で会う?』『じゃあ、ジョグジャカルタで会おう!』というような会話がよく交わされていて、僕も気になっているところです」(矢田部)

▲ガリン・ヌグロホ監督らが、アート映画の未来のために立ち上げた。(※画像は公式サイトのスクリーンショット)
Q6 海外映画祭にただ出品すれば良いではない?

▲『旅するダンボール』で参加したSXSW。
「映画と映画祭の相性には合う・合わないがあると思います。日本映画の海外セールスをしているなかで、ゲストを連れて世界中の映画祭を回っているんですが、映画祭のディレクターとプログラマーの嗜好とか、見にくるお客さんの層とか、映画祭の特徴がわかってきました。製作と海外セールスを担当した『旅するダンボール』の場合は、エンタメ寄りのドキュメンタリーであること、監督が初長編というフレッシュさ、“ダンボール”という特殊なネタ、それに対して一番理解してくれるのはSXSWのディレクターで、それを一番楽しんでくれるのはSXSWのオーディエンスだろうな、と思って出品を決めました。SXSWはまさに玉石混交で、ワールドプレミアをしてもお客さんが全然来なくて落ち込んでいる監督もいました(笑)。でも、その作品が悪いというよりも、SXSWのオーディエンスにハマっていなかっただけ。どの映画祭に出品するか、ちゃんと理解して選ぶのもプロデューサーの仕事だと思います」(汐巻)

▲映画鑑賞中のSXSWのオーディエンス。
Special Report
“初めてづくし”の国際映画祭!映画監督・岡島龍介が体感したSXSW
 ▲初長編『旅するダンボール』でSXSW 2018に参加した岡島監督。
▲初長編『旅するダンボール』でSXSW 2018に参加した岡島監督。
「SXSWへの正式出品が発表された瞬間、海外のバイヤーや映画祭からのオファーのメールが殺到しました。それと同時に、映画祭側からの事前質問のペーパーワーク、会場近くの宿探し、DCPと字幕入れの作業、トレイラーの作成…など、出発前はやることが山積みで、かなりバタバタしたのを覚えています。
僕たちの映画『旅するダンボール』の上映は3日間でしたが、ありがたいことにどの日もほぼ満席状態、口コミ効果もあって、取材も当初の予定より多く入ったので、会場のあるオースティンの街を駆け回っていました。笑いのツボが微妙に違う海外のオーディエンスに伝わるか心配していましたが、その不安を払拭してくれるかのように、上映中はこちらの仕掛け通り、予想通りの声をあげて反応してくれたのは、とても自信に繋がりました。
これまでエディター・監督として多くの作品に関わってきましたが、作っては次の作品へ、それが終わるとまた次へ…と、完成した作品を多くの人に見せることやその反応を見ることに時間を割いてきませんでした。そのせいか、今回も自分の作品について意見がまとまらないままワールドプレミアを迎え、ここぞというときに意見を求められたらすぐ打ち返す“瞬発力”がなかったのは、反省すべきところです。
SXSWは新人の登竜門としても有名ですが、映画、音楽、IT業界の出会いの場でもあります。今、世界は何に注目をしているのか? どんなものに興味があるのか? 畑違いの人たちからの意見は、映像制作の大きなヒントにもなります。『旅するダンボール』のテーマである“アップサイクル”という概念も、普段から世界に目を向けているプロデューサーがいたからこそ出てきたワードでした。映画祭などを通じて、こうしたプロデューサーの嗅覚をぜひ自分も磨きたいと思います」

▲作品が上映される劇場「ALAMO」の前で記念撮影。

▲映画祭会場内に作品のチラシを貼りまくる。

▲海外メディアから取材を受ける岡島監督。

▲公式のブランチではクリエイター同士で意見交換ができる。

▲会期中に訪れたロバート・ロドリゲス監督のトラブルメーカー・スタジオ。
教えて!矢田部PD
Q. 国際映画祭における「#MeToo」問題は?
A. “不公平感”への意識が高い
「カンヌをはじめ海外の映画祭に行くと、女性監督を取り巻く現状に対する不公平感への意識が高いと実感させられます。以前、トルコのイスタンブール映画祭でシンポジウムに参加した時の話なんですが、最前列に座っていた女性に『あなたの映画祭では女性監督の数が少ないと思いませんか?』と質問されたことも。実際、TIFFでは性別を問わず、映画のクオリティでしか判断していないんですが、そもそも#MeToo問題は、日本にあまり上陸しなかったのではないかと。それぐらい海外では、女性監督への意識喚起が注目されているんです」

▲TIFFで注目された、15名の女性監督による『21世紀の女の子』。©2018 TIFF
『真っ赤な星』
全国順次公開
(監)(脚)井樫彩(撮)萩原脩(編)小林美優(出)小松未来、桜井ユキ ほか
『溶ける』で国内外の注目を集めた若手映像作家・井樫彩による初長編作品。14歳の少女と27歳の女性の“交わることのない”恋心の行方を繊細なタッチとビビッドな色彩で描く。
2018年/日本/カラー/DCP/16:9/101分

©「真っ赤な星」製作委員会
『旅するダンボール』
全国順次公開
(監)(撮)(編)岡島龍介(製)汐巻裕子(音)吉田大致(出)島津冬樹
ダンボール製の財布を創作する“段ボールアーティスト”島津冬樹氏に迫ったドキュメンタリー。島津氏の日々の活動に捉えながら、温かな目線でアップサイクルの可能性を伝える。
2018年/日本/カラー/DCP/1.85:1/91分

© 2018 pictures dept. All Rights Reserved
●ビデオSALON2019年1月号より転載


