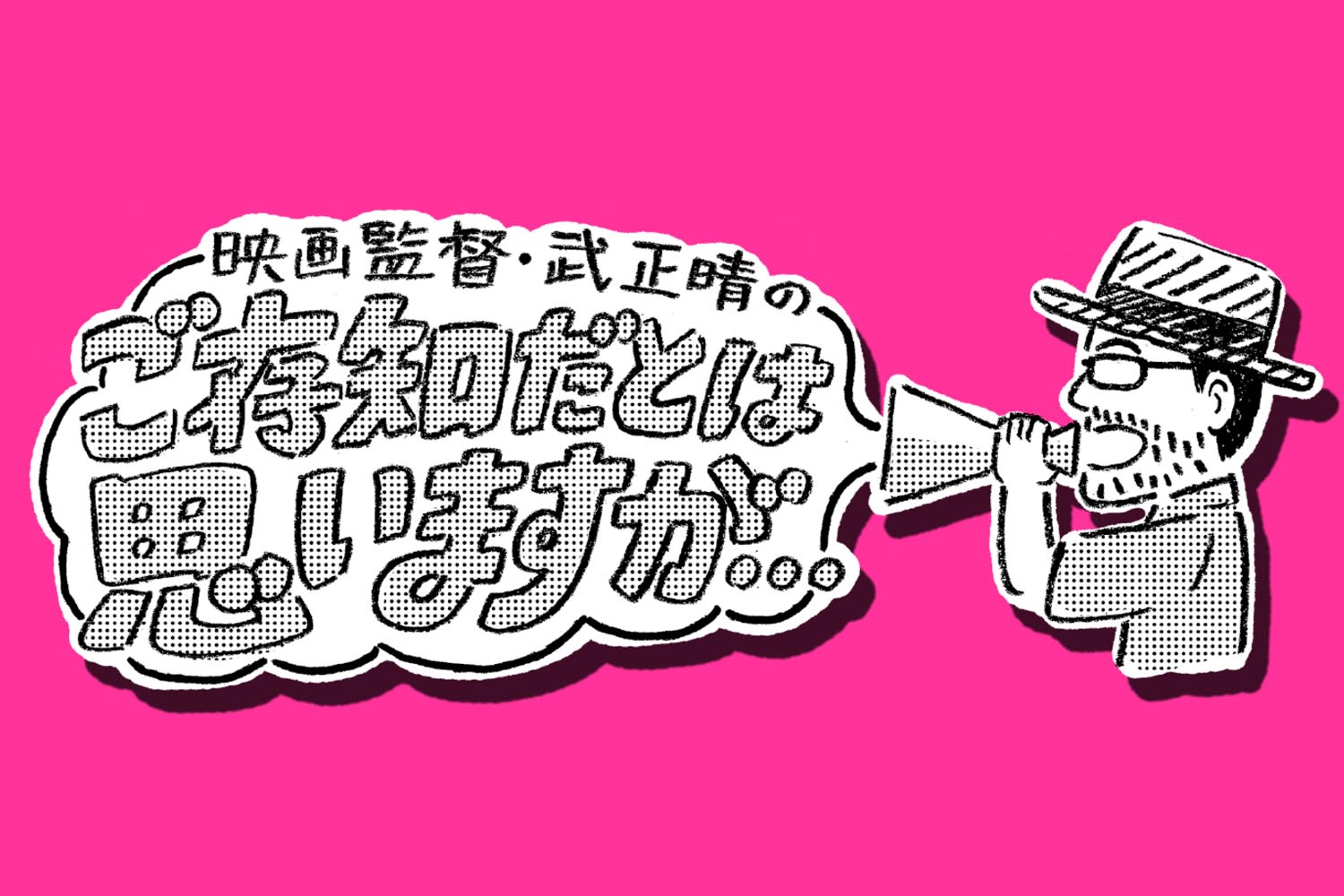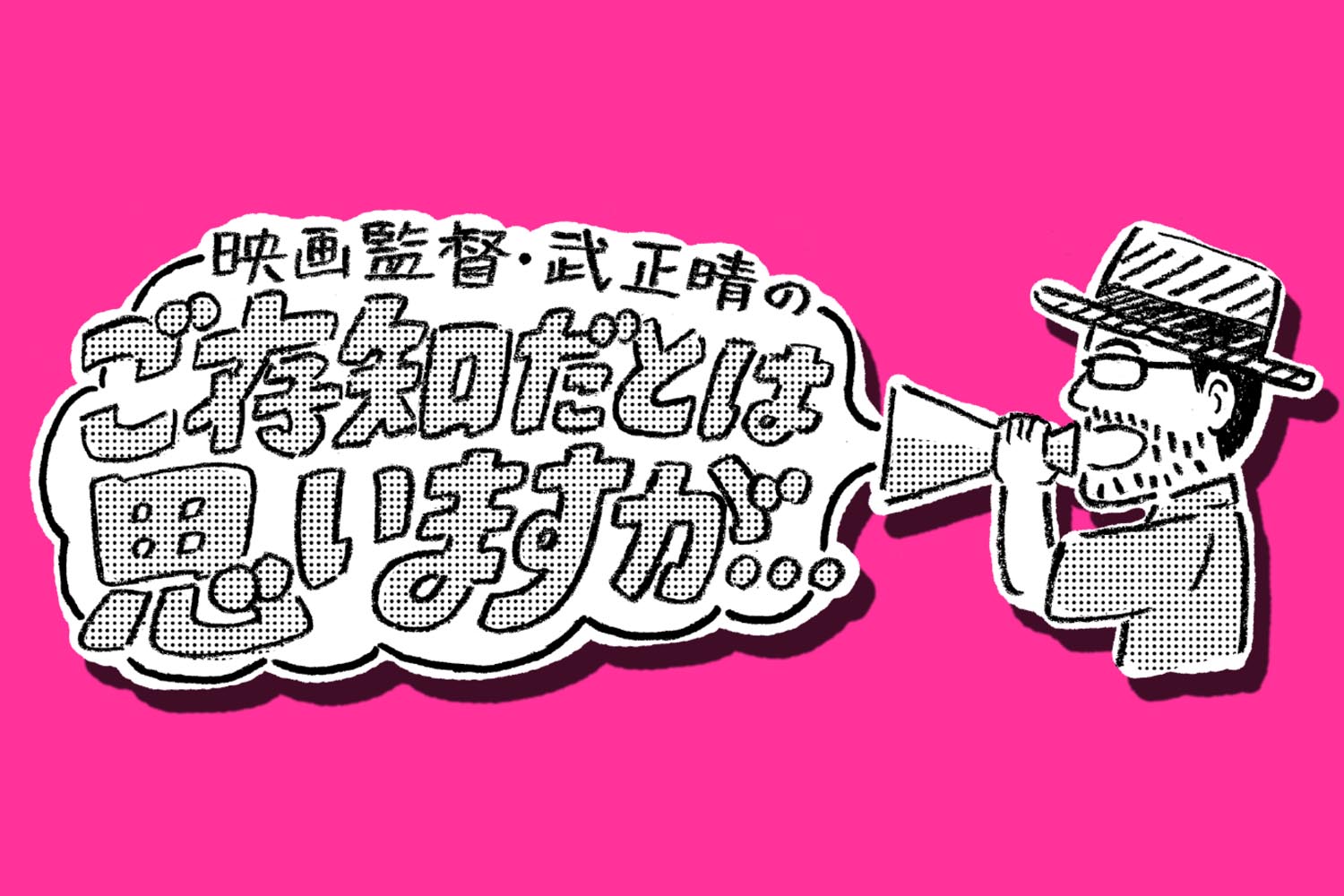
中・高・大と映画に明け暮れた日々。
あの頃、作り手ではなかった自分が
なぜそこまで映画に夢中になれたのか?
作り手になった今、その視点から
忘れられないワンシーン・ワンカットの魅力に
改めて向き合ってみる。
文●武 正晴
第8回『ラストショー』

イラスト●死後くん
____________________________
朝鮮戦争が始まった頃のテキサスの小さな町アナリーン。町で唯一の映画館は若者たちの社交場になっていた。そんな何もない町で多感な時期の青春の夢とその終わりを描く。原題はLast Picture Show。原作者のラリー・マクマートリーの半自伝的な作品。
製作年 1971年
製作国 アメリカ
上映時間 118分
アスペクト比 ビスタ
監督 ピーター・ボグダノヴィッチ
脚本 ラリー・マクマートリー
ピーター・ボグダノヴィッチ
撮影 ロバート・サーティース
編集 ドン・キャンバーン
出演 ティモシー・ボトムズ
ジェフ・ブリッジス
シビル・シェパード
クロリス・リーチマン
ベン・ジョンソン他
____________________________
※この連載は2015年12月号に掲載した内容を転載しています。
東京国際映画祭でピーター・ボグダノヴィッチの新作上映
今年(2015年)で東京国際映画祭が28回目を迎えた。僕が東京に来た年から始まっているから30年近くになる。昨年初めて拙作『百円の恋』を出品し、賞までいただけたのだが、一番の驚きはピーター・ボグダノビヴィッチ監督が新作コメディを引っ提げてサプライズ来日したことだった。
突然の来日に映画祭関係者も僕もうれしい悲鳴をあげていた。13年振りの新作にマスコミからの「今まで何をしていたのか?」という意地悪な質問にも「とにかく色々やることがあって凄く忙しかったのだよ」と茶目っ気たっぷりに75歳の名匠は笑わせてくれた。急遽、京橋にあるフィルムセンターでMOMAニューヨーク近代美術館映画コレクションの特別上映で名匠による上映前の講義に駆けつけた。
映画評論家、研究家としても一流の名匠はジョン・フォードやオーソン・ウェルズとの交流を誇らしげに語ってくれた。上映作品のジャック・レモン初出演作『有名になる方法教えます』とジョージ・キューカー監督について軽妙に解説してくれた。満員のフィルムセンターの観客にとっても至福な30分となった。
オスカー級の名演が光る
ボクダノビッチ監督作品に初めて出会ったのは高校3年生の時だった。『ラストショー』を名古屋シネマテークで観たのは、会員に向けた定例鑑賞会上映だった。シネマテークの会員だった父親は平日仕事で会社を休む訳にはいかないので、代わりに僕が鑑賞会に行くのだ。僕も学校は平日あるのだが、『ラストショー』は学校で観られないのだから仕方がない。
テキサス州の小さな田舎町アナリーンでの卒業間近の高校生主人公サニー(ティモシー・ボトムズ)とデュエーン(ジェフ・ ブリッジス)の1951年10月から52年11月末までを描いた青春友情ストーリーである。さびれていく町の姿と失われた青春の悲しみをモノクロによる撮影によって見事に捉えている。
ボクダノビッチ監督はオーソンウェルズからこの作品は白黒で撮ることをアドバイスされたそうだ。この主人公2人を翻弄する町一番の美女で金持ちのジェシィー(シビル・シェパード)が良いのだ。僕は一足先に彼女とは『タクシードライバー』のトラヴィスがおか惚れする気まぐれ女ペッツィーとして小学生の時に出会っていたが、『ラストショー』でスクリーンデビューしたシビル・シェパードがなんともスケベな下唇で、挙げ句に丸裸のヌードまで披露してくれて僕もおか惚れしてしまった。
ジェシィーの母親役にエレン・バースティン。サニーが不倫するルース役にクロリス・リーチマン。世話好きの中年ウェートレス役のアイリーン・ブレナンの演技が素晴らしいのだ。リーチマンはこの作品で助演女優賞のオスカーをゲットしているが、他の二人もオスカー級の演技を見せてくれる。
主人公達が憧れる元カウボーイのサム・ザ・ライオンと呼ばれるテキサス男をベン・ジョンソンが演じ、助演男優賞のオスカーをゲットしている。『ワイルドバンチ』や『ゲッタウェイ』のサム・ペキンパーの作品で僕が大好きだったベン・ジョンソンはこの役を3度断ったそうだ。理由は「セリフが多すぎる。馬を遠乗りするような役をやりたい。」監督が「オスカーを絶対獲らせるから」との殺し文句で出演をようやく決めたそうだ。
良きアメリカのフロンティアスピリッツの夢を主人公サニー淡々と語るシーンの長回しでの芝居がオスカーを決定付けた。「一番バカなのは何もしないで老いぼれる事さ」とサム・ザ・ ライオンがスクリーンから僕に笑って話かけてくれた。カメラと人物の距離が的確だ。名優達の名演と息づかいを捉え、届けてくれる。感情がスクリーンに写し出される。
「橋を爆破するぞ」…僕も現場で言ってみたい
リース役のリーチマンが最後に見せた感情のうねりに胸が熱くなる。リハーサルなしで一発本番でトライしたそうだ。リーチマンは不安で監督にもう一度演技させてもらうことを嘆願したが、監督はそれを許さずにOKを与えた。リーチマンは一回きりの名演でオスカーをゲットした。
忘れられない場面がある。ティモシー・ボトムズの実弟であるサム・ボトムズが演じる主人公サニーの弟、ビリーの死の場面だ。このシーンもリハーサルなしの一発本番で挑んだそうだ。動かない弟を抱きかかえ叫んだセリフに熱いものが込み上げてくる。「道を掃いていたんだよ、バカヤロー!」 ティモシー・ボトムズの名演は永遠だ。観て欲しい。
ボクダノビッチ監督は一発本番の時、スタッフに「一回きりしかできない芝居を撮るぞ!」という気持ちから「橋を爆破するぞ」と号令をかけるそうだ。僕もいつか撮影現場で言ってみたい。
朝鮮戦争で出征するデュエーンを誘って、サニーは閉鎖する町の映画館のラスト・ピクチャー・ショウを観に行く。そこではジョン・フォードの『赤い河』が上映されている。監督はテキサス州を舞台にした映画を意識したそうだ。デュエーンが「良い映画だった、前に一度見たことがある」とサニーに言った。僕もスクリーンの前で頷いた。
1つの時代の終わりを告げる象徴としてのラストショー。「野球とテレビのせいだ」ともぎりのおばちゃんが嘆く。1971年度のアカデミー賞でこの映画は6部門でノミネートされた。朝鮮ではなくベトナムへと若い兵士たちは行き先を変えていた。
85年の僕はと言えば
1985年の僕の田舎町には映画館もなかったし、周りにはサム・ザ・ ライオンのような憧れるスピリッツを持った大人もいなかった。もちろん、スケベな下唇のおか惚れするような金持ちの美女の同級生もいなかった。僕にはこの田舎町にいる理由が見つからなかった。
19歳の僕は東京に進路を向けた。出発の日に小・中・高校と一緒だった親友と名古屋駅前の小さな映画館で映画を観た。『アメリカングラフティ』と『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の粋な2本立てだった。
アメグラはテレビで何度か見ていたが、劇場では初めてだった。『バックトゥ』は大評判だったのにロードショーを見逃していたのでありがたかった。文句なしに面白かった。『アメグラ』には少しシミジミしてしまった。映画の後、新幹線のホームまで親友は僕を見送ってくれた。あの駅前の映画館は今はもうなくなってしまった。
この30年で東京も随分変貌した。その頃から続く映画館も僅かを数えるのみだ。いくつもの映画館でラストピクチャーショウに立ち会ってきた。
僕は映画館で映画を観るのが好きだ。それは僕が映画を創る1つの理由でもある。28回目の東京国際映画祭のオープニング上映が『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のロバート・ゼメキス監督の新作だった。あの映画から30年。特別な想いで東京に来ているのではないか。
思い通りの未来ではなかったが、大きく外れているわけでもない。オープニング上映には参加できなかったが、その後のオープニングパーティーに遅参した。ロバート・ゼメキス監督の姿は見つからなかったが、今年1年様々な映画祭で出逢った友人たちの顔を沢山見つけた。懐かしい古くからの映画仲間達の顔も沢山見つけた。温故知新。僕はパーティー会場の入口から、奥へ奥へと進んでいった。
●この記事はビデオSALON2015年12月号より転載
http://www.genkosha.co.jp/vs/backnumber/1503.html
●連載をまとめて読む
http://www.genkosha.com/vs/rensai/gozonji/